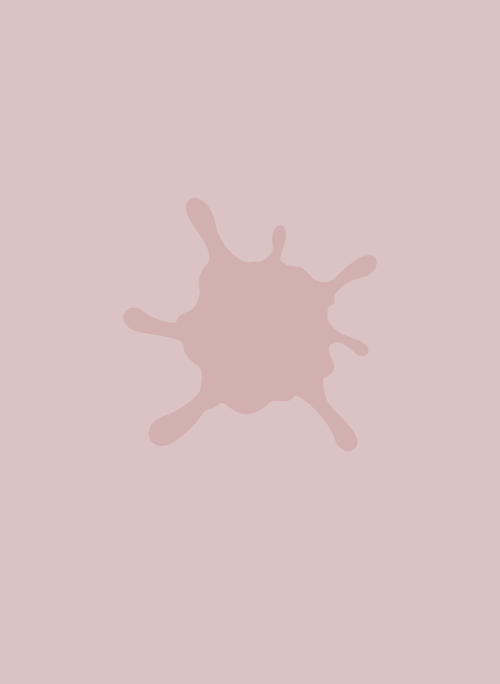プロローグ
夜のキャンパスは、昼間の喧噪が嘘のように静まり返っていた。
薄暗い旧研究棟の廊下は、立ち入る者の気配を拒むように埃の匂いを漂わせている。ここは十年前の火災以来、立入禁止となったまま放置されていた建物だ。
懐中電灯を頼りに進んでいた篠原遼は、ふと足を止めた。
壁に、何かが掻きつけられている。
赤黒くこびりついた線――乾ききった血の色。
それはただの汚れではなかった。よく見ると、乱れた筆跡がひとつの言葉を形作っていた。
「ゆるして」
その瞬間、背筋が凍りついた。
火事で焼け焦げた壁に、どうして今もこんなものが残っているのか。
誰が、何のために、ここに血で文字を刻んだのか。
遼は目を逸らすことができなかった。
それはただの落書きではない。
血文字は、確かに誰かの声だった。
――息絶える間際に、最後の力を振り絞って訴えた「告白」。
だが、その声を聞いたことが彼自身の運命を大きく狂わせることを、まだ遼は知らなかった。
夜のキャンパスは、昼間の喧噪が嘘のように静まり返っていた。
薄暗い旧研究棟の廊下は、立ち入る者の気配を拒むように埃の匂いを漂わせている。ここは十年前の火災以来、立入禁止となったまま放置されていた建物だ。
懐中電灯を頼りに進んでいた篠原遼は、ふと足を止めた。
壁に、何かが掻きつけられている。
赤黒くこびりついた線――乾ききった血の色。
それはただの汚れではなかった。よく見ると、乱れた筆跡がひとつの言葉を形作っていた。
「ゆるして」
その瞬間、背筋が凍りついた。
火事で焼け焦げた壁に、どうして今もこんなものが残っているのか。
誰が、何のために、ここに血で文字を刻んだのか。
遼は目を逸らすことができなかった。
それはただの落書きではない。
血文字は、確かに誰かの声だった。
――息絶える間際に、最後の力を振り絞って訴えた「告白」。
だが、その声を聞いたことが彼自身の運命を大きく狂わせることを、まだ遼は知らなかった。