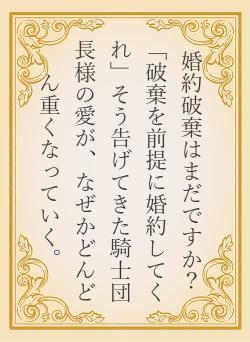体がつらいわけではないのに、何もする気がおきなくて、何もできなくて、無為な時間をただ過ごしていた。
何度試しても、魔法は使えない。
もう、病み上がりなんていう時期は過ぎたのに一向に使える気配はしなかった。
焦って、何度も失敗して、落ち込むばかりだった。
そんな私に、シオン様は無理せずゆっくりしてと言う。
どれだけゆっくりしたって私の魔法が戻るわけじゃないのに。
うすうす感じていた。もう、戻ることはないのではないかと。
そしてシオン様は、月に一度の領地視察に一人で向かった。
申し訳ないと思いながらも、行っても役に立たないと思うと行けなかった。
家に残り、部屋の窓際に座って中庭を眺める。
最近、朝の二人の稽古を見ていない。あんなに楽しみしていたことに心ときめかなくなった。
「本当、自分が嫌になる」
どうしてこんなに苦しいのかはわかっている。
私は今、自分の存在意義を見失っている。
グラーツ家に嫁いで来たのは領地を繫栄させるため。私の能力を買われたから。
魔法が使えない私は、シオン様の妻である資格なんてない。
ぼんやりとしていると、部屋のドアがノックされた。
「はい」
「ティア様、クラウド様がいらっしゃっています」
クラウド様が?
なんの用だろう。シオン様が今いないこと知らないのだろうか。
追い返すこともできないので、客間に通してもらった。
「クラウド様、お久しぶりです。どうされましたか? シオン様は今領地に行っていまして」
「ああ、わかってる。ティア嬢に会いにきたんだ」
「私に?」
「シオンが、自分がいない間ティア嬢の様子をみてくれてって頼んできたんだよ。俺も会いたかったし」
「そう、なのですね」
シオン様がそんなことを……。よほど心配されているんだな。
でも、クラウド様はどうして私に会いたかったのだろう。
「ティア嬢、申し訳なかった」
すると突然、クラウド様は頭を下げた。
「どうしたのですか? 頭を上げてください」
「元は俺と婚約者の問題だったのに、ティア嬢に怪我させて申し訳ないと思ってる」
「でも、クラウド様のせいではありませんから」
あれはお見合い相手の女性が勝手に逆恨みをしたからだ。
それに、私ではなくシオン様を狙っていた。私が飛び出したりなんてせず、シオン様が対応していれば、誰も怪我をすることなく、彼女が重い罪に問われることなく収まっていたかもしれない。
とは言っても、クラウド様は責任を感じているようだった。
私に会いたかったのも、謝罪したかったからだと言った。
そしてあれから、お父様がお見合いを勧めてくることはなくなったそうだ。今回の私が刺された件で反省し、安易に結婚を進めることをやめたらしい。
「クラウド様は、以前言っていた好きな方とは本当に一緒にならなくていいと思っているのですか?」
「ああ。俺は、そいつが笑ってくれてたら、それでいいんだ」
「そう、なのですね……」
以前は、絶対にシオン様とクラウド様に一緒になって欲しいと思っていた。けれど今はなぜかクラウド様の答えにホッといている自分がいる。
でも、気持ちはよくわかる。大切な人に笑っていて欲しいという気持ち。
「ティア嬢、シオンから話は聞いてる。俺が言えたことじゃないが、あんま気負いすぎるなよ」
きっと、魔法が使えずふさぎ込んでいることを言っているのだろう。
励ましてくれているのかもしれないけど、魔法が使えないとグラーツ家に嫁いできた意味がない。
「ですが、妻としてなんの役にも立てません」
「そんなもん、妻としてそこにいるだけで役に立ってるんだよ」
「それはさすがに……」
何もできなければ、本当にただのお飾りの妻になってしまう。
グラーツ家の繫栄に力添えできることが、私の存在意義だったのに。
「とにかくティア嬢、お前は笑っとけ。それだけでシオンは喜ぶんだから」
「はい……ありがとうございます」
クラウド様はじゃあな、と言い帰っていった。
シオン様、わざわざ一人になった私の様子を見て欲しいと頼むなんて、よほど心配してくれているんだ。
気遣いがありがたくもあり、苦しくもある。
何もできない私は、気を遣ってもらう価値なんてない。
でも、本当はシオン様に必要とされる人間でありたい。シオン様と同じ場所に立っていたい。シオン様の隣で笑っていたい。
自分の無力さを実感した今、この居場所がなくなることがすごく怖い。
ああ、そうか。私、シオン様のことが好きなんだ……。
ずっと、気付けなかった。気付くのが遅すぎた。もっと早くに気付けていれば、できたことがあったかもしれないのに。
でも、気付いたからこそ強く思うことがある。
愛する者同士が一緒にいなければいけないと。
シオン様の愛する人は、私じゃない。
『そいつが笑ってくれてたら、それでいいんだ』
私も、シオン様に笑っていて欲しい。
もう、理由をつけて引き延ばしても仕方ない。
潔く、私のほうから別れを告げよう。
何度試しても、魔法は使えない。
もう、病み上がりなんていう時期は過ぎたのに一向に使える気配はしなかった。
焦って、何度も失敗して、落ち込むばかりだった。
そんな私に、シオン様は無理せずゆっくりしてと言う。
どれだけゆっくりしたって私の魔法が戻るわけじゃないのに。
うすうす感じていた。もう、戻ることはないのではないかと。
そしてシオン様は、月に一度の領地視察に一人で向かった。
申し訳ないと思いながらも、行っても役に立たないと思うと行けなかった。
家に残り、部屋の窓際に座って中庭を眺める。
最近、朝の二人の稽古を見ていない。あんなに楽しみしていたことに心ときめかなくなった。
「本当、自分が嫌になる」
どうしてこんなに苦しいのかはわかっている。
私は今、自分の存在意義を見失っている。
グラーツ家に嫁いで来たのは領地を繫栄させるため。私の能力を買われたから。
魔法が使えない私は、シオン様の妻である資格なんてない。
ぼんやりとしていると、部屋のドアがノックされた。
「はい」
「ティア様、クラウド様がいらっしゃっています」
クラウド様が?
なんの用だろう。シオン様が今いないこと知らないのだろうか。
追い返すこともできないので、客間に通してもらった。
「クラウド様、お久しぶりです。どうされましたか? シオン様は今領地に行っていまして」
「ああ、わかってる。ティア嬢に会いにきたんだ」
「私に?」
「シオンが、自分がいない間ティア嬢の様子をみてくれてって頼んできたんだよ。俺も会いたかったし」
「そう、なのですね」
シオン様がそんなことを……。よほど心配されているんだな。
でも、クラウド様はどうして私に会いたかったのだろう。
「ティア嬢、申し訳なかった」
すると突然、クラウド様は頭を下げた。
「どうしたのですか? 頭を上げてください」
「元は俺と婚約者の問題だったのに、ティア嬢に怪我させて申し訳ないと思ってる」
「でも、クラウド様のせいではありませんから」
あれはお見合い相手の女性が勝手に逆恨みをしたからだ。
それに、私ではなくシオン様を狙っていた。私が飛び出したりなんてせず、シオン様が対応していれば、誰も怪我をすることなく、彼女が重い罪に問われることなく収まっていたかもしれない。
とは言っても、クラウド様は責任を感じているようだった。
私に会いたかったのも、謝罪したかったからだと言った。
そしてあれから、お父様がお見合いを勧めてくることはなくなったそうだ。今回の私が刺された件で反省し、安易に結婚を進めることをやめたらしい。
「クラウド様は、以前言っていた好きな方とは本当に一緒にならなくていいと思っているのですか?」
「ああ。俺は、そいつが笑ってくれてたら、それでいいんだ」
「そう、なのですね……」
以前は、絶対にシオン様とクラウド様に一緒になって欲しいと思っていた。けれど今はなぜかクラウド様の答えにホッといている自分がいる。
でも、気持ちはよくわかる。大切な人に笑っていて欲しいという気持ち。
「ティア嬢、シオンから話は聞いてる。俺が言えたことじゃないが、あんま気負いすぎるなよ」
きっと、魔法が使えずふさぎ込んでいることを言っているのだろう。
励ましてくれているのかもしれないけど、魔法が使えないとグラーツ家に嫁いできた意味がない。
「ですが、妻としてなんの役にも立てません」
「そんなもん、妻としてそこにいるだけで役に立ってるんだよ」
「それはさすがに……」
何もできなければ、本当にただのお飾りの妻になってしまう。
グラーツ家の繫栄に力添えできることが、私の存在意義だったのに。
「とにかくティア嬢、お前は笑っとけ。それだけでシオンは喜ぶんだから」
「はい……ありがとうございます」
クラウド様はじゃあな、と言い帰っていった。
シオン様、わざわざ一人になった私の様子を見て欲しいと頼むなんて、よほど心配してくれているんだ。
気遣いがありがたくもあり、苦しくもある。
何もできない私は、気を遣ってもらう価値なんてない。
でも、本当はシオン様に必要とされる人間でありたい。シオン様と同じ場所に立っていたい。シオン様の隣で笑っていたい。
自分の無力さを実感した今、この居場所がなくなることがすごく怖い。
ああ、そうか。私、シオン様のことが好きなんだ……。
ずっと、気付けなかった。気付くのが遅すぎた。もっと早くに気付けていれば、できたことがあったかもしれないのに。
でも、気付いたからこそ強く思うことがある。
愛する者同士が一緒にいなければいけないと。
シオン様の愛する人は、私じゃない。
『そいつが笑ってくれてたら、それでいいんだ』
私も、シオン様に笑っていて欲しい。
もう、理由をつけて引き延ばしても仕方ない。
潔く、私のほうから別れを告げよう。