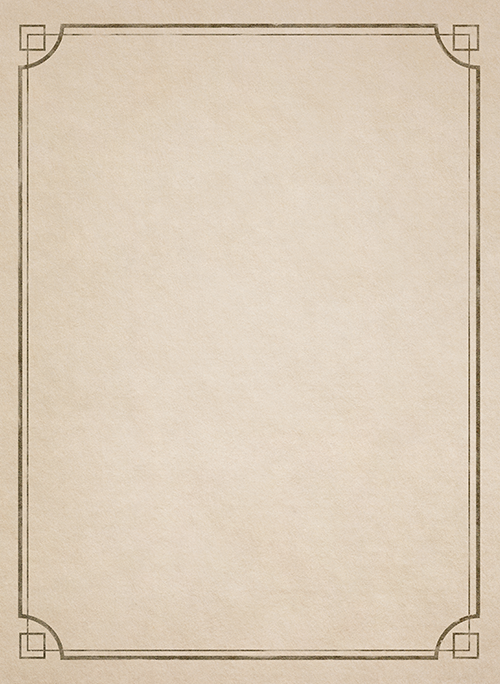週に三度訪れる、彼との時間。それが私の日常の中に、当たり前のように存在し始めてた。
家庭教師の彼と、生徒の私。その役割を演じてる間だけは、私の心にいる罪悪感と彼への気持ちを、授業中という名の下に隠すことができる。
そう思ってた。今日の授業が始まるまでは。
今日の科目は古典。机の上に広げた教科書には、筆で書いたような文字で古い言葉が並んでる。私には、英語の長文と同じくらい意味不明な記号の羅列。
「今日は、万葉集を少し読んでみようか」
彼はそう言って、タブレットに教科書のページを映し出した。いつも通り穏やかな声で、私の苦手意識を見抜いてるみたいに優しい調子。
「万葉集っていうのは、今から千三百年以上も前に作られた日本で一番古い和歌集なんだ。天皇から、身分のない普通の人まで、色々な人たちの歌が集められてる」
彼は歴史の背景から丁寧に説明してくれた。その分かりやすい解説で、私は少しだけ古典への苦手意識が薄れるのを感じてた。
「その中でも、今日は恋の歌を一つ。有名な歌だから、聞いたことがあるかもしれないな」
彼が指で示したのは、教科書に大きく取り上げられてる一首だった。
『君が行く道の長手を繰り畳ね 焼き滅ぼさむ天の火もがも』
「……どういう、意味ですか?」
声に出して読んでみたけど、やっぱり意味が分からない。私が尋ねると、彼は少しだけ口元を緩めて解説を始めた。
「『あなたがこれから旅立ってく長い道のりを、たぐり寄せて畳んで、焼き尽くしちゃうような天の火が欲しい』……まあ、現代語にするとそんな感じかな。すごい情熱的な歌だよね」
「道を、焼き尽くす……?」
「そう。愛しい人が遠くへ行っちゃうのが耐えられない。だから、その人が進む道をいっそ燃やしてなくしちゃいたい、と。そうすれば、ずっと自分のそばにいてくれるのに、っていう激しい恋心の歌なんだ」
彼の言葉が、私の胸にすーっと流れ込んでくるようだった。愛しい人が、遠くへ行っちゃう。その道を、なくしちゃいたい。その気持ちが、痛いほど分かる気がした。
私の目の前にいる、この人。彼は記憶を失って、私にとっては手の届かない遠い場所へ行っちゃったのと同じ。彼と私を隔ててる見えない壁。もし、それを焼き尽くすことができるなら。そうすれば、私たちはまた昔みたいに笑い合えるのかな。
「この歌の面白いところは、相手への愛情が深すぎるあまりに、ちょっと独善的とも言える願いになってる点なんだ。相手の旅の安全を祈るんじゃなくて、行かせたくない、っていう自分の気持ちを優先してる。でも、それくらい強く相手を想ってる、ってことの裏返しでもある」
彼の解説が続く。その一つ一つの言葉が、私の心の柔らかい部分をピンポイントで突いてくる。
自分の気持ちを、優先する。
三年前のあの日。私は、彼に会いたいっていう自分の気持ちを優先してメッセージを送った。大事な話がある、って。あのメッセージがなければ、彼は事故に遭わなかったかもしれない。私の独善的な想いが、彼の未来を、彼の記憶を、奪っちゃった。
教科書に印刷された、たった三十一文字の歌が、まるで私自身の罪を責めてるみたいに思えて見てられなかった。指先がじんわり冷たくなってく。ノートに視線を落としても、ペンを握る手に力が入らない。
「……ユキさん? どうかした?」
不意に、彼が私の名前を呼んだ。その声に、はっと我に返る。いつの間にか、彼の解説は終わってたみたい。
「ああ、いや……すみません、なんでもないです」
慌てて顔を上げると、彼は心配そうに私の顔をのぞき込んでた。その優しい眼差しが、今はすごくつらい。
「疲れてる? ちょっと、顔色が悪いみたいだけど」
「だ、大丈夫です。ちょっと、考え事をしてて……」
「そっか。まあ、無理しないで。分からなかったら、いつでも言って」
彼はそう言って、私のペースに合わせてゆっくり次の解説を始めてくれた。その優しさが、私の胸に温かく広がるのと同時に、針みたいに刺さる。
どうして、あなたはそんなに優しいの。
あなたの記憶を奪った原因かもしれない人間のことなんて、気にしなくていいのに。そう叫びたい気持ちを、私は奥歯をぎゅっと噛んで必死にこらえた。優しくされればされるほど、私の罪悪感は深くて暗い場所に沈んでく。まるで、底なしの泥沼に足を取られちゃったみたい。
◇
授業が終わる頃には、私はすっかり心も体もぐったりしてた。重たい体を引きずるようにして、彼と一緒にリビングに向かう。テーブルの上には、お母さんが用意してくれたお茶とクッキーが置いてあった。
「あら、お疲れ様。森田君、いつもありがとうございます」
キッチンから顔を出したお母さんが、にこやかに言った。
「いえ、とんでもないです。ユキさん、すごく頑張ってますよ」
彼がそう答えると、お母さんは「本当に? よかった」って嬉しそうに笑った。その何気ない会話が、私にはすごく遠い場所で交わされてるように聞こえた。
「さあ、二人とも、ゆっくりしてってください。私、ちょっとご近所さんのところへ行ってきますから」
お母さんはそう言い残して、パタパタ忙しそうに玄関の方へ向かっちゃった。リビングには、私と彼、二人だけが残される。気まずい沈黙が、部屋の空気を重くした。
「……あの、どうぞ」
私は沈黙に耐えきれず、彼にクッキーの皿を差し出した。彼は「ありがとう」って短く言って、一つ手に取る。
「お母さん、明るい人だね」
「……はい。いつも、あんな感じです」
「いいなあ。俺の家は、どっちかっていうと静かだから」
彼はそう言って、ちょっと寂しそうに笑った。その表情に、私は彼の家庭の事情を思い出す。彼のご両親は彼が記憶を失ったことに、きっと心を痛めてるはず。今の彼の言葉に、その一端が表れてるのかも。
「大学は、どうですか。楽しいですか?」
重たい空気を変えたくて、私は当たり障りのない質問をした。
「うん、楽しいよ。サークルとかには入ってないけど、講義は面白いし、気の合う友達もできた」
彼は大学生活について、ポツポツ話し始めた。文学部の講義のこと、新しくできた友人のこと。その話をする彼の横顔は、とても生き生きして見えた。そのことに、私は心の底からホッとする。彼が、彼自身の人生をちゃんと前に進めてる。その事実が、私にとっては何よりの救いだった。
「将来は、どうするんですか?」
話の流れで、私はごく自然にそう尋ねてた。
「将来か……。まだ、はっきりとは決めてないけど」
彼は少し考えるように空を見てから、言った。
「文学関係の仕事に就けたらいいなって思ってる。出版とか、編集とか。言葉を扱う仕事がしたいんだ」
その言葉を聞いた瞬間、私の心臓がドクンって一瞬止まったみたいになった。
言葉を扱う仕事。
それは、中学三年生の時、彼が私に語ってくれた夢と根本的には同じだったから。あの頃の彼は国語の先生になりたいって言ってたけど、その根っこにあった想いは変わらないんだろう。
『俺さ、古い物語とか読んでると、昔の人も今の人も、同じことで悩んだり喜んだりしてるって分かって、面白いんだよな。そういうのを、誰かに伝える仕事がしたい』
夕焼けの教室で、机を並べて話した他愛ない会話。私にとっては、宝石みたいに大切な記憶。彼はそのことなんて、覚えてないはずなのに。
「……どうして、ですか?」
私の声が、ちょっと上ずる。
「うーん、なんでだろうな。昔から、なんとなく。言葉って面白いなって思うんだ。時代が変わっても、人の気持ちってそんなに変わらない。そういう、普遍的なものを扱える仕事って素敵だなって」
彼は少し照れくさそうに、そう語った。その理由も、昔聞いたものとほとんど変わらなかった。
ああ、よかった。
記憶は失われても、彼の本質は何も変わってない。彼っていう人間の中心にある一番大切な部分は、あの事故でも壊れたりしなかったんだ。その事実に、嬉しさと、そしてどうしようもない切なさが一緒にこみ上げてきて、私の目がじんわり熱くなった。
嬉しくて、泣きそうだった。そして、彼が覚えてないっていう事実が、あまりにも悲しくて、泣きそうだった。
◇
感情の波にゆさゆさ揺さぶられて、私はしばらく何も言えずに下を向いてた。そんな私の様子を、彼は静かに見てるみたいだった。
やがて、彼がポツリと言った。
「……やっぱり、不思議だな」
その声は、さっきまでとは違う真剣な調子を帯びてた。私が顔を上げると、彼はまっすぐ私を見つめてた。その瞳の奥がすごく真剣で、私はドキッとする。
「君とこうして話してると、すごく、心が落ち着くんだ」
彼の言葉が、静まり返ったリビングにゆっくり溶けてく。
「家庭教師なんて初めてだから、最初はすごく緊張してた。上手くやれるか不安だったし。でも、ユキさんが相手だと不思議と自然体でいられる。記憶がないのに……まるで、昔からよく知ってる人と話してるみたいに、心が安らぐんだ」
それは、告白だった。
恋愛感情とか、そういうものじゃないのかもしれない。でも、彼の心の奥底からの、嘘偽りのない言葉だってことは痛いほど伝わってきた。
論理的な記憶はなくても、感情に根ざした記憶が彼の中には残ってる。私と一緒にいた時間の、温かい感触だけが彼の心の中に消えずに残ってる。
その可能性が、私の心をぐらぐら揺さぶった。
嬉しい。心の底から、嬉しいと思った。でも、それと同時に恐怖が私の全身を駆け巡る。この穏やかな時間が愛しければ愛しいほど、真実を打ち明けることが怖くなる。
もし、私が全部話しちゃったら?
この、彼が感じてくれてる「安らぎ」は、憎しみや軽蔑に変わっちゃうんじゃないだろうか。そう考えただけで、体がぞくぞくって青くなった。
「……そう、ですか」
私は、そう答えるのが精一杯だった。どんな顔をしていいのか分からなくて、ただ、ぎゅっと握りしめた自分の指先を見つめてた。
彼が帰る時間になった。私は、玄関まで彼を見送りに出る。
「じゃあ、また。今日のところ、ちゃんと復習しておくように」
「……はい」
「無理は、しすぎないでね」
彼は最後にそう言って、私の頭をぽんと軽く一度だけ撫でた。その予想してなかった行動に、私の体は完全に固まっちゃう。彼の手が離れてった後も、髪の上に残る温かい感触が私の思考を真っ白にした。
彼は、それに気づいたのか気づかないのか、ちょっと気まずそうに視線をそらすと、「じゃあ」ともう一度言ってドアを開けて外に出てった。
彼の後ろ姿が、夜の暗闇に消えてく。
私は、閉まったドアの前でしばらく動くことができなかった。彼の言葉と、髪に残る感触が、私の心の中でいつまでも反響してた。
◇
自分の部屋に戻っても、心のざわめきは全然収まらなかった。机に向かっても、教科書を開く気になれない。彼の言葉が、彼の動作が、何度も頭の中で再生される。
『心が、安らぐんだ』
その言葉は、私にとって希望の光であると同時に、絶望への入り口みたいにも思えた。
どうすればいいんだろう。
このまま何も言わずに、家庭教師と生徒の関係を続けるべきなのか。それとも、すべてを打ち明けて彼に判断を委ねるべきなのか。
答えなんて、出るはずもなかった。どっちを選んでも、待ってるのは苦しみかもしれない。でも、このまま嘘を重ねてくのももう限界に近かった。
私は、吸い寄せられるようにベッドの上に置いてあったスマートフォンを手に取った。指が、勝手に動く。ブラウザを開いて、検索窓にいくつかのキーワードを打ち込んだ。
『三年前 交差点 事故』
タップすると、画面には無機質な検索結果のリストがずらりと並んだ。その中の一つに、見覚えのある地名が含まれてるのを見つけて、私はためらいながらもそのリンクをタップした。
表示されたのは、地方新聞社の古いニュース記事だった。
事故の日付。時刻。現場の状況。トラックの運転手の証言。そして、被害者として彼の名前が記されてた。当時、高校二年生。重傷を負い、病院に搬送された、と。
記事の最後には、一枚の写真が添えられてた。
警察による現場検証の様子を撮影した、その写真。見慣れた、あの交差点。私が彼を呼び出した、あの場所。
写真の中央には、彼のものだったんだろうか、ぐちゃぐちゃに変形した自転車の残骸が横たわってた。
その一枚の写真が、私に冷たい現実を突きつけた。
私が、この穏やかな日常を、彼の記憶を、彼の時間を、壊しちゃった。
その紛れもない事実が、重たい鎖みたいに私の心に絡みついてくる。スマートフォンを持つ指が、カタカタ小さく揺れてた。画面に映る無機質な写真が、私の罪の証拠として、静かに、でも雄弁に私を責め立ててるようだった。
家庭教師の彼と、生徒の私。その役割を演じてる間だけは、私の心にいる罪悪感と彼への気持ちを、授業中という名の下に隠すことができる。
そう思ってた。今日の授業が始まるまでは。
今日の科目は古典。机の上に広げた教科書には、筆で書いたような文字で古い言葉が並んでる。私には、英語の長文と同じくらい意味不明な記号の羅列。
「今日は、万葉集を少し読んでみようか」
彼はそう言って、タブレットに教科書のページを映し出した。いつも通り穏やかな声で、私の苦手意識を見抜いてるみたいに優しい調子。
「万葉集っていうのは、今から千三百年以上も前に作られた日本で一番古い和歌集なんだ。天皇から、身分のない普通の人まで、色々な人たちの歌が集められてる」
彼は歴史の背景から丁寧に説明してくれた。その分かりやすい解説で、私は少しだけ古典への苦手意識が薄れるのを感じてた。
「その中でも、今日は恋の歌を一つ。有名な歌だから、聞いたことがあるかもしれないな」
彼が指で示したのは、教科書に大きく取り上げられてる一首だった。
『君が行く道の長手を繰り畳ね 焼き滅ぼさむ天の火もがも』
「……どういう、意味ですか?」
声に出して読んでみたけど、やっぱり意味が分からない。私が尋ねると、彼は少しだけ口元を緩めて解説を始めた。
「『あなたがこれから旅立ってく長い道のりを、たぐり寄せて畳んで、焼き尽くしちゃうような天の火が欲しい』……まあ、現代語にするとそんな感じかな。すごい情熱的な歌だよね」
「道を、焼き尽くす……?」
「そう。愛しい人が遠くへ行っちゃうのが耐えられない。だから、その人が進む道をいっそ燃やしてなくしちゃいたい、と。そうすれば、ずっと自分のそばにいてくれるのに、っていう激しい恋心の歌なんだ」
彼の言葉が、私の胸にすーっと流れ込んでくるようだった。愛しい人が、遠くへ行っちゃう。その道を、なくしちゃいたい。その気持ちが、痛いほど分かる気がした。
私の目の前にいる、この人。彼は記憶を失って、私にとっては手の届かない遠い場所へ行っちゃったのと同じ。彼と私を隔ててる見えない壁。もし、それを焼き尽くすことができるなら。そうすれば、私たちはまた昔みたいに笑い合えるのかな。
「この歌の面白いところは、相手への愛情が深すぎるあまりに、ちょっと独善的とも言える願いになってる点なんだ。相手の旅の安全を祈るんじゃなくて、行かせたくない、っていう自分の気持ちを優先してる。でも、それくらい強く相手を想ってる、ってことの裏返しでもある」
彼の解説が続く。その一つ一つの言葉が、私の心の柔らかい部分をピンポイントで突いてくる。
自分の気持ちを、優先する。
三年前のあの日。私は、彼に会いたいっていう自分の気持ちを優先してメッセージを送った。大事な話がある、って。あのメッセージがなければ、彼は事故に遭わなかったかもしれない。私の独善的な想いが、彼の未来を、彼の記憶を、奪っちゃった。
教科書に印刷された、たった三十一文字の歌が、まるで私自身の罪を責めてるみたいに思えて見てられなかった。指先がじんわり冷たくなってく。ノートに視線を落としても、ペンを握る手に力が入らない。
「……ユキさん? どうかした?」
不意に、彼が私の名前を呼んだ。その声に、はっと我に返る。いつの間にか、彼の解説は終わってたみたい。
「ああ、いや……すみません、なんでもないです」
慌てて顔を上げると、彼は心配そうに私の顔をのぞき込んでた。その優しい眼差しが、今はすごくつらい。
「疲れてる? ちょっと、顔色が悪いみたいだけど」
「だ、大丈夫です。ちょっと、考え事をしてて……」
「そっか。まあ、無理しないで。分からなかったら、いつでも言って」
彼はそう言って、私のペースに合わせてゆっくり次の解説を始めてくれた。その優しさが、私の胸に温かく広がるのと同時に、針みたいに刺さる。
どうして、あなたはそんなに優しいの。
あなたの記憶を奪った原因かもしれない人間のことなんて、気にしなくていいのに。そう叫びたい気持ちを、私は奥歯をぎゅっと噛んで必死にこらえた。優しくされればされるほど、私の罪悪感は深くて暗い場所に沈んでく。まるで、底なしの泥沼に足を取られちゃったみたい。
◇
授業が終わる頃には、私はすっかり心も体もぐったりしてた。重たい体を引きずるようにして、彼と一緒にリビングに向かう。テーブルの上には、お母さんが用意してくれたお茶とクッキーが置いてあった。
「あら、お疲れ様。森田君、いつもありがとうございます」
キッチンから顔を出したお母さんが、にこやかに言った。
「いえ、とんでもないです。ユキさん、すごく頑張ってますよ」
彼がそう答えると、お母さんは「本当に? よかった」って嬉しそうに笑った。その何気ない会話が、私にはすごく遠い場所で交わされてるように聞こえた。
「さあ、二人とも、ゆっくりしてってください。私、ちょっとご近所さんのところへ行ってきますから」
お母さんはそう言い残して、パタパタ忙しそうに玄関の方へ向かっちゃった。リビングには、私と彼、二人だけが残される。気まずい沈黙が、部屋の空気を重くした。
「……あの、どうぞ」
私は沈黙に耐えきれず、彼にクッキーの皿を差し出した。彼は「ありがとう」って短く言って、一つ手に取る。
「お母さん、明るい人だね」
「……はい。いつも、あんな感じです」
「いいなあ。俺の家は、どっちかっていうと静かだから」
彼はそう言って、ちょっと寂しそうに笑った。その表情に、私は彼の家庭の事情を思い出す。彼のご両親は彼が記憶を失ったことに、きっと心を痛めてるはず。今の彼の言葉に、その一端が表れてるのかも。
「大学は、どうですか。楽しいですか?」
重たい空気を変えたくて、私は当たり障りのない質問をした。
「うん、楽しいよ。サークルとかには入ってないけど、講義は面白いし、気の合う友達もできた」
彼は大学生活について、ポツポツ話し始めた。文学部の講義のこと、新しくできた友人のこと。その話をする彼の横顔は、とても生き生きして見えた。そのことに、私は心の底からホッとする。彼が、彼自身の人生をちゃんと前に進めてる。その事実が、私にとっては何よりの救いだった。
「将来は、どうするんですか?」
話の流れで、私はごく自然にそう尋ねてた。
「将来か……。まだ、はっきりとは決めてないけど」
彼は少し考えるように空を見てから、言った。
「文学関係の仕事に就けたらいいなって思ってる。出版とか、編集とか。言葉を扱う仕事がしたいんだ」
その言葉を聞いた瞬間、私の心臓がドクンって一瞬止まったみたいになった。
言葉を扱う仕事。
それは、中学三年生の時、彼が私に語ってくれた夢と根本的には同じだったから。あの頃の彼は国語の先生になりたいって言ってたけど、その根っこにあった想いは変わらないんだろう。
『俺さ、古い物語とか読んでると、昔の人も今の人も、同じことで悩んだり喜んだりしてるって分かって、面白いんだよな。そういうのを、誰かに伝える仕事がしたい』
夕焼けの教室で、机を並べて話した他愛ない会話。私にとっては、宝石みたいに大切な記憶。彼はそのことなんて、覚えてないはずなのに。
「……どうして、ですか?」
私の声が、ちょっと上ずる。
「うーん、なんでだろうな。昔から、なんとなく。言葉って面白いなって思うんだ。時代が変わっても、人の気持ちってそんなに変わらない。そういう、普遍的なものを扱える仕事って素敵だなって」
彼は少し照れくさそうに、そう語った。その理由も、昔聞いたものとほとんど変わらなかった。
ああ、よかった。
記憶は失われても、彼の本質は何も変わってない。彼っていう人間の中心にある一番大切な部分は、あの事故でも壊れたりしなかったんだ。その事実に、嬉しさと、そしてどうしようもない切なさが一緒にこみ上げてきて、私の目がじんわり熱くなった。
嬉しくて、泣きそうだった。そして、彼が覚えてないっていう事実が、あまりにも悲しくて、泣きそうだった。
◇
感情の波にゆさゆさ揺さぶられて、私はしばらく何も言えずに下を向いてた。そんな私の様子を、彼は静かに見てるみたいだった。
やがて、彼がポツリと言った。
「……やっぱり、不思議だな」
その声は、さっきまでとは違う真剣な調子を帯びてた。私が顔を上げると、彼はまっすぐ私を見つめてた。その瞳の奥がすごく真剣で、私はドキッとする。
「君とこうして話してると、すごく、心が落ち着くんだ」
彼の言葉が、静まり返ったリビングにゆっくり溶けてく。
「家庭教師なんて初めてだから、最初はすごく緊張してた。上手くやれるか不安だったし。でも、ユキさんが相手だと不思議と自然体でいられる。記憶がないのに……まるで、昔からよく知ってる人と話してるみたいに、心が安らぐんだ」
それは、告白だった。
恋愛感情とか、そういうものじゃないのかもしれない。でも、彼の心の奥底からの、嘘偽りのない言葉だってことは痛いほど伝わってきた。
論理的な記憶はなくても、感情に根ざした記憶が彼の中には残ってる。私と一緒にいた時間の、温かい感触だけが彼の心の中に消えずに残ってる。
その可能性が、私の心をぐらぐら揺さぶった。
嬉しい。心の底から、嬉しいと思った。でも、それと同時に恐怖が私の全身を駆け巡る。この穏やかな時間が愛しければ愛しいほど、真実を打ち明けることが怖くなる。
もし、私が全部話しちゃったら?
この、彼が感じてくれてる「安らぎ」は、憎しみや軽蔑に変わっちゃうんじゃないだろうか。そう考えただけで、体がぞくぞくって青くなった。
「……そう、ですか」
私は、そう答えるのが精一杯だった。どんな顔をしていいのか分からなくて、ただ、ぎゅっと握りしめた自分の指先を見つめてた。
彼が帰る時間になった。私は、玄関まで彼を見送りに出る。
「じゃあ、また。今日のところ、ちゃんと復習しておくように」
「……はい」
「無理は、しすぎないでね」
彼は最後にそう言って、私の頭をぽんと軽く一度だけ撫でた。その予想してなかった行動に、私の体は完全に固まっちゃう。彼の手が離れてった後も、髪の上に残る温かい感触が私の思考を真っ白にした。
彼は、それに気づいたのか気づかないのか、ちょっと気まずそうに視線をそらすと、「じゃあ」ともう一度言ってドアを開けて外に出てった。
彼の後ろ姿が、夜の暗闇に消えてく。
私は、閉まったドアの前でしばらく動くことができなかった。彼の言葉と、髪に残る感触が、私の心の中でいつまでも反響してた。
◇
自分の部屋に戻っても、心のざわめきは全然収まらなかった。机に向かっても、教科書を開く気になれない。彼の言葉が、彼の動作が、何度も頭の中で再生される。
『心が、安らぐんだ』
その言葉は、私にとって希望の光であると同時に、絶望への入り口みたいにも思えた。
どうすればいいんだろう。
このまま何も言わずに、家庭教師と生徒の関係を続けるべきなのか。それとも、すべてを打ち明けて彼に判断を委ねるべきなのか。
答えなんて、出るはずもなかった。どっちを選んでも、待ってるのは苦しみかもしれない。でも、このまま嘘を重ねてくのももう限界に近かった。
私は、吸い寄せられるようにベッドの上に置いてあったスマートフォンを手に取った。指が、勝手に動く。ブラウザを開いて、検索窓にいくつかのキーワードを打ち込んだ。
『三年前 交差点 事故』
タップすると、画面には無機質な検索結果のリストがずらりと並んだ。その中の一つに、見覚えのある地名が含まれてるのを見つけて、私はためらいながらもそのリンクをタップした。
表示されたのは、地方新聞社の古いニュース記事だった。
事故の日付。時刻。現場の状況。トラックの運転手の証言。そして、被害者として彼の名前が記されてた。当時、高校二年生。重傷を負い、病院に搬送された、と。
記事の最後には、一枚の写真が添えられてた。
警察による現場検証の様子を撮影した、その写真。見慣れた、あの交差点。私が彼を呼び出した、あの場所。
写真の中央には、彼のものだったんだろうか、ぐちゃぐちゃに変形した自転車の残骸が横たわってた。
その一枚の写真が、私に冷たい現実を突きつけた。
私が、この穏やかな日常を、彼の記憶を、彼の時間を、壊しちゃった。
その紛れもない事実が、重たい鎖みたいに私の心に絡みついてくる。スマートフォンを持つ指が、カタカタ小さく揺れてた。画面に映る無機質な写真が、私の罪の証拠として、静かに、でも雄弁に私を責め立ててるようだった。