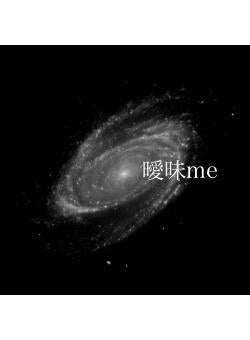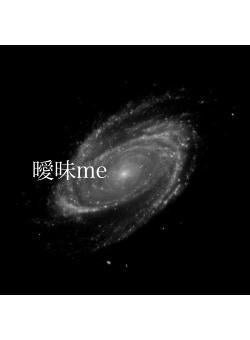「私ね、ときどき、人生を諦めたくなるときがあるんだ。死にたいとか、そんな大袈裟なものじゃないけど。」
彼女はボクの黒い毛を撫でながら、気力のなさに満ちた表情でそう言う。
「消えたいというか、なんというか。どちらかといえば、生きたくないに近いかな。」
彼女は毎晩ここにきては、ただ一人でこんな風にボクに語りかける。
そんなニンゲンの難しい話なんて、ボクに分かるわけないのに。
「なんのために生きてるんだろうとか、どうせ歴史に残ることもなく死ぬのになんで生きてるんだろうとか。」
ボクはただ、「ミャー」と鳴き返す。
そして、そっと彼女の手を掴み返した。
彼女のためにボクができることなんて、これぐらいしかないだろう。
「ねぇ、私、なんで生きてるのかな」
生きる意味なんて、別に探さなくたっていいのに。
ご飯が食べれて、寝ることさえできればボクはそれでいい。
それと、彼女に優しく撫でてもらえればもう十分。
「まぁ、こんなこと言ったってきみに分かるわけないよね。じゃあね。」
彼女は立ち上がり、暗いトンネルへと去っていった。
ボクにはニンゲンのことなんか分からない。だけど、少なくとも彼女は
''生きたいがゆえに生きる理由を探している''
ボクの瞳には、そんな風に見えた。
彼女はボクの黒い毛を撫でながら、気力のなさに満ちた表情でそう言う。
「消えたいというか、なんというか。どちらかといえば、生きたくないに近いかな。」
彼女は毎晩ここにきては、ただ一人でこんな風にボクに語りかける。
そんなニンゲンの難しい話なんて、ボクに分かるわけないのに。
「なんのために生きてるんだろうとか、どうせ歴史に残ることもなく死ぬのになんで生きてるんだろうとか。」
ボクはただ、「ミャー」と鳴き返す。
そして、そっと彼女の手を掴み返した。
彼女のためにボクができることなんて、これぐらいしかないだろう。
「ねぇ、私、なんで生きてるのかな」
生きる意味なんて、別に探さなくたっていいのに。
ご飯が食べれて、寝ることさえできればボクはそれでいい。
それと、彼女に優しく撫でてもらえればもう十分。
「まぁ、こんなこと言ったってきみに分かるわけないよね。じゃあね。」
彼女は立ち上がり、暗いトンネルへと去っていった。
ボクにはニンゲンのことなんか分からない。だけど、少なくとも彼女は
''生きたいがゆえに生きる理由を探している''
ボクの瞳には、そんな風に見えた。