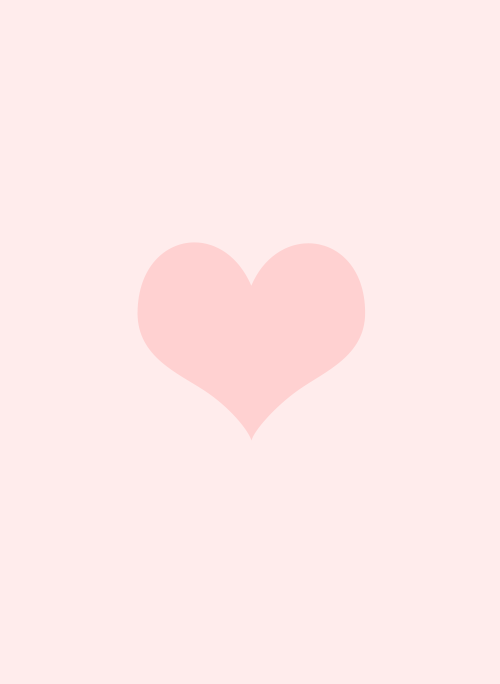「そ、そうだよね!ごめん、変なこと言って!同い年なのに妹とか、意味わかんないよね!」
「…そうじゃ、なくて。」
「え?」
日向の言葉の真意がわからなくて、紫月は少しずつ顔が赤くなっていく日向を見つめた。
「…梅原さんが立夏でも、立夏…あ、妹なんだけど、立夏を撫でるみたいには、撫でられないよ。あんなにぐしゃぐしゃに、乱暴に扱えない。梅原さんは、俺にとってそういう人だから。」
どこまで触れていいのか探るような手が再び、少しだけ動く。距離が近付いた時にだけ香る、日向の香りが今日はずっと近くにあるように感じる。
「…帰れなくなっちゃうな、これじゃ。…勿体ないけど、おしまいにします。」
遠ざかっていく手が、初めてなのに名残惜しい。こんなに優しい時間が終わってしまうことが勿体ないと思うのは、紫月だって同じだった。でも、それは言えない。日向はもう充分、自分に優しくしてくれた。これ以上を望むなんて図々しいにも程がある。
「マグカップ貸して。洗ってくる。」
「い、一緒に洗います!」
「あ、ほんと?じゃあ、一緒にやろう。」
二人で並んでシンクに立ち、手早く洗って帰り支度をする。
「一緒に帰ろう。送る。」
「えっ、い、いいよ!大丈夫!今日私、日向くんにいっぱい迷惑かけてるし、返せるものは仕事くらいしかないのにそれすら終わってないしで役立たずなので…。」
「全部俺が突っ込んで聞いたことだよ。…それに、梅原さんはめちゃくちゃ鈍感な人なんだなってことがわかったので、俺も行動を改めることにしました。」
「ど、鈍感…?確かに人の気持ちに鈍いかもしれない…けど、そんなにかな。」
「ん-…じゃあたとえばだけど、いつもの梅原さんと違うなって思って声を掛けてくる人がいたとして、その人はなんでその違いに気付けると思う?」
外に出ると夕方まで雨だったからなのか、少し湿度の高い空気がまとわりついた。日向の問いを飲み込んで、一度よく考えてみる。考えあぐねた末、出てきたのは当たり障りのない答えだけだった。
「…観察力が、高いから?」
「うーん、不正解。」
「…そうじゃ、なくて。」
「え?」
日向の言葉の真意がわからなくて、紫月は少しずつ顔が赤くなっていく日向を見つめた。
「…梅原さんが立夏でも、立夏…あ、妹なんだけど、立夏を撫でるみたいには、撫でられないよ。あんなにぐしゃぐしゃに、乱暴に扱えない。梅原さんは、俺にとってそういう人だから。」
どこまで触れていいのか探るような手が再び、少しだけ動く。距離が近付いた時にだけ香る、日向の香りが今日はずっと近くにあるように感じる。
「…帰れなくなっちゃうな、これじゃ。…勿体ないけど、おしまいにします。」
遠ざかっていく手が、初めてなのに名残惜しい。こんなに優しい時間が終わってしまうことが勿体ないと思うのは、紫月だって同じだった。でも、それは言えない。日向はもう充分、自分に優しくしてくれた。これ以上を望むなんて図々しいにも程がある。
「マグカップ貸して。洗ってくる。」
「い、一緒に洗います!」
「あ、ほんと?じゃあ、一緒にやろう。」
二人で並んでシンクに立ち、手早く洗って帰り支度をする。
「一緒に帰ろう。送る。」
「えっ、い、いいよ!大丈夫!今日私、日向くんにいっぱい迷惑かけてるし、返せるものは仕事くらいしかないのにそれすら終わってないしで役立たずなので…。」
「全部俺が突っ込んで聞いたことだよ。…それに、梅原さんはめちゃくちゃ鈍感な人なんだなってことがわかったので、俺も行動を改めることにしました。」
「ど、鈍感…?確かに人の気持ちに鈍いかもしれない…けど、そんなにかな。」
「ん-…じゃあたとえばだけど、いつもの梅原さんと違うなって思って声を掛けてくる人がいたとして、その人はなんでその違いに気付けると思う?」
外に出ると夕方まで雨だったからなのか、少し湿度の高い空気がまとわりついた。日向の問いを飲み込んで、一度よく考えてみる。考えあぐねた末、出てきたのは当たり障りのない答えだけだった。
「…観察力が、高いから?」
「うーん、不正解。」