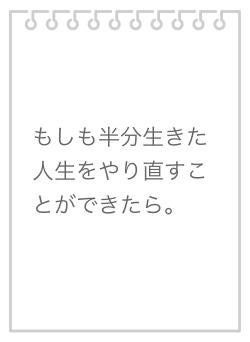家の周りには、警察官が数人立ち、何台ものパトカーがサイレンを止めたまま待機していた。
遠くから近所の人々が、何事かとこちらをうかがっている。
その光景が、母親にこれは夢でも想像でもなく、現実なのだと突きつけた。
「………す、すみません。ここの住人の妻です。娘と夫は……中にいますか?」
しかしその日、母は夫にも、娘にも会うことはできなかった。
途方に暮れ、原付で来た道をそのまま戻り、自宅へ帰る。
夜になり、兄からの連絡で、初めて夫からの電話に出ることになる。
『……もしもし』
「朝日は?!…どこにいるん?!! 大丈夫なん!?」
何度かけても繋がらなかったが、夜になってようやく声がつながった。
母の声は、今にも泣き出しそうに震えていた。
『……すまん』
「ちょっと、待ってよ……いや…“すまん”じゃなくって……」
母の言葉を遮るように、父の低い声が重なった。
『警察の人が……!!自殺で間違いないって。遺書もある。他殺じゃない』
「………」
『…………亡くなってから……もう一週間は経ってたらしい……』
その瞬間、母は声を荒げて泣き出した。
助かるも何も。
あの時、生きていてほしいと願った時には、もう娘はこの世にいなかった。
「あー……。なんでぇ……ちょっと……信じられへんわ……なんでなん……」
大粒の涙をこぼしながら、何度も何度もフローリングを拳で叩く。
「同じ家に住んどったのに……!!なんで…!!?…なんで気づけへんかったんよ!!!」
その言葉は父を責めるものであり、同時に自分自身への怒りでもあった。
どうして最期があんな別れ方だったのか。
なぜ死を選ばせてしまったのか。
「お願い……。お願いやから帰ってきて……。帰ってきてよ……朝日…」
たったひとりの娘だった。
もう連絡を取れなくても、母と子でいられなくても、会話や挨拶がなくても。
息を吸って、吐いて、この世界のどこかで、笑って生きてくれていたら、それだけで良かった。
それだけで良かった。
遠くから近所の人々が、何事かとこちらをうかがっている。
その光景が、母親にこれは夢でも想像でもなく、現実なのだと突きつけた。
「………す、すみません。ここの住人の妻です。娘と夫は……中にいますか?」
しかしその日、母は夫にも、娘にも会うことはできなかった。
途方に暮れ、原付で来た道をそのまま戻り、自宅へ帰る。
夜になり、兄からの連絡で、初めて夫からの電話に出ることになる。
『……もしもし』
「朝日は?!…どこにいるん?!! 大丈夫なん!?」
何度かけても繋がらなかったが、夜になってようやく声がつながった。
母の声は、今にも泣き出しそうに震えていた。
『……すまん』
「ちょっと、待ってよ……いや…“すまん”じゃなくって……」
母の言葉を遮るように、父の低い声が重なった。
『警察の人が……!!自殺で間違いないって。遺書もある。他殺じゃない』
「………」
『…………亡くなってから……もう一週間は経ってたらしい……』
その瞬間、母は声を荒げて泣き出した。
助かるも何も。
あの時、生きていてほしいと願った時には、もう娘はこの世にいなかった。
「あー……。なんでぇ……ちょっと……信じられへんわ……なんでなん……」
大粒の涙をこぼしながら、何度も何度もフローリングを拳で叩く。
「同じ家に住んどったのに……!!なんで…!!?…なんで気づけへんかったんよ!!!」
その言葉は父を責めるものであり、同時に自分自身への怒りでもあった。
どうして最期があんな別れ方だったのか。
なぜ死を選ばせてしまったのか。
「お願い……。お願いやから帰ってきて……。帰ってきてよ……朝日…」
たったひとりの娘だった。
もう連絡を取れなくても、母と子でいられなくても、会話や挨拶がなくても。
息を吸って、吐いて、この世界のどこかで、笑って生きてくれていたら、それだけで良かった。
それだけで良かった。