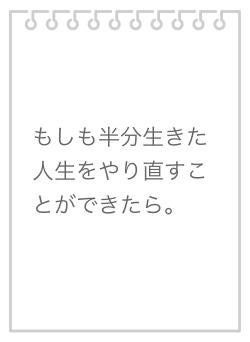――ゴウン。
低い音とともに、火葬炉の扉が完全に閉まる。
父が火入れボタンを押す。
僧侶の読経とりんの音が響き渡る。
内部の炎が立ち上がる機械音が鳴り響く。
母はその場に崩れ落ちた。
呼吸がうまくできない。
喉が詰まり、酸素が入ってこない。
「はぁっ……はぁっ……はぁっ……あ……」
嗚咽とともに、よだれと鼻水が混じって頬を濡らす。
心臓がドクドクと鳴る。
現実が、全身を叩きつけるように押し寄せてくる。
「ゆかりちゃん……外出よう……」
親戚が支える。
母は立ち上がれないまま、引きずられるようにして外へ出た。
外は湿った空気。風が重い。
「……すまん、朝日。申し訳ない……」
父は焼却炉の前に立ち尽くし、誰にも聞こえないほどの声で呟いた。
彼女の身体が、炎の中で形を失っていく。
髪が焼け、皮膚がひび割れ、白い骨が露出し、崩れていく。
やがてそれは、音もなく砕け散り、真っ白な灰になった。
この日も、雨が降っていた。
煙がゆらゆらと立ちのぼり、鈍い空の中に溶けていく。
白い煙だけが、彼女の最期を知っていた。
残された者たちは、
もう二度と戻らない現実を前に、
ただ息をして生きていくしかなかった。
なぜ命を投げ出すしかなかったのか。
誰も、答えを持っていない。
理由は?
原因は?
きっかけは?
誰かに助けを求められなかったのか。
誰かが気づけなかったのか。
話してくれていたら――。
聞くことができていれば――。
今日も、彼女は生きていたのかもしれない。
だが、その「もしも」はもう存在しない。
彼女の気持ちも、真実も、
生きている者にはもう届かない。
わたしたちは「生きていく」ことしかできない。
答え合わせのない現実を抱えたまま。
誰もがその場に縛られたまま、動けずにいた。
82歳になる彼女の祖母が、体を震わし静かに泣いた。
白い煙が、またひと筋、空に溶けていく。