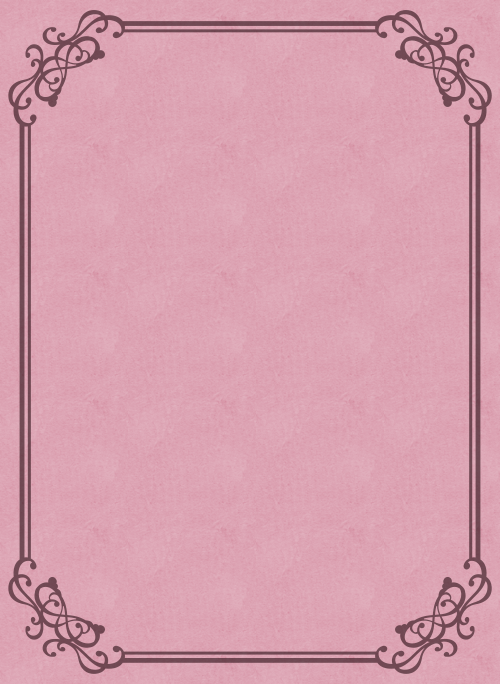数日後、シドはリアンと一緒に広場の噴水で昼食を食べていた。
広場の噴水が詰まったとかでシドが呼ばれていたのだ。
リアンは手作りのサンドイッチを持ってきてくれた。
「あ、そういえば最近まだ誰かに付けられてる?」
「いや、もう誰も付けてきてないようだ。何だったんだろうな。」
「良かったわ。でも気をつけてね。さて、そろそろ仕事に行かなきゃ。」
リアンは王宮に仕えており、王女のお世話係をしていた。
「仕事はどうだ?」
サンドウィッチを頬張りながらシドはリアンに問いかけた。
「相変わらずよ。私の仕えてる王女様は王室御一家の中でもなんていうか…馴染めていなくて。見ていてお可哀想よ。」
「へー。王女なら溺愛されて甘やかされているんじゃないんだな。」
シドの言葉にリアンは首を横に張った。
リアンは王宮に向かい、シドは今日はもうまじないの依頼はなかったので、家に帰った。
すると、シドのアパートの前に豪華な馬車が一台停められていた。
中から男性が1人降りてきた。
「…シドさんですね?」
「…あんたは?」
すると男性は胸ポケットから手紙を一通差し出した。
「王室付魔法使いロザリア様からシドさんに宛てたお手紙です。」
「王室付魔法使い?!」
シドは手紙を受け取った。
「内容をご確認ください。それでは。」
馬車が出ると、シドはその場で手紙をビリビリと開けてみた。
広場の噴水が詰まったとかでシドが呼ばれていたのだ。
リアンは手作りのサンドイッチを持ってきてくれた。
「あ、そういえば最近まだ誰かに付けられてる?」
「いや、もう誰も付けてきてないようだ。何だったんだろうな。」
「良かったわ。でも気をつけてね。さて、そろそろ仕事に行かなきゃ。」
リアンは王宮に仕えており、王女のお世話係をしていた。
「仕事はどうだ?」
サンドウィッチを頬張りながらシドはリアンに問いかけた。
「相変わらずよ。私の仕えてる王女様は王室御一家の中でもなんていうか…馴染めていなくて。見ていてお可哀想よ。」
「へー。王女なら溺愛されて甘やかされているんじゃないんだな。」
シドの言葉にリアンは首を横に張った。
リアンは王宮に向かい、シドは今日はもうまじないの依頼はなかったので、家に帰った。
すると、シドのアパートの前に豪華な馬車が一台停められていた。
中から男性が1人降りてきた。
「…シドさんですね?」
「…あんたは?」
すると男性は胸ポケットから手紙を一通差し出した。
「王室付魔法使いロザリア様からシドさんに宛てたお手紙です。」
「王室付魔法使い?!」
シドは手紙を受け取った。
「内容をご確認ください。それでは。」
馬車が出ると、シドはその場で手紙をビリビリと開けてみた。