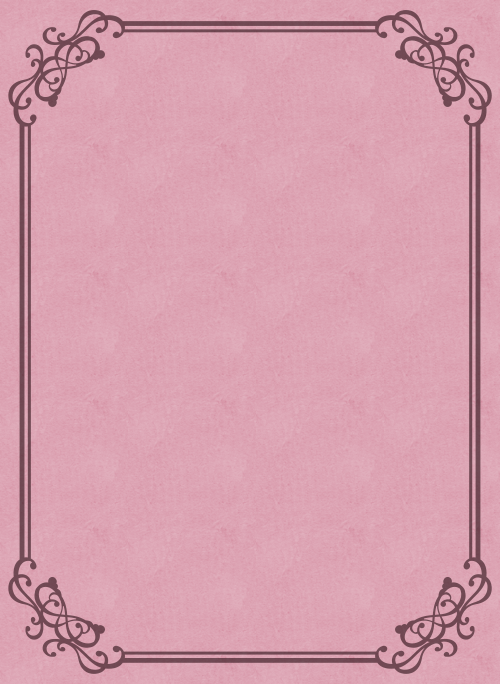湖畔に吹く夏風が、白のドレスとシャツをふわりと揺らす。
「この塔は、大昔の国王が王妃様のために建てたそうよ。」
アリスが、塔を見上げながらそう話した。シドは横で小さく頷いた。
「……なるほど。落ち着く場所だ」
ふたりは柔らかに微笑み合った。
そのとき、塔の前で呼ばれたアリスが「少しだけ」と言ってその場を離れる。手にしていたグラスを揺らしながら、白いドレスの裾をひらりと揺らして。
シドがその場にひとりになった瞬間だった。
「君が……シドだな。」
静かに、だが確かに気配をまとって近づいてきたのは、王太子ルイだった。
シドが向き直ると、白の礼装に身を包んだ彼は微笑を浮かべていたが、その瞳の奥には揺らがぬ鋭さが潜んでいた。
「妹とは、ずいぶん親しそうだったな。」
「……殿下。」
シドは一歩引いて頭を下げた。だがルイはそれを気にするでもなく、シドの横に立つと、同じように塔を見上げる。
「毎年思う。いつかの国王は、この塔を贈ることで、王妃に何を与えたかったのか。王宮からの“自由”?それとも、“静けさ”か。」
そして、塔から視線を外し、真正面からシドを見据えた。
「君は、どこの出身だったかな?」
あくまで穏やかに、ただの会話の延長のように――それでいて、明確に“答え”を求める目。
シドの胸の奥が、ぎゅっと硬くなる。
「…………」
言葉に詰まった瞬間、その緊張を切るように、横からやわらかな声が割り込んできた。
「まぁ、殿下ったら意地悪。初対面でそれを聞くのはさすがに無粋よ。」
ロザリアだった。
白銀の髪を風になびかせ、手にグラスを持ったまま、すっとルイとシドの間に入る。
「彼は私の補佐官です。出身地を気にするより、今この国でどれだけ尽くしてくれているかをご覧になっては?」
ロザリアの笑顔は柔らかいが、その言葉にははっきりとした“壁”のようなものがあった。
ルイは視線をロザリアに移すと、ほんのわずかに口元を緩めた。
「……そうだったな。気を悪くしたなら、すまない。少し気になっただけなんだ。」
そのままグラスを傾け、静かにその場を離れていった。
残されたシドは、風が吹き抜ける中に立ち尽くしていた。
(――まさか、本当に気づいて……?)
ロザリアは何も言わず、ただ一歩近づいてシドの肩に軽く触れた。
「気をつけて。あなたは、すでに“見られている”のよ。」
「この塔は、大昔の国王が王妃様のために建てたそうよ。」
アリスが、塔を見上げながらそう話した。シドは横で小さく頷いた。
「……なるほど。落ち着く場所だ」
ふたりは柔らかに微笑み合った。
そのとき、塔の前で呼ばれたアリスが「少しだけ」と言ってその場を離れる。手にしていたグラスを揺らしながら、白いドレスの裾をひらりと揺らして。
シドがその場にひとりになった瞬間だった。
「君が……シドだな。」
静かに、だが確かに気配をまとって近づいてきたのは、王太子ルイだった。
シドが向き直ると、白の礼装に身を包んだ彼は微笑を浮かべていたが、その瞳の奥には揺らがぬ鋭さが潜んでいた。
「妹とは、ずいぶん親しそうだったな。」
「……殿下。」
シドは一歩引いて頭を下げた。だがルイはそれを気にするでもなく、シドの横に立つと、同じように塔を見上げる。
「毎年思う。いつかの国王は、この塔を贈ることで、王妃に何を与えたかったのか。王宮からの“自由”?それとも、“静けさ”か。」
そして、塔から視線を外し、真正面からシドを見据えた。
「君は、どこの出身だったかな?」
あくまで穏やかに、ただの会話の延長のように――それでいて、明確に“答え”を求める目。
シドの胸の奥が、ぎゅっと硬くなる。
「…………」
言葉に詰まった瞬間、その緊張を切るように、横からやわらかな声が割り込んできた。
「まぁ、殿下ったら意地悪。初対面でそれを聞くのはさすがに無粋よ。」
ロザリアだった。
白銀の髪を風になびかせ、手にグラスを持ったまま、すっとルイとシドの間に入る。
「彼は私の補佐官です。出身地を気にするより、今この国でどれだけ尽くしてくれているかをご覧になっては?」
ロザリアの笑顔は柔らかいが、その言葉にははっきりとした“壁”のようなものがあった。
ルイは視線をロザリアに移すと、ほんのわずかに口元を緩めた。
「……そうだったな。気を悪くしたなら、すまない。少し気になっただけなんだ。」
そのままグラスを傾け、静かにその場を離れていった。
残されたシドは、風が吹き抜ける中に立ち尽くしていた。
(――まさか、本当に気づいて……?)
ロザリアは何も言わず、ただ一歩近づいてシドの肩に軽く触れた。
「気をつけて。あなたは、すでに“見られている”のよ。」