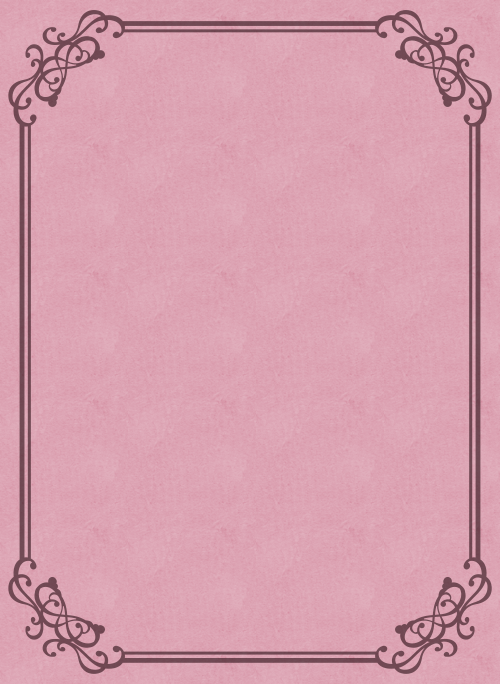王太子ルイは、書斎の机に広げられた一枚の紙をじっと見つめていた。
それは、明日のガーデンパーティーの参加者名簿――
「今年は母上、欠席なさるそうだ」
そう告げると、部屋の奥から妻ソフィアの声が返ってきた。
「また? これで何度目になるかしら。もうお義父様との公務には出ないって噂ね」
「噂じゃない。ほぼ確定だよ。父上との間には、もう表面上のつながりすら残っていないようだ」
ルイの口調は静かだったが、その瞳には複雑な色が浮かんでいた。
ソフィアは窓辺に腰かけて言う。
「アリスは? 出席するの?」
「名簿には名がある。だが……さあな。来るかどうかまでは分からない」
ソフィアがくすっと笑う。
「妹なのに冷たいわね」
それに、ルイは少しうつむいて微笑んだ。
「そんなことはないさ。……いつだって心配しているよ。だがアリスは、俺を――両親と同じように、遠ざけているからな」
ふと視線を逸らしたルイの表情には、どこか寂しげな影が差していた。
「昔は、もっと近かったんだ。だが、気づけばアリスとの距離はどんどん遠くなっていた。……俺は“王になるため”に育てられ、周囲もそう扱ってきた。それが、アリスを孤独にさせたのかもしれない」
ソフィアは小さく肩をすくめ、気まずさを軽く受け流すように話題を変えた。
「そういえば、明日のパーティーには、あの魔法大臣の補佐も出席するそうよ。名前……シドだったかしら?」
「……ああ。気にはなっている」
そう答えたところで、控えの侍女が扉をノックした。
差し出されたのは、一通の手紙。封に刻まれた印章を見て、ルイの眉がぴくりと動いた。
「……アスタリト?」
ソフィアが小首を傾げる。
「あなた、行ったことあったかしら?」
「ないな。距離もあるし、これまであまり外交の関わりもなかった国だ」
封を切り、中の書状に目を通した途端、ルイの表情が変わる。
その瞳に浮かんだのは、驚愕か、あるいは疑念か。
「ルイ……?」
ソフィアが不思議そうに問いかけたが、ルイはすぐに手紙を畳んだ。
「……いや、なんでもない。」
彼の目はどこか遠くを見ていた――
その書状には、シドという名が、はっきりと記されていた。
それは、明日のガーデンパーティーの参加者名簿――
「今年は母上、欠席なさるそうだ」
そう告げると、部屋の奥から妻ソフィアの声が返ってきた。
「また? これで何度目になるかしら。もうお義父様との公務には出ないって噂ね」
「噂じゃない。ほぼ確定だよ。父上との間には、もう表面上のつながりすら残っていないようだ」
ルイの口調は静かだったが、その瞳には複雑な色が浮かんでいた。
ソフィアは窓辺に腰かけて言う。
「アリスは? 出席するの?」
「名簿には名がある。だが……さあな。来るかどうかまでは分からない」
ソフィアがくすっと笑う。
「妹なのに冷たいわね」
それに、ルイは少しうつむいて微笑んだ。
「そんなことはないさ。……いつだって心配しているよ。だがアリスは、俺を――両親と同じように、遠ざけているからな」
ふと視線を逸らしたルイの表情には、どこか寂しげな影が差していた。
「昔は、もっと近かったんだ。だが、気づけばアリスとの距離はどんどん遠くなっていた。……俺は“王になるため”に育てられ、周囲もそう扱ってきた。それが、アリスを孤独にさせたのかもしれない」
ソフィアは小さく肩をすくめ、気まずさを軽く受け流すように話題を変えた。
「そういえば、明日のパーティーには、あの魔法大臣の補佐も出席するそうよ。名前……シドだったかしら?」
「……ああ。気にはなっている」
そう答えたところで、控えの侍女が扉をノックした。
差し出されたのは、一通の手紙。封に刻まれた印章を見て、ルイの眉がぴくりと動いた。
「……アスタリト?」
ソフィアが小首を傾げる。
「あなた、行ったことあったかしら?」
「ないな。距離もあるし、これまであまり外交の関わりもなかった国だ」
封を切り、中の書状に目を通した途端、ルイの表情が変わる。
その瞳に浮かんだのは、驚愕か、あるいは疑念か。
「ルイ……?」
ソフィアが不思議そうに問いかけたが、ルイはすぐに手紙を畳んだ。
「……いや、なんでもない。」
彼の目はどこか遠くを見ていた――
その書状には、シドという名が、はっきりと記されていた。