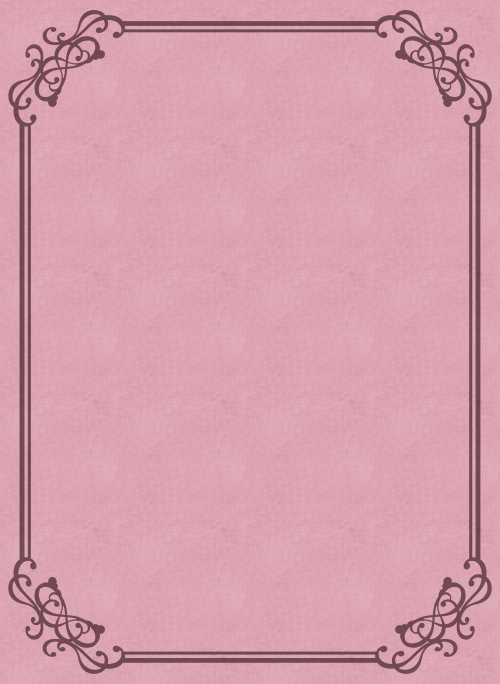年に一度、王宮の夏の風物詩として開かれる「白のガーデンパーティー」。
その舞台は、宮殿の敷地奥に広がる湖の中に浮かぶ小さな島――湖心の島と呼ばれ、島には古い石造りの塔がひとつ建っている。かつて、王妃がしきたりや儀礼から逃れ、心を休めるために作られたとされるその場所は、今では華やかな貴族たちの社交の場に姿を変えていた。
パーティーには厳格なドレスコードがあり、それは“白”。
衣装だけでなく、装飾や花々、調度のすべてが白を基調に揃えられ、まるで夢の中の宴のような幻想的な空間が演出される。……それを、アリスは心の底からうんざりしていた。
「毎年毎年、なんで白なのよ……。誰が考えたのよ、こんなガーデンパーティー。」
自室で控えめなため息を吐きながら、アリスはドレッサーの前に座っていた。侍女が用意した真っ白なドレスがハンガーに吊るされている。ふんわりと広がるスカートに、透けるようなレースの袖。形も生地も文句はない。けれど、問題はその“真っ白”という統一感だ。
「清楚で可憐な王女」を演出するには、あまりにも息が詰まる。
毎年のことなのに、慣れるどころか年々耐え難くなってきた。社交や形式にうんざりする自分に気づくたび、「王女」としての肩書きがひどく窮屈に感じられる。
けれど――。
「……シドも来るんでしょ、今年は」
ぽつりと呟いたその声は、どこか軽やかだった。
この間の剣術大会で一躍注目を浴びた、魔法使いの青年――シド。
ロザリアの補佐として王宮にやってきた、あの無口で素っ気ない男が、まさかあれほどの腕を隠していたとは。侍女たちの間ではすでに「無口な剣士魔法使い」として大人気で、今回のガーデンパーティーでも注目の的になることは間違いなかった。
「……まぁ、見てるだけなら、少しは退屈まぎれにはなるかも」
自分でも理由ははっきりしない。
けれど彼が来ると知ってから、今年の白に染まる宴が、ほんのすこしだけ違って見えたのは――否定できない事実だった。
その舞台は、宮殿の敷地奥に広がる湖の中に浮かぶ小さな島――湖心の島と呼ばれ、島には古い石造りの塔がひとつ建っている。かつて、王妃がしきたりや儀礼から逃れ、心を休めるために作られたとされるその場所は、今では華やかな貴族たちの社交の場に姿を変えていた。
パーティーには厳格なドレスコードがあり、それは“白”。
衣装だけでなく、装飾や花々、調度のすべてが白を基調に揃えられ、まるで夢の中の宴のような幻想的な空間が演出される。……それを、アリスは心の底からうんざりしていた。
「毎年毎年、なんで白なのよ……。誰が考えたのよ、こんなガーデンパーティー。」
自室で控えめなため息を吐きながら、アリスはドレッサーの前に座っていた。侍女が用意した真っ白なドレスがハンガーに吊るされている。ふんわりと広がるスカートに、透けるようなレースの袖。形も生地も文句はない。けれど、問題はその“真っ白”という統一感だ。
「清楚で可憐な王女」を演出するには、あまりにも息が詰まる。
毎年のことなのに、慣れるどころか年々耐え難くなってきた。社交や形式にうんざりする自分に気づくたび、「王女」としての肩書きがひどく窮屈に感じられる。
けれど――。
「……シドも来るんでしょ、今年は」
ぽつりと呟いたその声は、どこか軽やかだった。
この間の剣術大会で一躍注目を浴びた、魔法使いの青年――シド。
ロザリアの補佐として王宮にやってきた、あの無口で素っ気ない男が、まさかあれほどの腕を隠していたとは。侍女たちの間ではすでに「無口な剣士魔法使い」として大人気で、今回のガーデンパーティーでも注目の的になることは間違いなかった。
「……まぁ、見てるだけなら、少しは退屈まぎれにはなるかも」
自分でも理由ははっきりしない。
けれど彼が来ると知ってから、今年の白に染まる宴が、ほんのすこしだけ違って見えたのは――否定できない事実だった。