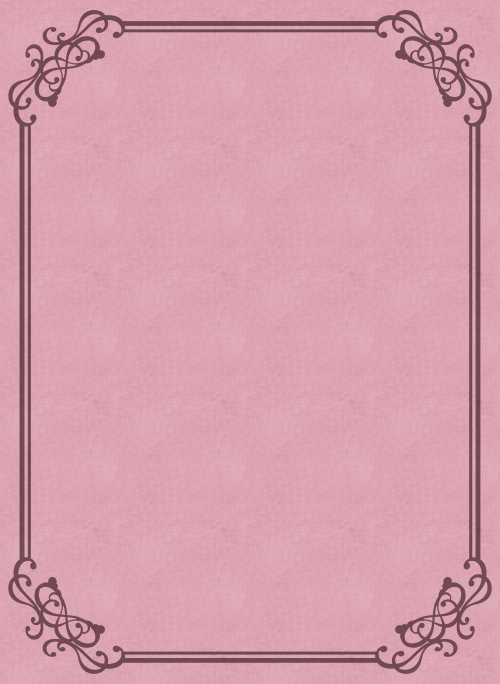貴族たちが列をなす観覧席。眩しい日差しの中、練り上げられた演技用の砂が敷き詰められた剣術場を見下ろしながら、ロザリアは手元のグラスを揺らした。
風は少し強い。砂が舞い上がるほどではないが、日傘を持たない貴婦人たちはすでにうんざりしている様子だった。
だが、ロザリアにとっては快適な気候だった。
隣に座る側近のエドが眉をひそめ、手元の参加者名簿を指でなぞった。
「……まさか、シドが出場しているとは思わなくて。これは本当にご本人ですか?」
「ええ、間違いなく」
ロザリアは涼しげに微笑み、頷いた。
「あたしがシドをエントリーしたの。シドは知らないけどね。」
「ですが……退治屋をしていたとはいえ、魔物と人間の戦いは違うはずです。剣術大会なんて、まともに経験があるとは思えませんが……」
エドの冷静な分析に、ロザリアはくすりと笑った。
視線はそのまま、遠くの控え室に向けられている。
「退治屋じゃなく、よ」
「え?」
エドが聞き返すと、ロザリアはわざといたずらっぽく意味を濁した。
「少なくとも、彼はただの町の剣士じゃないわ。…ねぇ、こういうの、面白いと思わない? 誰も彼の過去を知らないまま、強さだけが先に舞台に上がる。貴族の若者たちが次々に驚いていく様子、見ものじゃない?」
「……まるで、用意された劇を観ているみたいですね」
「ふふ。あら、少し違うわ。これは“彼”が選んだ舞台よ」
ロザリアはまた視線を戻し、静かにグラスを置いた。
彼女の目には、ただの剣術大会ではなく、シドという青年の“過去”と“現在”が交差する瞬間が見えていた。た
風は少し強い。砂が舞い上がるほどではないが、日傘を持たない貴婦人たちはすでにうんざりしている様子だった。
だが、ロザリアにとっては快適な気候だった。
隣に座る側近のエドが眉をひそめ、手元の参加者名簿を指でなぞった。
「……まさか、シドが出場しているとは思わなくて。これは本当にご本人ですか?」
「ええ、間違いなく」
ロザリアは涼しげに微笑み、頷いた。
「あたしがシドをエントリーしたの。シドは知らないけどね。」
「ですが……退治屋をしていたとはいえ、魔物と人間の戦いは違うはずです。剣術大会なんて、まともに経験があるとは思えませんが……」
エドの冷静な分析に、ロザリアはくすりと笑った。
視線はそのまま、遠くの控え室に向けられている。
「退治屋じゃなく、よ」
「え?」
エドが聞き返すと、ロザリアはわざといたずらっぽく意味を濁した。
「少なくとも、彼はただの町の剣士じゃないわ。…ねぇ、こういうの、面白いと思わない? 誰も彼の過去を知らないまま、強さだけが先に舞台に上がる。貴族の若者たちが次々に驚いていく様子、見ものじゃない?」
「……まるで、用意された劇を観ているみたいですね」
「ふふ。あら、少し違うわ。これは“彼”が選んだ舞台よ」
ロザリアはまた視線を戻し、静かにグラスを置いた。
彼女の目には、ただの剣術大会ではなく、シドという青年の“過去”と“現在”が交差する瞬間が見えていた。た