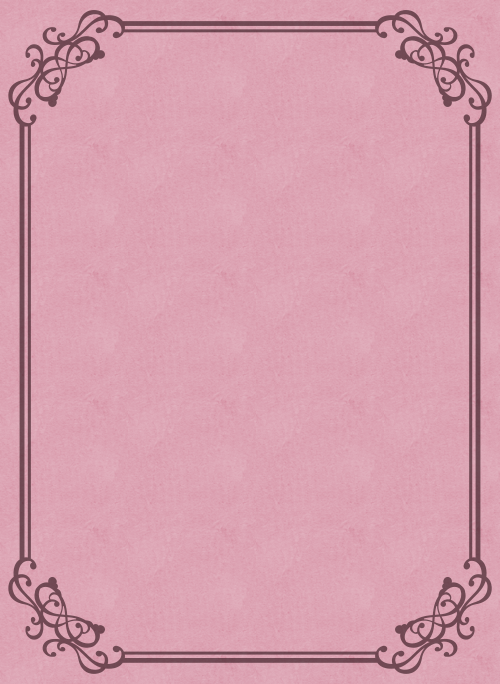その夜、リアンは王宮の用事を終えると、ふらりと城下町の一角にあるバーへ足を運んだ。
看板に灯る暖色の光が、夜の帳の中にほっとするような温もりを灯している。
扉を開けると、店の奥からいつもの柔らかな声が響いた。
「いらっしゃい。珍しいね、今日は一人?」
「うん、シドは仕事で来られないって。。」
カウンターの奥でグラスを拭いていたレオが、苦労を分かち合うような顔で微笑む。
リアンはいつもの席に腰を下ろし、ため息まじりに言った。
「そのため息は仕事疲れか?それとも他の悩みか?」
レオの言葉にリアンは少しハッとしたように視線を逸らした。
「…今日王宮でシドのことをかっこいいってメイド仲間達が騒いでいたの。」
「そうか。まぁ、シドは確かに美形だからなぁ。」
「それに1人はシドと話したことがあるって。王女様とも仲良いみたいだし、割と王宮内では社交的なのよ。。」
グラスに注がれた琥珀色の液体を見つめながら、リアンはぽつりと呟いた。
「……私が一番、昔から知ってるのに」
その声には、少しの寂しさと、やり場のない気持ちがにじんでいた。
「確かにシドは俺たち以外に深く関わる人はこの街には少ないよな。」
リアンは珍しくお酒を一気に飲み干した。
「…おいおい、大丈夫か。リアンも他国の王子の来訪で忙しいんだろ?」
「まぁ、ね。ねぇ、私そろそろシドに告白しようと思ってたのよ。でも、シドが王宮で働く事になって言うのを辞めたの。」
レオはグラスを拭きながら静かに頷きリアンの話を聞いた。
「…どうして伝えるのを辞めたんだ?」
遠くに行っちゃうような気がしてたから。……私の届かない場所に、向かってる気がして」
そう言ったリアンの声は、ほんの少し震えていた。
「でもね、本当は分かってた。あの人はずっと、どこか遠くを見てた。出会った頃から、そうだった」
レオは少しだけ視線を落とし、リアンの言葉を噛みしめるように黙った。
やがて、静かな声で返す。
「リアンが背中を押したんだよ、きっと」
「え?」
「誰かがちゃんと信じてくれてたから、彼は迷わず行けたんだ。……そして、リアンはずっと近くにいた。今でもね」
リアンは息を呑み、グラスを両手で包んだ。
「……近くに、いられてるのかな」
「それを決めるのは、たぶん――次、リアンがどうしたいかじゃない?」
優しい声だった。
リアンはそっと目を閉じて、胸の奥にあった何かが少しだけ、ほどけるような気がした。
看板に灯る暖色の光が、夜の帳の中にほっとするような温もりを灯している。
扉を開けると、店の奥からいつもの柔らかな声が響いた。
「いらっしゃい。珍しいね、今日は一人?」
「うん、シドは仕事で来られないって。。」
カウンターの奥でグラスを拭いていたレオが、苦労を分かち合うような顔で微笑む。
リアンはいつもの席に腰を下ろし、ため息まじりに言った。
「そのため息は仕事疲れか?それとも他の悩みか?」
レオの言葉にリアンは少しハッとしたように視線を逸らした。
「…今日王宮でシドのことをかっこいいってメイド仲間達が騒いでいたの。」
「そうか。まぁ、シドは確かに美形だからなぁ。」
「それに1人はシドと話したことがあるって。王女様とも仲良いみたいだし、割と王宮内では社交的なのよ。。」
グラスに注がれた琥珀色の液体を見つめながら、リアンはぽつりと呟いた。
「……私が一番、昔から知ってるのに」
その声には、少しの寂しさと、やり場のない気持ちがにじんでいた。
「確かにシドは俺たち以外に深く関わる人はこの街には少ないよな。」
リアンは珍しくお酒を一気に飲み干した。
「…おいおい、大丈夫か。リアンも他国の王子の来訪で忙しいんだろ?」
「まぁ、ね。ねぇ、私そろそろシドに告白しようと思ってたのよ。でも、シドが王宮で働く事になって言うのを辞めたの。」
レオはグラスを拭きながら静かに頷きリアンの話を聞いた。
「…どうして伝えるのを辞めたんだ?」
遠くに行っちゃうような気がしてたから。……私の届かない場所に、向かってる気がして」
そう言ったリアンの声は、ほんの少し震えていた。
「でもね、本当は分かってた。あの人はずっと、どこか遠くを見てた。出会った頃から、そうだった」
レオは少しだけ視線を落とし、リアンの言葉を噛みしめるように黙った。
やがて、静かな声で返す。
「リアンが背中を押したんだよ、きっと」
「え?」
「誰かがちゃんと信じてくれてたから、彼は迷わず行けたんだ。……そして、リアンはずっと近くにいた。今でもね」
リアンは息を呑み、グラスを両手で包んだ。
「……近くに、いられてるのかな」
「それを決めるのは、たぶん――次、リアンがどうしたいかじゃない?」
優しい声だった。
リアンはそっと目を閉じて、胸の奥にあった何かが少しだけ、ほどけるような気がした。