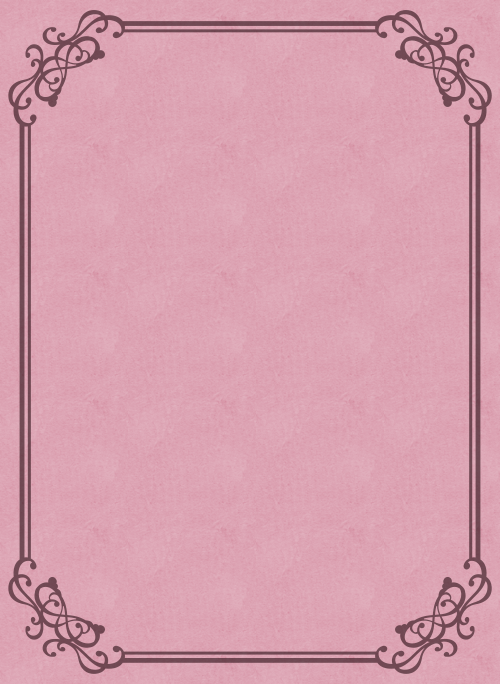アリスが席に着くと、エレオノーラは侍女に任せることなく、自らティーポットを手に取った。
湯を注ぐ仕草は静かで、無駄がなく、それでいてどこか温かい。
「どうぞ」
差し出されたカップを両手で受け取り、一口含む。
ふわりと広がる香りと、角のない味わいに、こわばっていた心がほんの少し緩んだ。
「……とても、美味しいです」
「それはよかったわ」
エレオノーラは小さく微笑むと、今度は菓子皿をアリスの方へ寄せた。
「お菓子もどうぞ。わたくしが作りましたの」
「え……?」
アリスは思わず目を見開いた。
「エレオノーラ様が、お作りに?」
「ええ。料理はいいものですよ。何も考えずに没頭できますから」
淡々とした口調だったが、その言葉には不思議と実感がこもっていた。
しばらく二人で紅茶を口に運んだ後、エレオノーラがふと視線を向ける。
「まだここへ来て数日ですが……少しは落ち着きましたか」
「え、ええ……何不自由なく。何もかもご用意いただいて、ありがとうございます」
そう答えながらも、アリスの胸はわずかにざわついていた。
エレオノーラはカップを静かに置き、窓の向こうを見るような、少し遠い目をする。
「本当に……急な婚姻話で、アリス様も大変なことでしたでしょう」
その言葉に、心臓が小さく跳ねた。
――この方も、きっと知っている。
セオに婚約者がいたことも、その関係が引き裂かれたことも。
強引に決めた祖国の判断を、エレオノーラがどう思っているのか。
その真意はまだ、アリスには測れなかった。
けれど。
この静かな気遣いの中に、敵意は感じられない。
それだけは、はっきりと分かった。
湯を注ぐ仕草は静かで、無駄がなく、それでいてどこか温かい。
「どうぞ」
差し出されたカップを両手で受け取り、一口含む。
ふわりと広がる香りと、角のない味わいに、こわばっていた心がほんの少し緩んだ。
「……とても、美味しいです」
「それはよかったわ」
エレオノーラは小さく微笑むと、今度は菓子皿をアリスの方へ寄せた。
「お菓子もどうぞ。わたくしが作りましたの」
「え……?」
アリスは思わず目を見開いた。
「エレオノーラ様が、お作りに?」
「ええ。料理はいいものですよ。何も考えずに没頭できますから」
淡々とした口調だったが、その言葉には不思議と実感がこもっていた。
しばらく二人で紅茶を口に運んだ後、エレオノーラがふと視線を向ける。
「まだここへ来て数日ですが……少しは落ち着きましたか」
「え、ええ……何不自由なく。何もかもご用意いただいて、ありがとうございます」
そう答えながらも、アリスの胸はわずかにざわついていた。
エレオノーラはカップを静かに置き、窓の向こうを見るような、少し遠い目をする。
「本当に……急な婚姻話で、アリス様も大変なことでしたでしょう」
その言葉に、心臓が小さく跳ねた。
――この方も、きっと知っている。
セオに婚約者がいたことも、その関係が引き裂かれたことも。
強引に決めた祖国の判断を、エレオノーラがどう思っているのか。
その真意はまだ、アリスには測れなかった。
けれど。
この静かな気遣いの中に、敵意は感じられない。
それだけは、はっきりと分かった。