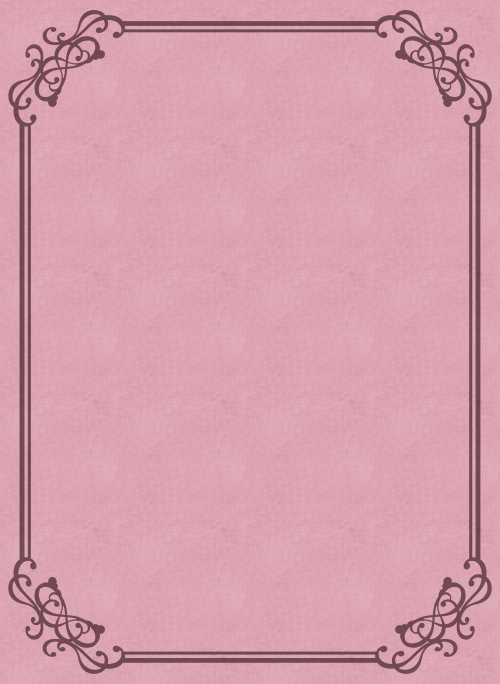ミロ王国――イスタリアの南に位置する、小さく静かな山岳の国。
豊かな資源も、強い軍事力も持たず、長年“大国の間に挟まれた平和”の上に成り立ってきた。
国土のほとんどが険しい地形で、畑も少なく、豊かとは言い難い。
ただひとつ誇れるものがあるとすれば、それは何百年も続く穏やかな王家の血筋と、慎ましくも誠実な国民性だった。
その王城の一室で、重苦しい空気が流れていた。
大理石のテーブルを挟んで、ミロ王国国王と側近が一枚の書状を前に俯いている。
イスタリアの国章が押された封蝋は、見ただけで胃が痛むほどの圧力を帯びていた。
「……イスタリア国王より、最終通達にございます。」
側近の低い声が静まり返った室内に落ちる。
「こ……これを拒めばどうなるのだと書かれている?」
側近は口を開きかけたが、言葉を選ぶように一度目を伏せた。
「……“両国の長き友好関係に亀裂が入り、今後の支援は一切望めない”と。
平たく言えば……絶縁、そして外交上の孤立、でございます。」
国王は深く眉を寄せ、手紙に目を落とした。
「なぜだ……なぜ大国イスタリアが、我が国などに。
アリス王女を、わざわざ……政略結婚の相手として望むなど……」
言葉には“理解できない”というより、
“信じたくない”という痛みが滲んでいた。
側近は重々しく首を振った。
「……おそらく、殿下が理由でしょう。」
国王の身体がわずかに震える。
殿下――その言葉は、この国では“第一王子セオ”を意味していた。
生まれつき身体が弱く、今では自力で歩くことも困難だ。
政治の場に出られる日も限られ、王族としての義務を果たすどころか、日々を静かに過ごすのが精一杯。
そんな息子を、誰より理解しているのは父である国王だった。
「……あの子が、政(まつりごと)で主導権を取れぬことを……イスタリアの王は知っていると?」
「はい。だからこそ――でしょう。」
セオが反発できないことを見越した結婚。
その裏を読んだ途端、国王は拳を強く握りしめた。
「……なんということを……!」
小国ミロが拒む道は、ほとんど残されていない。
この国は他国の庇護なしには存続が難しい。
ましてイスタリアはこの大陸最大の国。
機嫌を損ねれば、一瞬で孤立する。
「……セオは……なんと言っておる?」
側近は小さく息を呑んだように見えた。
「殿下は……“国が困るなら、僕は構いません”と。」
国王は顔を覆い、深く深く首を垂れた。
息子の優しさと覚悟が痛かった。
「……あの優しい子を……利用するというのか、イスタリアは……」
部屋に沈黙が降りる。
小国の悲鳴は、誰にも届かない──。
豊かな資源も、強い軍事力も持たず、長年“大国の間に挟まれた平和”の上に成り立ってきた。
国土のほとんどが険しい地形で、畑も少なく、豊かとは言い難い。
ただひとつ誇れるものがあるとすれば、それは何百年も続く穏やかな王家の血筋と、慎ましくも誠実な国民性だった。
その王城の一室で、重苦しい空気が流れていた。
大理石のテーブルを挟んで、ミロ王国国王と側近が一枚の書状を前に俯いている。
イスタリアの国章が押された封蝋は、見ただけで胃が痛むほどの圧力を帯びていた。
「……イスタリア国王より、最終通達にございます。」
側近の低い声が静まり返った室内に落ちる。
「こ……これを拒めばどうなるのだと書かれている?」
側近は口を開きかけたが、言葉を選ぶように一度目を伏せた。
「……“両国の長き友好関係に亀裂が入り、今後の支援は一切望めない”と。
平たく言えば……絶縁、そして外交上の孤立、でございます。」
国王は深く眉を寄せ、手紙に目を落とした。
「なぜだ……なぜ大国イスタリアが、我が国などに。
アリス王女を、わざわざ……政略結婚の相手として望むなど……」
言葉には“理解できない”というより、
“信じたくない”という痛みが滲んでいた。
側近は重々しく首を振った。
「……おそらく、殿下が理由でしょう。」
国王の身体がわずかに震える。
殿下――その言葉は、この国では“第一王子セオ”を意味していた。
生まれつき身体が弱く、今では自力で歩くことも困難だ。
政治の場に出られる日も限られ、王族としての義務を果たすどころか、日々を静かに過ごすのが精一杯。
そんな息子を、誰より理解しているのは父である国王だった。
「……あの子が、政(まつりごと)で主導権を取れぬことを……イスタリアの王は知っていると?」
「はい。だからこそ――でしょう。」
セオが反発できないことを見越した結婚。
その裏を読んだ途端、国王は拳を強く握りしめた。
「……なんということを……!」
小国ミロが拒む道は、ほとんど残されていない。
この国は他国の庇護なしには存続が難しい。
ましてイスタリアはこの大陸最大の国。
機嫌を損ねれば、一瞬で孤立する。
「……セオは……なんと言っておる?」
側近は小さく息を呑んだように見えた。
「殿下は……“国が困るなら、僕は構いません”と。」
国王は顔を覆い、深く深く首を垂れた。
息子の優しさと覚悟が痛かった。
「……あの優しい子を……利用するというのか、イスタリアは……」
部屋に沈黙が降りる。
小国の悲鳴は、誰にも届かない──。