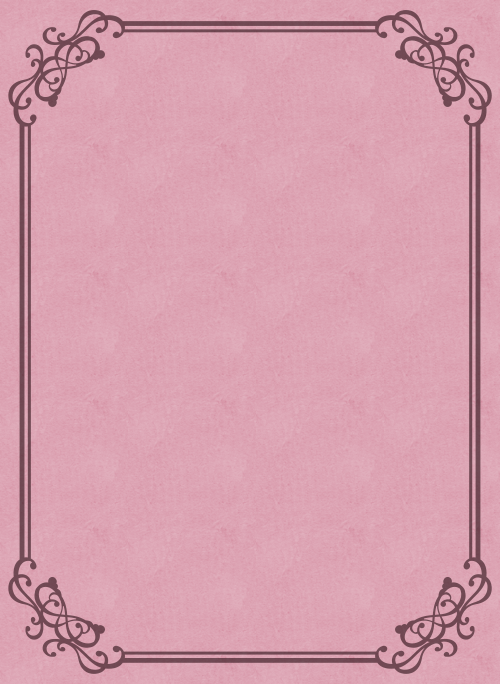「アスタリト王国……」
シドの声が、かすかに震えた。
その名を口にすることは、もう何年もなかった。
ダリウスはゆっくりと続けた。
「王都の広場でね、偶然、建国祭の行列を見かけたんだ。
白い制服を纏った若い王子がいて……その剣捌きに、見惚れた」
シドは沈黙したまま、視線を落とした。
胸の奥に小さな痛みが広がる。
遠い過去を抉るような痛み。
「その時の王子の顔を、君を見た瞬間に思い出した。
姿勢も、構えも、剣の握り方も……あまりにも似ていたから」
ダリウスはそこで言葉を区切り、穏やかに笑った。
た。
「驚かなくていい。私は誰にも言うつもりはない。
けれど……君がどう生きるか、迷うときがあるなら、私は味方でいたいと思っている」
風が吹き抜け、訓練場の砂を巻き上げた。
その音の中で、シドはゆっくりと頭を下げた。
「ありがとうございます、ダリウス殿。……その言葉、忘れません」
ダリウスは軽く頷き、微笑を残して去っていった。
シドはその背を見送りながら、胸の奥に静かに疼く何かを感じていた。
シドの声が、かすかに震えた。
その名を口にすることは、もう何年もなかった。
ダリウスはゆっくりと続けた。
「王都の広場でね、偶然、建国祭の行列を見かけたんだ。
白い制服を纏った若い王子がいて……その剣捌きに、見惚れた」
シドは沈黙したまま、視線を落とした。
胸の奥に小さな痛みが広がる。
遠い過去を抉るような痛み。
「その時の王子の顔を、君を見た瞬間に思い出した。
姿勢も、構えも、剣の握り方も……あまりにも似ていたから」
ダリウスはそこで言葉を区切り、穏やかに笑った。
た。
「驚かなくていい。私は誰にも言うつもりはない。
けれど……君がどう生きるか、迷うときがあるなら、私は味方でいたいと思っている」
風が吹き抜け、訓練場の砂を巻き上げた。
その音の中で、シドはゆっくりと頭を下げた。
「ありがとうございます、ダリウス殿。……その言葉、忘れません」
ダリウスは軽く頷き、微笑を残して去っていった。
シドはその背を見送りながら、胸の奥に静かに疼く何かを感じていた。