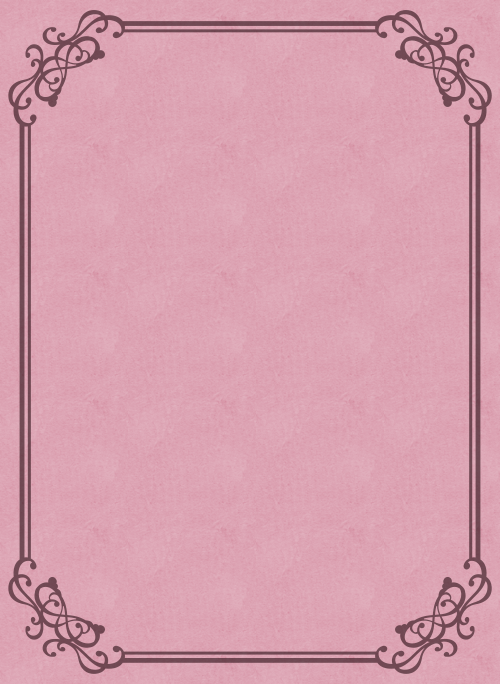翌朝、王宮の中庭はいつになく賑わっていた。
旅装を解いたばかりのダリウスが姿を見せると、侍女たちの間に小さなざわめきが走った。
「まあ、ダリウス様が……!」
「以前よりずっと精悍になられて……」
花を抱えた侍女が頬を染め、衛兵たちでさえ敬意を込めて背筋を伸ばす。
ダリウスはそんな視線の渦の中でも気負うことなく、穏やかに笑ってみせた。
誰にでも分け隔てなく声をかけ、庭師の老人には旅先の草花の話を、書庫の司書には新しい書の話をする。
王家の一員としての立場を自ら手放したはずなのに、その振る舞いには不思議な気品が宿っていた。
アリスは少し離れた回廊からその光景を見つめていた。
人々が自然と彼の周りに集まる。
まるで春の陽だまりに引き寄せられるように。
「……やはり、人気者でいらっしゃいますね」
隣で控えていたリアンが、そっと微笑んだ。
「殿下でいらした頃もそうでしたが、立場を離れられても人を惹きつけるお方です。まるで——生まれながらの王のようでございます」
アリスは小さく笑みを漏らした。
「そうかもしれないわ。ダリウスは、王族をやめても王族らしいの」
そう言いながらも、胸の奥に少しだけ複雑な感情が灯る。
ダリウスは誰にでも優しい。
それが誇らしくもあり、ほんの少し寂しくもあった。
ふと、視線の先でダリウスがこちらに気づく。
彼は群衆の中から軽く手を上げ、穏やかな笑みを浮かべた。
その笑顔に、周囲の空気が一層柔らかくなる。
「……やっぱり、ダリウスは変わらないわ」
アリスは胸の前で指を組み、ひとりごとのように呟いた。
あの人の存在は、王宮に春を運んでくる。
けれど、その光が強ければ強いほど、自分の立っている場所の影が濃くなる気がした。
旅装を解いたばかりのダリウスが姿を見せると、侍女たちの間に小さなざわめきが走った。
「まあ、ダリウス様が……!」
「以前よりずっと精悍になられて……」
花を抱えた侍女が頬を染め、衛兵たちでさえ敬意を込めて背筋を伸ばす。
ダリウスはそんな視線の渦の中でも気負うことなく、穏やかに笑ってみせた。
誰にでも分け隔てなく声をかけ、庭師の老人には旅先の草花の話を、書庫の司書には新しい書の話をする。
王家の一員としての立場を自ら手放したはずなのに、その振る舞いには不思議な気品が宿っていた。
アリスは少し離れた回廊からその光景を見つめていた。
人々が自然と彼の周りに集まる。
まるで春の陽だまりに引き寄せられるように。
「……やはり、人気者でいらっしゃいますね」
隣で控えていたリアンが、そっと微笑んだ。
「殿下でいらした頃もそうでしたが、立場を離れられても人を惹きつけるお方です。まるで——生まれながらの王のようでございます」
アリスは小さく笑みを漏らした。
「そうかもしれないわ。ダリウスは、王族をやめても王族らしいの」
そう言いながらも、胸の奥に少しだけ複雑な感情が灯る。
ダリウスは誰にでも優しい。
それが誇らしくもあり、ほんの少し寂しくもあった。
ふと、視線の先でダリウスがこちらに気づく。
彼は群衆の中から軽く手を上げ、穏やかな笑みを浮かべた。
その笑顔に、周囲の空気が一層柔らかくなる。
「……やっぱり、ダリウスは変わらないわ」
アリスは胸の前で指を組み、ひとりごとのように呟いた。
あの人の存在は、王宮に春を運んでくる。
けれど、その光が強ければ強いほど、自分の立っている場所の影が濃くなる気がした。