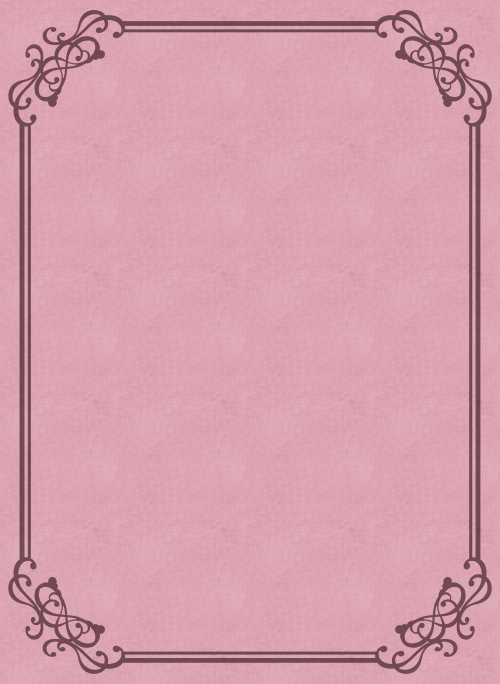廊下に駆ける侍女の声が耳に入った瞬間、アリスは手にしていた書をそっと閉じた。
「——殿下が、帰国なさいました!」
アリスの胸の奥で、久しぶりに小さな高鳴りが跳ねる。
王族としての形式に縛られる日々の中で、自由奔放な従兄弟ダリウスだけが、心をさらけ出せる存在だった。
「……ダリウスが、また突然……」
胸の奥で、何かがふっとほどけるような感覚が広がった。
王族として過ごす日々の中で、心から笑える相手は彼くらいしかいない。
幼いころから、アリスにとってダリウスは“風”のような存在だった。
どこからともなく現れては笑い、好き勝手に言ってはまた旅立ってしまう。
けれどその自由さが、どこか羨ましくもあった。
「陛下へのご挨拶を済ませたあと、すぐにお部屋へお越しになるそうです」
侍女の報告に、アリスは思わず微笑む。
「きっと、またお土産話が山ほどあるのでしょうね」
窓の外では、春の風が庭の白薔薇を揺らしていた。
アリスの胸の内にも、同じような軽やかな風が吹き込む。
久しぶりに、退屈な王宮に色が戻る予感がした。
「——殿下が、帰国なさいました!」
アリスの胸の奥で、久しぶりに小さな高鳴りが跳ねる。
王族としての形式に縛られる日々の中で、自由奔放な従兄弟ダリウスだけが、心をさらけ出せる存在だった。
「……ダリウスが、また突然……」
胸の奥で、何かがふっとほどけるような感覚が広がった。
王族として過ごす日々の中で、心から笑える相手は彼くらいしかいない。
幼いころから、アリスにとってダリウスは“風”のような存在だった。
どこからともなく現れては笑い、好き勝手に言ってはまた旅立ってしまう。
けれどその自由さが、どこか羨ましくもあった。
「陛下へのご挨拶を済ませたあと、すぐにお部屋へお越しになるそうです」
侍女の報告に、アリスは思わず微笑む。
「きっと、またお土産話が山ほどあるのでしょうね」
窓の外では、春の風が庭の白薔薇を揺らしていた。
アリスの胸の内にも、同じような軽やかな風が吹き込む。
久しぶりに、退屈な王宮に色が戻る予感がした。