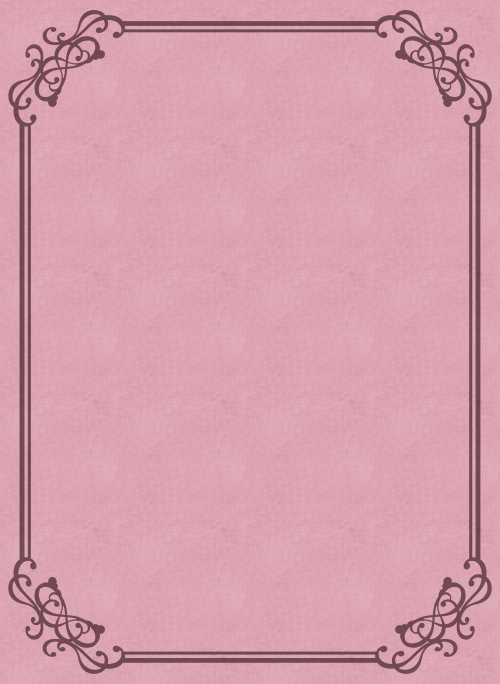シドは離宮で、王宮の喧騒から切り離された暮らしを送っていた。
人目を避け、静かな廊下と庭を行き来するだけの毎日。だがその静寂の中で、彼はひたすら自分の魔法を試していた。
「自分は、何ができるのか」
その答えを求めるように、書物を読み漁り、魔法陣を描き、失敗を重ね、独学で力を磨いた。
やがて、自分の力の輪郭がはっきりと見えてくる。
炎も氷も、癒しも防御も、どれも確かな手応えがあった。だが同時に、この力はアスタリトの王宮には居場所がないと悟った。
――思う存分、魔法を使える場所へ行きたい。
――そして、この力で人の役に立ちたい。
その願いは、日に日に強くなっていった。
やがてシドは、迷いを断ち切るように心の中で決意する。
すべてを置いてでも、自分を必要とする場所へ行くのだ。
そして、彼はアスタリトを去った。
ーー
静かに話を聞いていたロザリアは、シドの言葉が途切れるのを待ち、ゆっくりと頷いた。
「この国で、そしてここ――王宮で、思う存分力を使いなさい。あなたは今、私の弟子。」
それだけ告げると、ロザリアは背を向け、足音も静かに部屋を後にした。
シドは届いた手紙をやっかいに思う一方で、久しぶりに故郷のことを口にできたせいか、不思議と胸の奥が軽くなっているのを感じていた。
***
その夜、アリスはまた眠れずにいた。
頭に浮かぶのは、兄と義姉の会話、そしてシドの横顔。
――いつか必ず、あの人の口から真実を聞こう。
胸の奥で静かにそう誓う。
窓辺に目をやると、雪がしんしんと降り続けていた。
その静けさは美しくも、どこか不穏で――まるで、何かが迫っていることを告げているようだった。
アリスは毛布を胸元まで引き寄せた。
心の奥底に芽生えたざわめきは、雪とともに静かに積もっていく。
人目を避け、静かな廊下と庭を行き来するだけの毎日。だがその静寂の中で、彼はひたすら自分の魔法を試していた。
「自分は、何ができるのか」
その答えを求めるように、書物を読み漁り、魔法陣を描き、失敗を重ね、独学で力を磨いた。
やがて、自分の力の輪郭がはっきりと見えてくる。
炎も氷も、癒しも防御も、どれも確かな手応えがあった。だが同時に、この力はアスタリトの王宮には居場所がないと悟った。
――思う存分、魔法を使える場所へ行きたい。
――そして、この力で人の役に立ちたい。
その願いは、日に日に強くなっていった。
やがてシドは、迷いを断ち切るように心の中で決意する。
すべてを置いてでも、自分を必要とする場所へ行くのだ。
そして、彼はアスタリトを去った。
ーー
静かに話を聞いていたロザリアは、シドの言葉が途切れるのを待ち、ゆっくりと頷いた。
「この国で、そしてここ――王宮で、思う存分力を使いなさい。あなたは今、私の弟子。」
それだけ告げると、ロザリアは背を向け、足音も静かに部屋を後にした。
シドは届いた手紙をやっかいに思う一方で、久しぶりに故郷のことを口にできたせいか、不思議と胸の奥が軽くなっているのを感じていた。
***
その夜、アリスはまた眠れずにいた。
頭に浮かぶのは、兄と義姉の会話、そしてシドの横顔。
――いつか必ず、あの人の口から真実を聞こう。
胸の奥で静かにそう誓う。
窓辺に目をやると、雪がしんしんと降り続けていた。
その静けさは美しくも、どこか不穏で――まるで、何かが迫っていることを告げているようだった。
アリスは毛布を胸元まで引き寄せた。
心の奥底に芽生えたざわめきは、雪とともに静かに積もっていく。