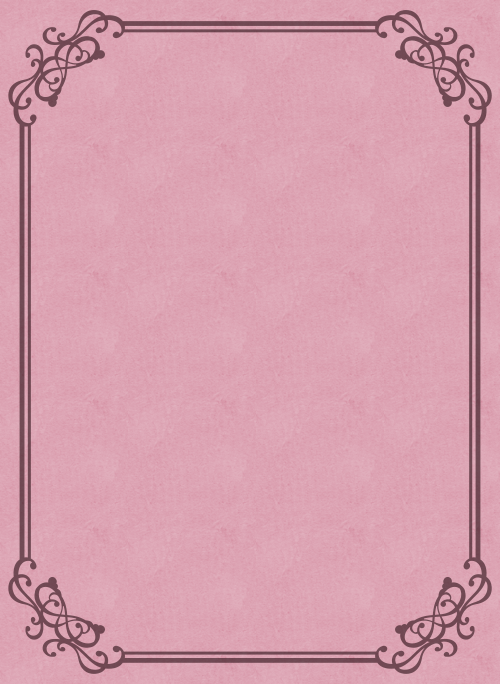使者が去り、部屋に静けさが戻った。
重苦しい空気の中、シドは深く息を吐き、窓の外に視線をやった。
背後で扉が閉まる音がして、残ったのはロザリアだけだった。
「……知っていたんですね」
振り返らずに、シドは低く問う。
「ええ」
ロザリアは少し間を置き、落ち着いた声で答えた。
「ずっと前のことよ。アスタリトへ行った時、舞踏会であなたを見かけたの」
「……」
「端のほうで、何か魔法を使っていたわね。アスタリトに魔法使いがいること自体珍しい。それも舞踏会の場に出られる立場となれば、王族か、それに並ぶ者しかいない」
ロザリアは少しだけ視線を伏せた。
「そのときは、ただ珍しいと思っただけだった。でも――今日の使者を見て、ようやく確信したわ」
シドは苦笑に似た息を漏らした。
「……そうか」
しばし沈黙が落ちる。
やがてシドは、振り返らぬまま問いかけた。
「じゃあ、なぜ黙っていたんですか。」
「必要のないことは、口にしない主義なの」
ロザリアは軽く肩をすくめるような口調だった。
「私にとって、あなたがアスタリトの王族かどうかなんて、仕事をするうえでは些細なことだったもの」
「……些細、ね」
シドはわずかに片眉を上げる。
「ただ――」ロザリアは言葉を継ぎ、まっすぐ彼を見た。
「あなたがそういう立場にあるのなら、無理をして守らなければならないものも、人一倍多いはずだと、そう思ってはいたわ」
シドは視線を床に落とし、短く息をつく。
「守るべきもの、か……」
その言葉が、遠い記憶と、今日の使者の言葉を重ね合わせた。
重苦しい空気の中、シドは深く息を吐き、窓の外に視線をやった。
背後で扉が閉まる音がして、残ったのはロザリアだけだった。
「……知っていたんですね」
振り返らずに、シドは低く問う。
「ええ」
ロザリアは少し間を置き、落ち着いた声で答えた。
「ずっと前のことよ。アスタリトへ行った時、舞踏会であなたを見かけたの」
「……」
「端のほうで、何か魔法を使っていたわね。アスタリトに魔法使いがいること自体珍しい。それも舞踏会の場に出られる立場となれば、王族か、それに並ぶ者しかいない」
ロザリアは少しだけ視線を伏せた。
「そのときは、ただ珍しいと思っただけだった。でも――今日の使者を見て、ようやく確信したわ」
シドは苦笑に似た息を漏らした。
「……そうか」
しばし沈黙が落ちる。
やがてシドは、振り返らぬまま問いかけた。
「じゃあ、なぜ黙っていたんですか。」
「必要のないことは、口にしない主義なの」
ロザリアは軽く肩をすくめるような口調だった。
「私にとって、あなたがアスタリトの王族かどうかなんて、仕事をするうえでは些細なことだったもの」
「……些細、ね」
シドはわずかに片眉を上げる。
「ただ――」ロザリアは言葉を継ぎ、まっすぐ彼を見た。
「あなたがそういう立場にあるのなら、無理をして守らなければならないものも、人一倍多いはずだと、そう思ってはいたわ」
シドは視線を床に落とし、短く息をつく。
「守るべきもの、か……」
その言葉が、遠い記憶と、今日の使者の言葉を重ね合わせた。