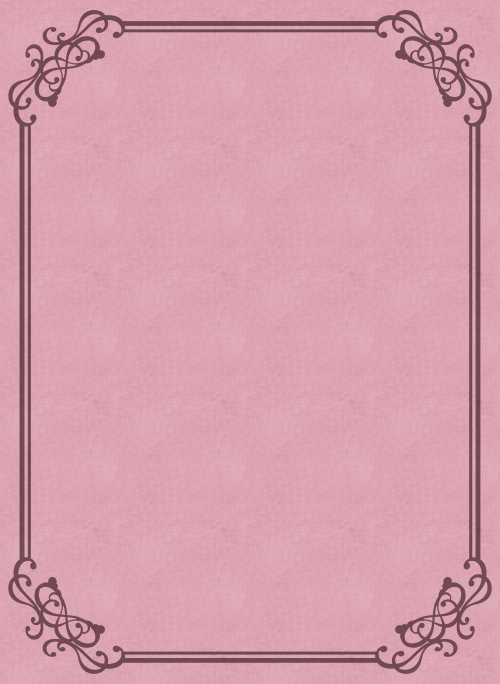冬の夜は、ことのほか静かだった。
王宮の石造りの回廊には灯がともり、燭台の火が壁にゆらゆらと揺れている。
アリスは一人、毛皮のショールを羽織り、自室を抜け出していた。
眠れなかった。
このところ、心がざわついて仕方がない。建国記念の舞踏会以来、シドの言葉も態度も、どこか何かを押し隠しているように感じられてならなかった。
彼のことを知りたい――そう思っているはずなのに、肝心なことは何ひとつ知らない。
冷えた指先を胸元で握りしめたとき、ふと前方から声が聞こえてきた。
回廊の突き当たり、半開きの扉の奥から、誰かの話し声が漏れている。
アリスは反射的に立ち止まった。
声の主は、兄のルイ。そして、もう一人はその妃――義理の姉であるソフィアだった。
立ち聞きなどするつもりはなかった。
でも、すぐに立ち去れなかったのは――
聞こえてきた“その名”のせいだった。
「……アスタリトの国王ジルからの手紙、届いてたわよね」
「――ああ。ジル国王の弟、シドの近況についても少し書いてあった」
シド?
今、確かに兄はそう言った。アスタリトの国王の“弟”――?
「あなた、本当に気にしているのね。アスタリトを離れた王子のことを」
「……気にしていないわけがない。王族の立場を捨てるなんて、前代未聞だ」
アリスの心臓が跳ねた。
――シドが……王子? 王族の立場を、捨てた?
静かに扉から離れると、アリスは小さく息をついた。
知らなかった。
彼が背負ってきたものの重さに、初めて気づいた気がした。
――でも、どうしてだろう。
シドが王子だということに、驚くよりも納得している自分がいる。
まだ彼のすべてを知れていない。
その確信だけが、胸の奥で静かに息づいていた。
王宮の石造りの回廊には灯がともり、燭台の火が壁にゆらゆらと揺れている。
アリスは一人、毛皮のショールを羽織り、自室を抜け出していた。
眠れなかった。
このところ、心がざわついて仕方がない。建国記念の舞踏会以来、シドの言葉も態度も、どこか何かを押し隠しているように感じられてならなかった。
彼のことを知りたい――そう思っているはずなのに、肝心なことは何ひとつ知らない。
冷えた指先を胸元で握りしめたとき、ふと前方から声が聞こえてきた。
回廊の突き当たり、半開きの扉の奥から、誰かの話し声が漏れている。
アリスは反射的に立ち止まった。
声の主は、兄のルイ。そして、もう一人はその妃――義理の姉であるソフィアだった。
立ち聞きなどするつもりはなかった。
でも、すぐに立ち去れなかったのは――
聞こえてきた“その名”のせいだった。
「……アスタリトの国王ジルからの手紙、届いてたわよね」
「――ああ。ジル国王の弟、シドの近況についても少し書いてあった」
シド?
今、確かに兄はそう言った。アスタリトの国王の“弟”――?
「あなた、本当に気にしているのね。アスタリトを離れた王子のことを」
「……気にしていないわけがない。王族の立場を捨てるなんて、前代未聞だ」
アリスの心臓が跳ねた。
――シドが……王子? 王族の立場を、捨てた?
静かに扉から離れると、アリスは小さく息をついた。
知らなかった。
彼が背負ってきたものの重さに、初めて気づいた気がした。
――でも、どうしてだろう。
シドが王子だということに、驚くよりも納得している自分がいる。
まだ彼のすべてを知れていない。
その確信だけが、胸の奥で静かに息づいていた。