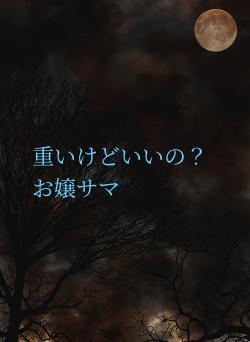──暗闇の部屋の中で、そればかりを考えていたら、時計の針がカチッと大きく響いた。
うっすらと見える時計は、夜中の1時になっていて、寝なきゃいけない焦りも生まれだす。
だけどそれよりも、スマホくんたちがわたしの思考をうめつくしていた。
ゆっくりと起き上がり、寝転がる3人に目をやってみる。明華くんと莉雨くんは丸くなり寝息をたてていたけれど、
「眠れない?」
机の引き出しのところに寄りかかる碧くんは、目を開けていた。
「つい、どうしたらいいのか考えちゃって」
2人を起こさないように碧くんの方へ体を向けて小声で答えれば、碧くんは静かに立ち上がり、わたしを見下ろす。
「碧くん?」
じっと見上げれば、そっと碧くんが顔を寄せてきて……
「っ……」
つい体を引くも、コツン、と碧くんの額がわたしの額にあたった。
「あ、碧く──」
「……もし、戻れなくてもぼくはこのままそばにいたい。ただ青空のスマホだからって理由じゃなくて……青空のことが好きだから、そばにいたい」
碧くんはゆっくりと離れると、暗い部屋の中でも表情がわかるくらいの視界の中でも、薄く微笑んだのが見えた。
その表情にドキリと鼓動がはねると同時に、碧くんはわたしの頬に手をそえる。
「スマホの姿なら、こうして自分から触れることは出来ないけどこの姿なら……いつでも君に触れられる。真っ直ぐ、青空の笑顔が見れる」