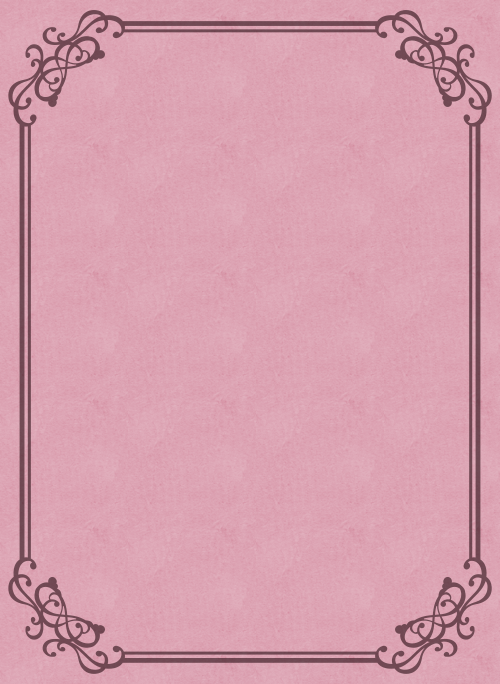そのホテルラウンジは、どこか現実離れしていた。
高い天井、絨毯を踏む音すら吸い込むような静けさ。
天窓から差し込む自然光が、テーブルの上を柔らかく照らしていた。
母に着せられたワンピース。
無理やり整えられた髪。
少しヒールの高いパンプス。
すべてが、“普段の私”じゃない気がして、息苦しかった。
時計を見れば、約束の時刻まであと1分。
既にテーブルには水が運ばれ、店員が丁寧に姿勢を正している。
(これから来る人が、私の“結婚相手”になるかもしれないのか)
そう思った瞬間、背筋に冷たいものが走った。
そして、現れた。
目に入ったのは――
見慣れた、長身と凛とした佇まい。
スーツではないけれど、端正な立ち姿。
視線が合った瞬間、呼吸が止まりそうになる。
「……っ、専務……?」
声にならない声が喉奥で震えた。
彼は、私の驚きを察してか、どこか静かに目を伏せ、深く一礼した。
「……今日は、よろしくお願いします」
それは、あまりにも丁寧で、
あまりにも“他人行儀”だった。
頭が真っ白になった。
なんで――なんで“この人”が、ここにいるの?
今日のお見合いの相手。
紹介されたのは、“名家の御曹司”としか聞いていなかった。
まさか……一ノ瀬ホールディングスの、あの専務。
私が仕えてきた人。
想いを抑えて、距離を保ち続けてきた――あの人が。
(冗談、じゃない……よね?)
「……どうか、少しのあいだだけ、“初対面”として、お付き合いください」
彼が低い声でそう囁いたとき、胸の奥が大きく波打った。
“初対面”として?
彼は、私が動揺しているのを悟ったうえで――
その場を壊さないように配慮してくれている。
そして私は、彼の言葉を拒むことができなかった。
(……ううん、拒みたくなかった)
向かい合って座る彼。
オフィスでは見たことのない、柔らかな表情。
「今日は、お忙しいところありがとうございます」
「いえ……こちらこそ」
言葉を交わすたびに、心の中がざわついていく。
視線が合うたびに、呼吸が速くなる。
こんなはずじゃなかった。
「誰でもいい」と思って来た。
“専務”じゃなければ、もう誰が来ても同じだと。
なのに、目の前にいるのは――
誰よりも、望んでしまった人。
心の奥に押し込んでいた名前。
諦めることで整理したはずの想い。
全部、目の前で揺らいでいく。
(どうしよう……)
(どうして、あなたが――)
そのあとは、当たり障りのない会話が続いた。
趣味、仕事のこと、休日の過ごし方。
けれどそのどれもが、“他人としての会話”に聞こえなかった。
まるで、お互いのことを、
もうすでにたくさん知っているのに――
“知らないふり”をして話しているみたいだった。
言うべきか、言わないべきか。
お見合いの場で彼と向かい合いながら、私はずっと、その一言を喉の奥で握りしめていた。
“初対面”という建前のもとで交わされた会話。
休日の過ごし方や、好きな食べ物、映画の話――どれも穏やかで、心地よくて。
だけど、どうしても消せない疑問が、胸の奥でずっと燻っていた。
(この人には、子どもがいる)
私がそう思っているのは、あの日の光景からだった。
大学の近くのテニスコート。
フェンスの向こうにいたあの女の子。
彼と手を繋いで、「パパ」と呼んでいた――あの瞬間。
その記憶が、ずっと私の心を縛っていた。
好きになってはいけない。
家庭がある人なんだから。
奥さんがいて、子どもがいる。
だから私の気持ちなんて、届いてはいけない――そうやって、自分を律してきた。
でも、今。
その“想ってはいけない人”が、私の目の前に座っている。
ほんの少しでいい。
この胸に巣食う霧を、晴らしたかった。
だから私は、震える唇をどうにか動かして――彼に問いかけた。
「……子ども、いるんですよね?」
声が出た瞬間、心臓が跳ね上がった。
彼の表情が、すっと静かになる。
取り繕うでもなく、驚くでもなく。
ただ、深い呼吸をひとつ置いて、まっすぐに目を見て言った。
「……あの子は、僕の姉の娘です」
言葉が、ゆっくりと胸に染み込んでくる。
「数年前に、姉夫婦が事故で亡くなって。あの子を引き取って、今は父と一緒に育てています」
「僕は――独身です。結婚したことも、子どもがいたことも、一度もありません」
まるで、世界の色が変わった気がした。
空気が、やっと肺に入ったような感覚。
肩に乗っていた重たい何かが、そっと降りた。
「あ……」
一瞬、返す言葉が出てこなくて。
でも気づけば、頬に何か温かいものが伝っていた。
涙だった。
恥ずかしい、と思った。
でも、それ以上に――心が、救われていた。
ずっと、どこかで願っていた。
「もし、違ったら」
「もし、彼に家庭がなかったら」
そんな都合のいい希望を、心の奥に閉じ込めていた。
でも、願いなんて叶わないと思っていた。
だからこそ、
“本当は違った”と知ったとき――
もうどうしようもなくて、涙が出た。
「……ごめんなさい。ずっと、誤解してました」
そう言うと、彼はふっと微笑んだ。
「無理もないよ。心春が僕を“パパ”って呼んだあの場面だけ見れば、そう思われても仕方ない」
(心春……)
あの女の子の名前。
その響きを口にする彼が、とても優しくて。
ますます胸が詰まった。
彼は、ずっと家族のことも、プライベートも、一切社内では見せなかった。
それは、誰にも見せない覚悟のようにも見えていた。
(ずっと、一人で抱えてたんだ)
そう思った瞬間――
少しだけ、彼に近づけたような気がした。
帰り道、ホテルのロビーを出ると、夕陽が落ちかけていた。
ビルのガラスに映る空は、オレンジ色に染まっていて、
その中に、さっきまでの涙が静かに溶けていった。
あの人には家庭がない。
あの子は姪で、彼はずっとひとりだった。
その事実だけで、こんなにも胸が軽くなるなんて。
高い天井、絨毯を踏む音すら吸い込むような静けさ。
天窓から差し込む自然光が、テーブルの上を柔らかく照らしていた。
母に着せられたワンピース。
無理やり整えられた髪。
少しヒールの高いパンプス。
すべてが、“普段の私”じゃない気がして、息苦しかった。
時計を見れば、約束の時刻まであと1分。
既にテーブルには水が運ばれ、店員が丁寧に姿勢を正している。
(これから来る人が、私の“結婚相手”になるかもしれないのか)
そう思った瞬間、背筋に冷たいものが走った。
そして、現れた。
目に入ったのは――
見慣れた、長身と凛とした佇まい。
スーツではないけれど、端正な立ち姿。
視線が合った瞬間、呼吸が止まりそうになる。
「……っ、専務……?」
声にならない声が喉奥で震えた。
彼は、私の驚きを察してか、どこか静かに目を伏せ、深く一礼した。
「……今日は、よろしくお願いします」
それは、あまりにも丁寧で、
あまりにも“他人行儀”だった。
頭が真っ白になった。
なんで――なんで“この人”が、ここにいるの?
今日のお見合いの相手。
紹介されたのは、“名家の御曹司”としか聞いていなかった。
まさか……一ノ瀬ホールディングスの、あの専務。
私が仕えてきた人。
想いを抑えて、距離を保ち続けてきた――あの人が。
(冗談、じゃない……よね?)
「……どうか、少しのあいだだけ、“初対面”として、お付き合いください」
彼が低い声でそう囁いたとき、胸の奥が大きく波打った。
“初対面”として?
彼は、私が動揺しているのを悟ったうえで――
その場を壊さないように配慮してくれている。
そして私は、彼の言葉を拒むことができなかった。
(……ううん、拒みたくなかった)
向かい合って座る彼。
オフィスでは見たことのない、柔らかな表情。
「今日は、お忙しいところありがとうございます」
「いえ……こちらこそ」
言葉を交わすたびに、心の中がざわついていく。
視線が合うたびに、呼吸が速くなる。
こんなはずじゃなかった。
「誰でもいい」と思って来た。
“専務”じゃなければ、もう誰が来ても同じだと。
なのに、目の前にいるのは――
誰よりも、望んでしまった人。
心の奥に押し込んでいた名前。
諦めることで整理したはずの想い。
全部、目の前で揺らいでいく。
(どうしよう……)
(どうして、あなたが――)
そのあとは、当たり障りのない会話が続いた。
趣味、仕事のこと、休日の過ごし方。
けれどそのどれもが、“他人としての会話”に聞こえなかった。
まるで、お互いのことを、
もうすでにたくさん知っているのに――
“知らないふり”をして話しているみたいだった。
言うべきか、言わないべきか。
お見合いの場で彼と向かい合いながら、私はずっと、その一言を喉の奥で握りしめていた。
“初対面”という建前のもとで交わされた会話。
休日の過ごし方や、好きな食べ物、映画の話――どれも穏やかで、心地よくて。
だけど、どうしても消せない疑問が、胸の奥でずっと燻っていた。
(この人には、子どもがいる)
私がそう思っているのは、あの日の光景からだった。
大学の近くのテニスコート。
フェンスの向こうにいたあの女の子。
彼と手を繋いで、「パパ」と呼んでいた――あの瞬間。
その記憶が、ずっと私の心を縛っていた。
好きになってはいけない。
家庭がある人なんだから。
奥さんがいて、子どもがいる。
だから私の気持ちなんて、届いてはいけない――そうやって、自分を律してきた。
でも、今。
その“想ってはいけない人”が、私の目の前に座っている。
ほんの少しでいい。
この胸に巣食う霧を、晴らしたかった。
だから私は、震える唇をどうにか動かして――彼に問いかけた。
「……子ども、いるんですよね?」
声が出た瞬間、心臓が跳ね上がった。
彼の表情が、すっと静かになる。
取り繕うでもなく、驚くでもなく。
ただ、深い呼吸をひとつ置いて、まっすぐに目を見て言った。
「……あの子は、僕の姉の娘です」
言葉が、ゆっくりと胸に染み込んでくる。
「数年前に、姉夫婦が事故で亡くなって。あの子を引き取って、今は父と一緒に育てています」
「僕は――独身です。結婚したことも、子どもがいたことも、一度もありません」
まるで、世界の色が変わった気がした。
空気が、やっと肺に入ったような感覚。
肩に乗っていた重たい何かが、そっと降りた。
「あ……」
一瞬、返す言葉が出てこなくて。
でも気づけば、頬に何か温かいものが伝っていた。
涙だった。
恥ずかしい、と思った。
でも、それ以上に――心が、救われていた。
ずっと、どこかで願っていた。
「もし、違ったら」
「もし、彼に家庭がなかったら」
そんな都合のいい希望を、心の奥に閉じ込めていた。
でも、願いなんて叶わないと思っていた。
だからこそ、
“本当は違った”と知ったとき――
もうどうしようもなくて、涙が出た。
「……ごめんなさい。ずっと、誤解してました」
そう言うと、彼はふっと微笑んだ。
「無理もないよ。心春が僕を“パパ”って呼んだあの場面だけ見れば、そう思われても仕方ない」
(心春……)
あの女の子の名前。
その響きを口にする彼が、とても優しくて。
ますます胸が詰まった。
彼は、ずっと家族のことも、プライベートも、一切社内では見せなかった。
それは、誰にも見せない覚悟のようにも見えていた。
(ずっと、一人で抱えてたんだ)
そう思った瞬間――
少しだけ、彼に近づけたような気がした。
帰り道、ホテルのロビーを出ると、夕陽が落ちかけていた。
ビルのガラスに映る空は、オレンジ色に染まっていて、
その中に、さっきまでの涙が静かに溶けていった。
あの人には家庭がない。
あの子は姪で、彼はずっとひとりだった。
その事実だけで、こんなにも胸が軽くなるなんて。