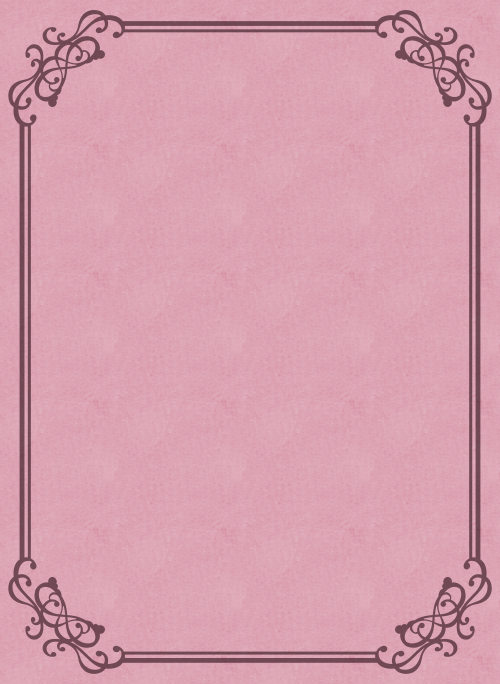父の声は、やけに淡々としていた。
「彼女は――○○グループのご令嬢だよ」
応接テーブルに置かれた一枚の資料に、目を通しながら父は続けた。
「〇〇ホールディングス。関東圏じゃなかなかの老舗企業だ。会長は彼女の祖父、現社長が父親で、母親も元華族筋の家系。見合い写真に選ばれるのも当然といえば当然だろう」
その言葉に、俺は思わず視線を落とした。
澪が……ご令嬢?
あの、地味で控えめで、どこかオフィスの片隅で気配を消していた彼女が――?
「しかも、彼女は一貫して付属の女子校に通っていた。大学卒業まで、ずっとだ」
「……箱入り、ってことか?」
「そういう言い方もできるな。本人はいたって真面目で、恋愛経験も……どうやら、ないらしい」
父は笑いを含んだように言った。
「本人もご両親も、“今までそういう交際をしたことがない”と言っていたよ。つまり――」
「……最初から、独りだったんだな」
その言葉が口からこぼれたとき、胸の奥がじわりと熱を帯びた。
あの“婚約者”という噂。
自ら口にしたという話。
社内で勝手に広がっていた推測の数々。
あれは――彼女が、わざと流した“嘘”だったのか。
なぜ?
自分を守るため?
あるいは、仕事をやりやすくするために?
(……あの子は、ずっと独りで戦ってきたんだ)
自分の立場を明かさず、守ってもらうこともなく、
ただ“新人秘書”として、あの場に立っていた。
誰にも頼らず、ひたすら仕事に向き合いながら――
(全部、見えてなかったのは……俺の方だった)
「颯真、お前が本気で考えるなら――」
父が口を開いた。
「私から紹介してもいい。“見合い”という形で、話を進めることもできる。だが……」
「だが?」
「彼女は恐らく、相手が“専務”だと知ったら、遠慮する可能性がある。もしかしたら、お前と向き合うことを恐れているかもしれん」
「だったら――」
「だったら、最初は“お前だと知らせない形”で進めるか?」
その提案に、思わず息が止まった。
父の目は冗談ではなかった。
「相手が“上司”だとわかれば、彼女は断るかもしれない。だが、ただの見合い相手なら――一人の男性として話せるだろう」
(……そこまでして、彼女に会いたいか?)
心の中で、自分に問いかける。
答えは、もうわかっていた。
(会いたい)
彼女に、もう一度――
“対等な立場”で、向き合いたい。
“専務と秘書”じゃなくて、
“男と女”として。
彼女が知らない自分の顔を見せて、
彼女の本当の想いを、初めて聞いてみたい。
そう願うことは、もう“間違い”ではない。
「わかった。見合い、受ける」
静かに、でも確かに頷いたとき、
父は満足げに目を細めた。
「なら、準備しておこう。週明けにでも日程を組む。お前の正体は、もちろん伏せておく」
「頼む」
胸の奥が、かすかに震えていた。
これは、きっと最初で最後のチャンスだ。
彼女と“まっすぐに”向き合うための。
この出会いを、“偶然”ではなく“選択”に変えるための――
新しい一歩が、ここから始まる。
「彼女は――○○グループのご令嬢だよ」
応接テーブルに置かれた一枚の資料に、目を通しながら父は続けた。
「〇〇ホールディングス。関東圏じゃなかなかの老舗企業だ。会長は彼女の祖父、現社長が父親で、母親も元華族筋の家系。見合い写真に選ばれるのも当然といえば当然だろう」
その言葉に、俺は思わず視線を落とした。
澪が……ご令嬢?
あの、地味で控えめで、どこかオフィスの片隅で気配を消していた彼女が――?
「しかも、彼女は一貫して付属の女子校に通っていた。大学卒業まで、ずっとだ」
「……箱入り、ってことか?」
「そういう言い方もできるな。本人はいたって真面目で、恋愛経験も……どうやら、ないらしい」
父は笑いを含んだように言った。
「本人もご両親も、“今までそういう交際をしたことがない”と言っていたよ。つまり――」
「……最初から、独りだったんだな」
その言葉が口からこぼれたとき、胸の奥がじわりと熱を帯びた。
あの“婚約者”という噂。
自ら口にしたという話。
社内で勝手に広がっていた推測の数々。
あれは――彼女が、わざと流した“嘘”だったのか。
なぜ?
自分を守るため?
あるいは、仕事をやりやすくするために?
(……あの子は、ずっと独りで戦ってきたんだ)
自分の立場を明かさず、守ってもらうこともなく、
ただ“新人秘書”として、あの場に立っていた。
誰にも頼らず、ひたすら仕事に向き合いながら――
(全部、見えてなかったのは……俺の方だった)
「颯真、お前が本気で考えるなら――」
父が口を開いた。
「私から紹介してもいい。“見合い”という形で、話を進めることもできる。だが……」
「だが?」
「彼女は恐らく、相手が“専務”だと知ったら、遠慮する可能性がある。もしかしたら、お前と向き合うことを恐れているかもしれん」
「だったら――」
「だったら、最初は“お前だと知らせない形”で進めるか?」
その提案に、思わず息が止まった。
父の目は冗談ではなかった。
「相手が“上司”だとわかれば、彼女は断るかもしれない。だが、ただの見合い相手なら――一人の男性として話せるだろう」
(……そこまでして、彼女に会いたいか?)
心の中で、自分に問いかける。
答えは、もうわかっていた。
(会いたい)
彼女に、もう一度――
“対等な立場”で、向き合いたい。
“専務と秘書”じゃなくて、
“男と女”として。
彼女が知らない自分の顔を見せて、
彼女の本当の想いを、初めて聞いてみたい。
そう願うことは、もう“間違い”ではない。
「わかった。見合い、受ける」
静かに、でも確かに頷いたとき、
父は満足げに目を細めた。
「なら、準備しておこう。週明けにでも日程を組む。お前の正体は、もちろん伏せておく」
「頼む」
胸の奥が、かすかに震えていた。
これは、きっと最初で最後のチャンスだ。
彼女と“まっすぐに”向き合うための。
この出会いを、“偶然”ではなく“選択”に変えるための――
新しい一歩が、ここから始まる。