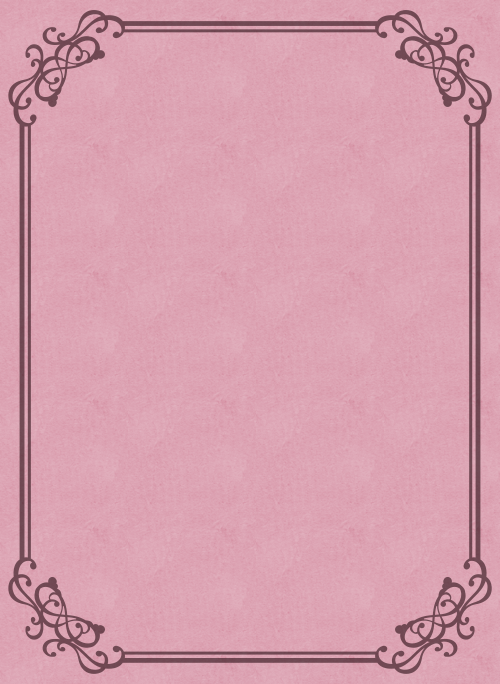目の前にある写真の女性は、間違いなく――高梨澪だった。
表情は少し緊張気味で、それでも控えめに笑っていた。
その姿は、いつものオフィスで見せる顔とはどこか違って見えた。
けれど、俺には一目でわかった。
(どうして……?)
思わず声が漏れた。
(なぜ、彼女が……?)
脳内に、これまでの“前提”が一気に走り回る。
――彼女には婚約者がいる。
――だから、自分は彼女に想いを寄せてはいけない。
――仕事の関係を守るためにも、踏み込んではいけない。
そう自分に言い聞かせ続けてきた。
それが、たとえ噂でしかなくても、彼女自身の口から否定されたわけではなかった。
けれど、今、現実として目の前にある“この写真”が――
そのすべてを、音もなく否定し始めていた。
「……父さん」
低く、静かに問いかけた。
「彼女……高梨澪は、婚約者がいるんじゃないのか?」
その言葉に、父はほんのわずかに眉を上げたが、
次の瞬間には肩をすくめて、ため息混じりに答えた。
「婚約者?いや、聞いてないがな。彼女の家とは何度か会っているが、そういう話はまったくなかったぞ」
「……え」
声が掠れた。
「むしろ、そういう話がどこから出てきたのか、不思議なくらいだな。ご両親も彼女も“まだ誰とも付き合ったことがない”と言っていたし、見合いの話も今回が初めてだ」
(嘘、だろ……)
俺は言葉を失った。
社内で流れていた、あの“婚約者がいる”という噂。
彼女がそれを自分の口で認めたという話。
(じゃあ……あれは、全部……)
何のために?
誰に向けて?
なぜ彼女は、そんな“嘘”を口にしたんだ?
答えのない疑問が、頭の中を駆け巡る。
けれど、ひとつだけはっきりしていることがあった。
(彼女は、ずっと独りだった)
誰かと婚約していたわけじゃない。
誰のものでもなかった。
そう思った瞬間、心の奥が熱くなるのを感じた。
手の中の写真を、ぎゅっと握りしめる。
(……だったら)
だったら、今まで俺が距離を置いてきた理由は、
すべて、崩れたことになる。
“想ってはいけない”という制限も。
“彼女は誰かのものだ”という遠慮も。
全部――
俺自身が勝手に創り上げていた、虚構だった。
「……お前、まさか。彼女のこと、気にしてるのか?」
父の声が、少しだけ揶揄を含んで聞こえた。
俺は返事をしなかった。
ただ、目の前の写真をじっと見つめ続けた。
テニス部時代の凛とした雰囲気も、
新人秘書として必死で食らいついてきたあの背中も。
そのすべてが、この写真一枚に重なっていた。
(彼女が、誰のものでもないのなら――)
(……なら、俺が)
その想いが、心の奥底から湧き上がってきた。
彼女に対して抱いてきた感情を、“諦め”や“我慢”という言葉で封じてきた。
けれど今、その蓋が音を立てて外れた。
はっきりと自覚する。
(俺は、彼女を――)
この手で、幸せにしたいと願っている。
今までは“見守るだけ”でよかった。
でも今は違う。
この気持ちを、もう“隠し通すこと”ができそうにない。
父は、ゆっくりと頷いた。
「お前がその気なら……この見合い、乗ってみてもいいんじゃないか?」
その言葉に、俺は静かに視線を上げた。
この瞬間――
すべてが、変わり始めた。
“無理だ”と思い込んでいた未来。
“叶わない”と決めつけていた関係。
それらが、今、初めて現実として手の中に近づいてきた。
俺はもう迷わない。
(彼女の隣に、俺が立ちたい)
そう強く、胸に刻んだ。
表情は少し緊張気味で、それでも控えめに笑っていた。
その姿は、いつものオフィスで見せる顔とはどこか違って見えた。
けれど、俺には一目でわかった。
(どうして……?)
思わず声が漏れた。
(なぜ、彼女が……?)
脳内に、これまでの“前提”が一気に走り回る。
――彼女には婚約者がいる。
――だから、自分は彼女に想いを寄せてはいけない。
――仕事の関係を守るためにも、踏み込んではいけない。
そう自分に言い聞かせ続けてきた。
それが、たとえ噂でしかなくても、彼女自身の口から否定されたわけではなかった。
けれど、今、現実として目の前にある“この写真”が――
そのすべてを、音もなく否定し始めていた。
「……父さん」
低く、静かに問いかけた。
「彼女……高梨澪は、婚約者がいるんじゃないのか?」
その言葉に、父はほんのわずかに眉を上げたが、
次の瞬間には肩をすくめて、ため息混じりに答えた。
「婚約者?いや、聞いてないがな。彼女の家とは何度か会っているが、そういう話はまったくなかったぞ」
「……え」
声が掠れた。
「むしろ、そういう話がどこから出てきたのか、不思議なくらいだな。ご両親も彼女も“まだ誰とも付き合ったことがない”と言っていたし、見合いの話も今回が初めてだ」
(嘘、だろ……)
俺は言葉を失った。
社内で流れていた、あの“婚約者がいる”という噂。
彼女がそれを自分の口で認めたという話。
(じゃあ……あれは、全部……)
何のために?
誰に向けて?
なぜ彼女は、そんな“嘘”を口にしたんだ?
答えのない疑問が、頭の中を駆け巡る。
けれど、ひとつだけはっきりしていることがあった。
(彼女は、ずっと独りだった)
誰かと婚約していたわけじゃない。
誰のものでもなかった。
そう思った瞬間、心の奥が熱くなるのを感じた。
手の中の写真を、ぎゅっと握りしめる。
(……だったら)
だったら、今まで俺が距離を置いてきた理由は、
すべて、崩れたことになる。
“想ってはいけない”という制限も。
“彼女は誰かのものだ”という遠慮も。
全部――
俺自身が勝手に創り上げていた、虚構だった。
「……お前、まさか。彼女のこと、気にしてるのか?」
父の声が、少しだけ揶揄を含んで聞こえた。
俺は返事をしなかった。
ただ、目の前の写真をじっと見つめ続けた。
テニス部時代の凛とした雰囲気も、
新人秘書として必死で食らいついてきたあの背中も。
そのすべてが、この写真一枚に重なっていた。
(彼女が、誰のものでもないのなら――)
(……なら、俺が)
その想いが、心の奥底から湧き上がってきた。
彼女に対して抱いてきた感情を、“諦め”や“我慢”という言葉で封じてきた。
けれど今、その蓋が音を立てて外れた。
はっきりと自覚する。
(俺は、彼女を――)
この手で、幸せにしたいと願っている。
今までは“見守るだけ”でよかった。
でも今は違う。
この気持ちを、もう“隠し通すこと”ができそうにない。
父は、ゆっくりと頷いた。
「お前がその気なら……この見合い、乗ってみてもいいんじゃないか?」
その言葉に、俺は静かに視線を上げた。
この瞬間――
すべてが、変わり始めた。
“無理だ”と思い込んでいた未来。
“叶わない”と決めつけていた関係。
それらが、今、初めて現実として手の中に近づいてきた。
俺はもう迷わない。
(彼女の隣に、俺が立ちたい)
そう強く、胸に刻んだ。