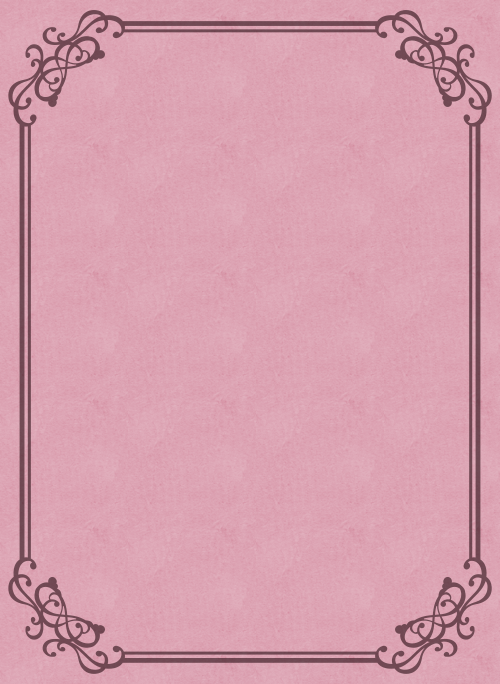「颯真、お前……そろそろ“身を固めても”いい年齢じゃないか?」
金曜の夕方、会議終わりに社長室へ呼ばれた俺に向かって、父――一ノ瀬巌はおもむろにそう切り出した。
無骨なスーツ。背筋を真っすぐに伸ばしたまま、親としてではなく、企業のトップとして語る父の言葉には、いつも余計な感情がなかった。
「お前のことは信頼してる。仕事ぶりも申し分ない。だが……」
「“後継者”として、そろそろ家庭を持つ責任も考えていい頃だと思うんだよ」
「――……結婚には、興味ないよ」
即答した。
それは、本心だった。
恋愛を避けてきたわけじゃない。
けれど、自分の人生に“家庭”という選択肢があると思ったことは、一度もなかった。
心春を育てていくという責任もある。
余計な誤解やしがらみを増やすようなことは、したくなかった。
「ほう……。まあ、そう言うと思った」
父はそう呟きながら、デスクの引き出しを開けた。
「だがな、親としても社長としても――“提案”くらいはさせてもらう」
そう言って、無造作に差し出されたのは、1冊の茶封筒だった。
分厚い。ずしりと重い。
封を開けると、中からは十数枚の写真付きプロフィールシート。
まるで就職活動の履歴書のように整った形式。
名家の令嬢たち。学歴、家柄、教養、特技、年齢……それぞれが表面的には申し分のない女性ばかり。
俺は無言のまま、渋々めくっていった。
(こういうの、昔もあったな)
20代後半の頃、社内で立場が確立しはじめたときにも一度、同じような“押し付け”があった。
もちろん、そのときも即座に断った。
「気に入った相手がいれば一度くらい会ってみろ。そういう気が起きるかもしれん」
そんな父の言葉を半ば聞き流しながら、俺は何枚目かの写真で、ふと手を止めた。
指が、かすかに震えた。
そこに写っていたのは――
高梨澪だった。
淡い色のワンピースに身を包み、緊張したような笑みを浮かべた彼女が、
名家の娘として“紹介されている”紙の中にいた。
【高梨 澪(たかなし みお)】
〇〇グループ会長令嬢/〇〇女子大学卒/現勤務先:一ノ瀬ホールディングス(秘書課)
趣味:読書、テニス
性格:穏やかで控えめ、人の話をよく聞くタイプです
(……嘘だろ)
心臓が、音を立てて跳ねた。
どうして彼女が、ここに?
あんなに“普通”で、“静か”で、“遠慮がち”だった彼女が――
実は、こんなに大きな家の令嬢だったなんて。
ずっと“庶民的な新人秘書”だと思っていた。
社内の誰も、そんなことを話していなかった。
なのに、父は言った。
「彼女、知ってるんだろ?」
「うちの会社にいるんだ。偶然かもしれんが、なかなかいい縁だと思ってな」
「……なぜ、俺に黙ってた?」
「お前に先入観を持ってほしくなかった。現場での彼女を見て、どう感じるか――それで十分だと思ったからだよ」
父の言葉に、俺は返す言葉を失っていた。
目の前にあるプロフィールの中で、
“彼女の素性”が、初めて明かされていた。
それでも――
最初に浮かんだのは、“彼女の婚約者”のことだった。
(……婚約者がいるなら、こんなところに出てくるはずがない)
(じゃあ、あれは――嘘?)
混乱が、胸の奥で音を立てて崩れていく。
じゃあ、あの噂は?
給湯室で聞いた、あの話は――?
高梨澪は、ずっとひとりだったのか?
(……もし、彼女に誰もいないのなら)
胸が、急激に熱を持った。
込み上げてきた感情に、自分で驚く。
でも、もう気づいていた。
彼女を“想っていい”理由が、初めて手の中に転がり込んできた。
ずっと心の奥でしまい込んでいた、
「俺が君の婚約者だったらよかったのに」という願いが――
今、現実になるかもしれない可能性を、
この手が掴みかけていた。
(なら、俺が)
(今度こそ、俺が――彼女の“隣”に立ちたい)
この瞬間、心の中で何かが決まった。
金曜の夕方、会議終わりに社長室へ呼ばれた俺に向かって、父――一ノ瀬巌はおもむろにそう切り出した。
無骨なスーツ。背筋を真っすぐに伸ばしたまま、親としてではなく、企業のトップとして語る父の言葉には、いつも余計な感情がなかった。
「お前のことは信頼してる。仕事ぶりも申し分ない。だが……」
「“後継者”として、そろそろ家庭を持つ責任も考えていい頃だと思うんだよ」
「――……結婚には、興味ないよ」
即答した。
それは、本心だった。
恋愛を避けてきたわけじゃない。
けれど、自分の人生に“家庭”という選択肢があると思ったことは、一度もなかった。
心春を育てていくという責任もある。
余計な誤解やしがらみを増やすようなことは、したくなかった。
「ほう……。まあ、そう言うと思った」
父はそう呟きながら、デスクの引き出しを開けた。
「だがな、親としても社長としても――“提案”くらいはさせてもらう」
そう言って、無造作に差し出されたのは、1冊の茶封筒だった。
分厚い。ずしりと重い。
封を開けると、中からは十数枚の写真付きプロフィールシート。
まるで就職活動の履歴書のように整った形式。
名家の令嬢たち。学歴、家柄、教養、特技、年齢……それぞれが表面的には申し分のない女性ばかり。
俺は無言のまま、渋々めくっていった。
(こういうの、昔もあったな)
20代後半の頃、社内で立場が確立しはじめたときにも一度、同じような“押し付け”があった。
もちろん、そのときも即座に断った。
「気に入った相手がいれば一度くらい会ってみろ。そういう気が起きるかもしれん」
そんな父の言葉を半ば聞き流しながら、俺は何枚目かの写真で、ふと手を止めた。
指が、かすかに震えた。
そこに写っていたのは――
高梨澪だった。
淡い色のワンピースに身を包み、緊張したような笑みを浮かべた彼女が、
名家の娘として“紹介されている”紙の中にいた。
【高梨 澪(たかなし みお)】
〇〇グループ会長令嬢/〇〇女子大学卒/現勤務先:一ノ瀬ホールディングス(秘書課)
趣味:読書、テニス
性格:穏やかで控えめ、人の話をよく聞くタイプです
(……嘘だろ)
心臓が、音を立てて跳ねた。
どうして彼女が、ここに?
あんなに“普通”で、“静か”で、“遠慮がち”だった彼女が――
実は、こんなに大きな家の令嬢だったなんて。
ずっと“庶民的な新人秘書”だと思っていた。
社内の誰も、そんなことを話していなかった。
なのに、父は言った。
「彼女、知ってるんだろ?」
「うちの会社にいるんだ。偶然かもしれんが、なかなかいい縁だと思ってな」
「……なぜ、俺に黙ってた?」
「お前に先入観を持ってほしくなかった。現場での彼女を見て、どう感じるか――それで十分だと思ったからだよ」
父の言葉に、俺は返す言葉を失っていた。
目の前にあるプロフィールの中で、
“彼女の素性”が、初めて明かされていた。
それでも――
最初に浮かんだのは、“彼女の婚約者”のことだった。
(……婚約者がいるなら、こんなところに出てくるはずがない)
(じゃあ、あれは――嘘?)
混乱が、胸の奥で音を立てて崩れていく。
じゃあ、あの噂は?
給湯室で聞いた、あの話は――?
高梨澪は、ずっとひとりだったのか?
(……もし、彼女に誰もいないのなら)
胸が、急激に熱を持った。
込み上げてきた感情に、自分で驚く。
でも、もう気づいていた。
彼女を“想っていい”理由が、初めて手の中に転がり込んできた。
ずっと心の奥でしまい込んでいた、
「俺が君の婚約者だったらよかったのに」という願いが――
今、現実になるかもしれない可能性を、
この手が掴みかけていた。
(なら、俺が)
(今度こそ、俺が――彼女の“隣”に立ちたい)
この瞬間、心の中で何かが決まった。