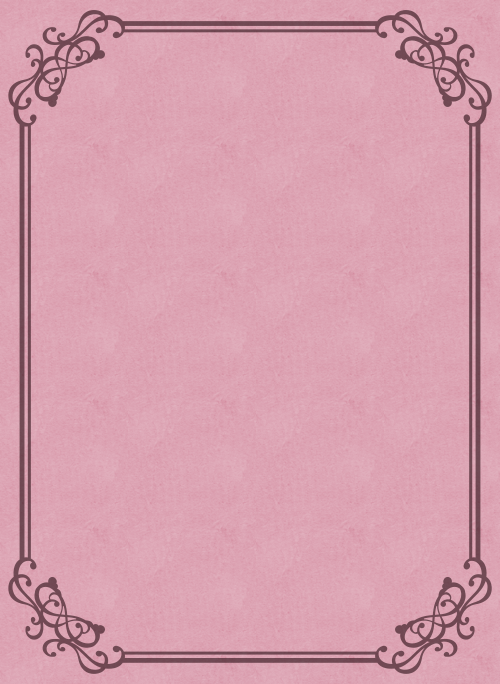週末、少し遅めの午後。
私は、なんとなく立ち寄った本屋の帰り道、大学の近くを歩いていた。
行き先を決めていたわけじゃない。
ただ、自然と足が向いてしまった。
あの頃、テニス部の練習帰りに毎日のように通っていた道。
汗をかいた体に夕陽が差して、フェンス越しに小さな女の子が「がんばれー!」と手を振ってくれた日々。
最近、仕事が忙しくて忘れかけていたその記憶が、季節の香りと共にふいに蘇った気がして、私はその道を歩いていた。
心のどこかで、彼のことを考えていたのかもしれない。
あの日、偶然目にした“あの子”の笑顔が忘れられなくて――
そんなことを思いながら、ふと前方に目をやったそのときだった。
(……えっ)
すぐに気づいた。
彼だった。
一ノ瀬専務が、休日の私服姿で歩いていた。
白シャツにネイビーの薄手ジャケット。
平日のオフィスとは違う、どこかやわらかい空気をまとっていた。
その手を――小さな女の子が、しっかり握っていた。
「あっ……」
私はその場に立ち止まった。
その子も、あの子だった。
フェンス越しに「がんばれー!」と応援してくれた女の子。
あの日、「パパ!」と駆け寄っていった、小さな背中。
ふたりは、笑っていた。
公園帰りなのか、子どもの手には小さな紙袋と、アイスクリームの包み紙が握られている。
特別な何かがあるわけじゃない。
でも、そこにあったのは、明らかに――“日常”だった。
父と娘。
週末の、ささやかな時間。
ふたりの間に流れていたのは、確かなぬくもりだった。
(……幸せそう)
胸の奥が、ぎゅっと締めつけられる。
誰が見ても、「家族」にしか見えなかった。
どんな言い訳も、どんな希望も、その姿を前にしたら無力だった。
(やっぱり……私には、関われない人だ)
どんなに彼の笑顔が嬉しくても、
どんなに彼の言葉があたたかくても、
あの手の中にある小さなぬくもりには、絶対に敵わない。
(あの人には、守るべきものがある)
それが、私じゃないということを――この光景がすべて教えてくれる。
思わず、私は背を向けた。
もう見てはいけない。
このまま立ち止まっていたら、涙があふれてしまいそうだった。
歩き出そうとした、その瞬間。
「……高梨さん?」
背後から、自分の名前を呼ばれる声がした。
一瞬、鼓動が止まったような気がした。
(……え?)
ゆっくりと振り返る。
彼が、私を見ていた。
あの子の手を引いたまま。
困ったように眉を下げ、少し驚いたような顔で。
「偶然……だね」
彼がそう言った。
私は、とっさに笑顔を作った。
「はい……すみません、なんだか懐かしくて。この辺、昔よく来てたので」
「そっか……」
そのとき、あの子が彼の袖をくいっと引っ張って言った。
「パパ、あのお姉ちゃん、テニスのおねえちゃん」
その声に、私は一瞬、目を見開いた。
彼もまた、ほんのわずかに動揺したように見えた。
「……そうか」
そう言って笑った彼の表情が、あまりにも優しくて――私はもう、それ以上見ていられなかった。
「それじゃ、失礼します」
そう言って、小さく頭を下げ、その場を去ろうとした。
でも、背中を向けた瞬間、私は気づいていた。
(ああ……だめだ)
歩き出した足が、重い。
息が、苦しい。
胸の奥が、じくじくと痛む。
――あの人の目の中に、私はいなかった。
あの人の世界には、もう充分な幸せがある。
私なんて、いなくても――あの人は、ちゃんと幸せでいられる。
(それで、いいんだよ)
(私の気持ちは、ただの片想いで終われば、それでいい)
それでも。
どうして、こんなにも、涙がこぼれそうになるんだろう。
家に帰ったあと、シャワーを浴びても、温かい紅茶を淹れても、胸の痛みは引かなかった。
ほんの少しだけでいいから、彼の隣にいたいと思ってしまった私。
それが、どれだけ傲慢だったのか。
あの子の笑顔が教えてくれた。
(やっぱり、私は彼の人生に踏み込んじゃいけない)
恋をしてしまったことは、もう消せない。
でも、だからこそ。
この想いを、誰にも知られないまま、心の中だけにしまっておこう。
窓の外、春の風が街路樹を揺らしていた。
「……好きになってごめんなさい」
誰にも届かない声で、私はそう呟いた。
それが――私の、静かな決意だった。
私は、なんとなく立ち寄った本屋の帰り道、大学の近くを歩いていた。
行き先を決めていたわけじゃない。
ただ、自然と足が向いてしまった。
あの頃、テニス部の練習帰りに毎日のように通っていた道。
汗をかいた体に夕陽が差して、フェンス越しに小さな女の子が「がんばれー!」と手を振ってくれた日々。
最近、仕事が忙しくて忘れかけていたその記憶が、季節の香りと共にふいに蘇った気がして、私はその道を歩いていた。
心のどこかで、彼のことを考えていたのかもしれない。
あの日、偶然目にした“あの子”の笑顔が忘れられなくて――
そんなことを思いながら、ふと前方に目をやったそのときだった。
(……えっ)
すぐに気づいた。
彼だった。
一ノ瀬専務が、休日の私服姿で歩いていた。
白シャツにネイビーの薄手ジャケット。
平日のオフィスとは違う、どこかやわらかい空気をまとっていた。
その手を――小さな女の子が、しっかり握っていた。
「あっ……」
私はその場に立ち止まった。
その子も、あの子だった。
フェンス越しに「がんばれー!」と応援してくれた女の子。
あの日、「パパ!」と駆け寄っていった、小さな背中。
ふたりは、笑っていた。
公園帰りなのか、子どもの手には小さな紙袋と、アイスクリームの包み紙が握られている。
特別な何かがあるわけじゃない。
でも、そこにあったのは、明らかに――“日常”だった。
父と娘。
週末の、ささやかな時間。
ふたりの間に流れていたのは、確かなぬくもりだった。
(……幸せそう)
胸の奥が、ぎゅっと締めつけられる。
誰が見ても、「家族」にしか見えなかった。
どんな言い訳も、どんな希望も、その姿を前にしたら無力だった。
(やっぱり……私には、関われない人だ)
どんなに彼の笑顔が嬉しくても、
どんなに彼の言葉があたたかくても、
あの手の中にある小さなぬくもりには、絶対に敵わない。
(あの人には、守るべきものがある)
それが、私じゃないということを――この光景がすべて教えてくれる。
思わず、私は背を向けた。
もう見てはいけない。
このまま立ち止まっていたら、涙があふれてしまいそうだった。
歩き出そうとした、その瞬間。
「……高梨さん?」
背後から、自分の名前を呼ばれる声がした。
一瞬、鼓動が止まったような気がした。
(……え?)
ゆっくりと振り返る。
彼が、私を見ていた。
あの子の手を引いたまま。
困ったように眉を下げ、少し驚いたような顔で。
「偶然……だね」
彼がそう言った。
私は、とっさに笑顔を作った。
「はい……すみません、なんだか懐かしくて。この辺、昔よく来てたので」
「そっか……」
そのとき、あの子が彼の袖をくいっと引っ張って言った。
「パパ、あのお姉ちゃん、テニスのおねえちゃん」
その声に、私は一瞬、目を見開いた。
彼もまた、ほんのわずかに動揺したように見えた。
「……そうか」
そう言って笑った彼の表情が、あまりにも優しくて――私はもう、それ以上見ていられなかった。
「それじゃ、失礼します」
そう言って、小さく頭を下げ、その場を去ろうとした。
でも、背中を向けた瞬間、私は気づいていた。
(ああ……だめだ)
歩き出した足が、重い。
息が、苦しい。
胸の奥が、じくじくと痛む。
――あの人の目の中に、私はいなかった。
あの人の世界には、もう充分な幸せがある。
私なんて、いなくても――あの人は、ちゃんと幸せでいられる。
(それで、いいんだよ)
(私の気持ちは、ただの片想いで終われば、それでいい)
それでも。
どうして、こんなにも、涙がこぼれそうになるんだろう。
家に帰ったあと、シャワーを浴びても、温かい紅茶を淹れても、胸の痛みは引かなかった。
ほんの少しだけでいいから、彼の隣にいたいと思ってしまった私。
それが、どれだけ傲慢だったのか。
あの子の笑顔が教えてくれた。
(やっぱり、私は彼の人生に踏み込んじゃいけない)
恋をしてしまったことは、もう消せない。
でも、だからこそ。
この想いを、誰にも知られないまま、心の中だけにしまっておこう。
窓の外、春の風が街路樹を揺らしていた。
「……好きになってごめんなさい」
誰にも届かない声で、私はそう呟いた。
それが――私の、静かな決意だった。