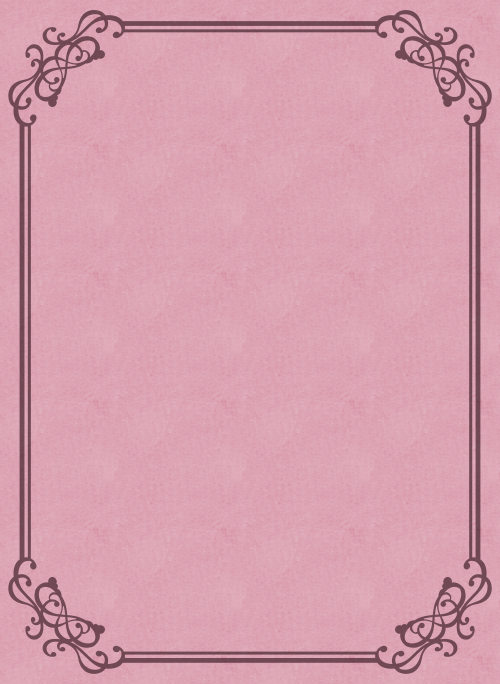日曜日の朝。
本来なら遅く起きて、コーヒーでも淹れて、洗濯や掃除に追われるはずの休日。
けれど、今日は違った。
昨晩入った急ぎの連絡。
システムトラブルと、外部との対応に備えた資料の再確認。
社内の人員が限られているなか、対応可能なメンバーとして、私は名前を挙げられた。
(休日出勤なんて、滅多にないのに……)
着慣れないスーツに袖を通しながら、小さく息を吐いた。
静かな朝の通勤電車。
平日とは違い、同じスーツ姿の人はほとんど見かけなかった。
車窓の外を流れる町並みは、どこか緩やかに光を浴びていて、街も人も週末のやわらかな空気に包まれていた。
(この空気の中で、会社に向かうのは……やっぱり少し、さみしい)
それでも、気を引き締めて会社の自動ドアをくぐった。
誰もいないエントランス。
警備員の挨拶が、やけに響いた。
そして。
まさか、あの人が来るなんて――思っていなかった。
「……専務?」
スーツではなく、私服姿。
シンプルなシャツに、落ち着いた色味のジャケット。
いつものようなピンとした背筋ではなく、少しだけリラックスした佇まい。
「……ああ。おはよう。来てくれて助かるよ」
「おはようございます。えっと……てっきり、今日は私だけかと……」
「トラブル対応だし、一応ね。念のため」
いつものように無駄のない口調。
でも、その声が、今日は少しだけ“軽やか”に感じられた。
(こんな顔、こんな声……初めてかもしれない)
ぎこちなく微笑む私に、彼はすぐに話題を仕事へと戻した。
けれど、私の心は――すでに、何かが静かに波立っていた。
午前中の作業は、淡々と進んだ。
担当部署への確認。
提出用資料の修正と再出力。
専務と確認を取り合いながら進める作業は、普段と変わらないはずなのに、空気だけがどこか違っていた。
フロアには、私たちふたりの足音と、キーボードの打鍵音だけが静かに響く。
それが、やけに心地よかった。
気づけば、仕事の手際も自然と合ってきていた。
私が資料を差し出すと、彼が無言でそれを受け取り、目を通す。
そして、何も言わずに付箋を貼って返してくれる。
言葉を交わさなくても、伝わるリズムがそこにある。
(……こんな空気、初めて)
それが、怖いくらいに嬉しかった。
昼過ぎ、コピーを取りに行こうと立ち上がったときだった。
ふと顔を上げると――また、彼と目が合った。
本当に、ただの偶然。
でも、その一瞬、私の中の何かが弾けた。
「……ふふっ」
つい、笑ってしまった。
微笑みというよりは、なんだか照れ笑いに近かった。
休日に、誰もいない会社で、まさかこんな風に笑いかけるなんて。
しかも、相手は――あの専務。
(変だよね、私)
でもそのとき。
彼の口元が、ふっと――少しだけ、緩んだように見えた。
(……え?)
見間違いじゃなかった。
あの、一ノ瀬専務が――笑った。
少しだけ、ほんの一瞬だけ。
でも確かに、優しい光がその顔に浮かんでいた。
胸が高鳴った。
一瞬で熱がこもる。
(……夢みたい)
この人のそんな顔、見たことない。
今だけ、誰もいないこの空間で、ふたりきりだからこそ、見せてくれた表情なのかもしれない――
そんなふうに、思ってしまった。
午後。
会議資料の束を抱えて戻る途中、狭い通路ですれ違う。
彼がほんの少し体を避けてくれた瞬間――
ふと、指先が触れた。
一瞬だった。
ほんの一瞬。
でも、そこには確かな熱があった。
(……!)
思わず息を呑んだ。
指先に、電気が走ったみたいだった。
全身が一瞬、硬直する。
彼もまた、わずかに動きを止めた。
けれど、何も言わず、そのまま通り過ぎた。
(いけない……)
(きっと、これ以上近づいたら、もう戻れなくなる)
心がそう告げていた。
でも。
それでも――
触れた指先は、まだ熱を帯びたままだった。
午後の仕事を終えて、ふたりでエントランスまで戻ったとき。
彼がふと口にした。
「……最初の頃と比べたら、だいぶ変わったな」
「え?」
「君が、ね。落ち着いてきたというか」
私は一瞬、返す言葉を失ってから、そっと微笑んだ。
「……ありがとうございます。専務のおかげです」
そう答えると、彼は一瞬、何か言いかけて――やめた。
ただ、静かに「気をつけて帰れよ」とだけ言った。
その声が、やさしかった。
帰り道。
歩きながら、自分の手をそっと見つめた。
ふと触れたあの瞬間。
彼の笑顔。
休日の静かな会社で交わした、言葉少ななやりとり。
全部、きっと仕事には関係のないもの。
でも、私の心には、深く残った。
(このままじゃダメだって、分かってるのに)
なのに、心はどんどん彼に近づいていく。
怖いくらいに。
嬉しくて、切なくて――でも、どうしようもなく恋しかった。
本来なら遅く起きて、コーヒーでも淹れて、洗濯や掃除に追われるはずの休日。
けれど、今日は違った。
昨晩入った急ぎの連絡。
システムトラブルと、外部との対応に備えた資料の再確認。
社内の人員が限られているなか、対応可能なメンバーとして、私は名前を挙げられた。
(休日出勤なんて、滅多にないのに……)
着慣れないスーツに袖を通しながら、小さく息を吐いた。
静かな朝の通勤電車。
平日とは違い、同じスーツ姿の人はほとんど見かけなかった。
車窓の外を流れる町並みは、どこか緩やかに光を浴びていて、街も人も週末のやわらかな空気に包まれていた。
(この空気の中で、会社に向かうのは……やっぱり少し、さみしい)
それでも、気を引き締めて会社の自動ドアをくぐった。
誰もいないエントランス。
警備員の挨拶が、やけに響いた。
そして。
まさか、あの人が来るなんて――思っていなかった。
「……専務?」
スーツではなく、私服姿。
シンプルなシャツに、落ち着いた色味のジャケット。
いつものようなピンとした背筋ではなく、少しだけリラックスした佇まい。
「……ああ。おはよう。来てくれて助かるよ」
「おはようございます。えっと……てっきり、今日は私だけかと……」
「トラブル対応だし、一応ね。念のため」
いつものように無駄のない口調。
でも、その声が、今日は少しだけ“軽やか”に感じられた。
(こんな顔、こんな声……初めてかもしれない)
ぎこちなく微笑む私に、彼はすぐに話題を仕事へと戻した。
けれど、私の心は――すでに、何かが静かに波立っていた。
午前中の作業は、淡々と進んだ。
担当部署への確認。
提出用資料の修正と再出力。
専務と確認を取り合いながら進める作業は、普段と変わらないはずなのに、空気だけがどこか違っていた。
フロアには、私たちふたりの足音と、キーボードの打鍵音だけが静かに響く。
それが、やけに心地よかった。
気づけば、仕事の手際も自然と合ってきていた。
私が資料を差し出すと、彼が無言でそれを受け取り、目を通す。
そして、何も言わずに付箋を貼って返してくれる。
言葉を交わさなくても、伝わるリズムがそこにある。
(……こんな空気、初めて)
それが、怖いくらいに嬉しかった。
昼過ぎ、コピーを取りに行こうと立ち上がったときだった。
ふと顔を上げると――また、彼と目が合った。
本当に、ただの偶然。
でも、その一瞬、私の中の何かが弾けた。
「……ふふっ」
つい、笑ってしまった。
微笑みというよりは、なんだか照れ笑いに近かった。
休日に、誰もいない会社で、まさかこんな風に笑いかけるなんて。
しかも、相手は――あの専務。
(変だよね、私)
でもそのとき。
彼の口元が、ふっと――少しだけ、緩んだように見えた。
(……え?)
見間違いじゃなかった。
あの、一ノ瀬専務が――笑った。
少しだけ、ほんの一瞬だけ。
でも確かに、優しい光がその顔に浮かんでいた。
胸が高鳴った。
一瞬で熱がこもる。
(……夢みたい)
この人のそんな顔、見たことない。
今だけ、誰もいないこの空間で、ふたりきりだからこそ、見せてくれた表情なのかもしれない――
そんなふうに、思ってしまった。
午後。
会議資料の束を抱えて戻る途中、狭い通路ですれ違う。
彼がほんの少し体を避けてくれた瞬間――
ふと、指先が触れた。
一瞬だった。
ほんの一瞬。
でも、そこには確かな熱があった。
(……!)
思わず息を呑んだ。
指先に、電気が走ったみたいだった。
全身が一瞬、硬直する。
彼もまた、わずかに動きを止めた。
けれど、何も言わず、そのまま通り過ぎた。
(いけない……)
(きっと、これ以上近づいたら、もう戻れなくなる)
心がそう告げていた。
でも。
それでも――
触れた指先は、まだ熱を帯びたままだった。
午後の仕事を終えて、ふたりでエントランスまで戻ったとき。
彼がふと口にした。
「……最初の頃と比べたら、だいぶ変わったな」
「え?」
「君が、ね。落ち着いてきたというか」
私は一瞬、返す言葉を失ってから、そっと微笑んだ。
「……ありがとうございます。専務のおかげです」
そう答えると、彼は一瞬、何か言いかけて――やめた。
ただ、静かに「気をつけて帰れよ」とだけ言った。
その声が、やさしかった。
帰り道。
歩きながら、自分の手をそっと見つめた。
ふと触れたあの瞬間。
彼の笑顔。
休日の静かな会社で交わした、言葉少ななやりとり。
全部、きっと仕事には関係のないもの。
でも、私の心には、深く残った。
(このままじゃダメだって、分かってるのに)
なのに、心はどんどん彼に近づいていく。
怖いくらいに。
嬉しくて、切なくて――でも、どうしようもなく恋しかった。