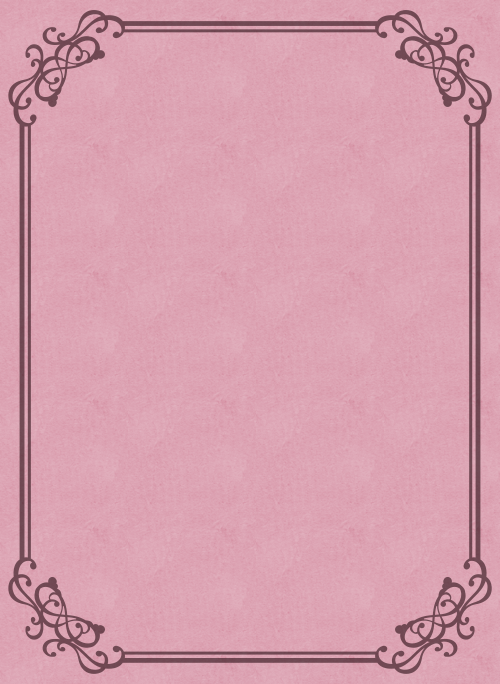会議準備の時間というのは、どうしてこうも落ち着かないのだろう。
時間に余裕を持って行動しているつもりでも、直前になればなるほど、細かい確認や忘れものの心配に追われて、頭も心もそわそわしてくる。
この日も例に漏れず、私は大きな資料を抱えて会議室を出たり入ったりしていた。
プロジェクターの接続確認、議事録フォーマットの再印刷、予備資料のクリップ留め、席次表の配置――
一つでも漏れがあれば、全部が台無しになる。
そんな緊張感に背中を押されながら、私は資料棚へと向かっていた。
ふと、何かを取りに戻ろうと振り返った瞬間。
目が合った。
会議室のガラス越しに、一ノ瀬専務がいた。
彼も同じように、机の上の書類に目を落としていたはずだったのに、なぜかこちらを見ていた。
(……え?)
目が、確かに合っていた。
それはほんの一瞬だったのに、時間が止まったように感じた。
反射的に、私は――にこっと、笑ってしまった。
(しまった……!)
笑顔なんて、業務中に。
しかも専務相手に。
しかも、こんなタイミングで――!
自分でも驚くほど自然な笑みがこぼれてしまったことに、後から気づいた。
でも、それ以上に驚いたのは――
一ノ瀬専務の反応だった。
手元の書類を、彼が閉じようとした――けれど、向きを間違えた。
それに気づいた彼は、すぐにそれを正したが、その指先がどこかぎこちなくて、そしてその瞬間、彼は少しだけ目をそらした。
(……え?)
(今……動揺、してた?)
思わず、胸の奥でざわめきが広がる。
(私の笑顔に、反応した……?)
考えすぎかもしれない。
たまたま見つめ合ってしまっただけかもしれない。
でも、あのわずかな“閉じ間違え”は、今まで一度も見たことがなかった。
彼はいつも冷静で、正確で、無駄がない。
それなのに。
まるで――目を奪われていたかのような、手の動きだった。
(まさか……)
(そんなはず、ないよね)
思考の隅で、自分の中の“期待”が暴れ出す。
でも、それと同時に、現実が重くのしかかる。
(だって、私は“婚約者がいる”ことになってる)
社内の誰もが、私に“相手がいる”と思っている。
それが前提の立ち位置で、私は一ノ瀬専務の秘書としてここにいる。
それに――
(専務には、子どもがいる)
大学近くで偶然見かけた、あの女の子。
笑顔で「パパ」と呼んだ、あの無垢な声。
あの子が、専務の“家族”のすべてを物語っていた。
(だから、勘違いなんてしちゃいけない)
彼が私を見ていたのも。
書類を閉じ間違えたのも。
目をそらしたのも。
すべて、偶然――そう思わなければいけない。
でも。
(……嬉しかった)
それでも、私は――
ほんの一瞬、恋愛対象として見てもらえたような気がして。
誰にも言えないけれど、心の中ではずっと、その瞬間がリフレインしていた。
目が合ったこと。
笑ったこと。
彼が動揺した“ように見えた”こと。
そして、そのあと彼が何も言わずに書類を整理し直して、淡々と会議を始めたこと。
(何でもないふりをしていたけれど――)
(もしかしたら、少しだけ……同じように感じてくれてたのかもしれない)
期待と、現実と、感情のはざまで心が揺れた。
「婚約者がいる」「子どもがいる」
そういう“前提”を何重にも積み上げて、ようやく落ち着いた場所だったのに。
その土台が、今、小さく軋みはじめていた。
帰り道。スマートフォンを開いて、ふと今日のスケジュールを見返す。
「15:00 役員会議」
それだけの記録。
でも、その横に手書きで小さく“資料・向きミス”とメモしてあった。
あの瞬間、彼が間違えたこと。
それが、私の中では“記憶に残したい”出来事になってしまっていた。
それがどんなにくだらないことでも。
意味がないとわかっていても。
私にとっては、“彼が動揺した唯一の瞬間”だった。
(また明日、顔を合わせる)
それが楽しみで、怖かった。
(今度は……私は、どんな顔をすればいいの)
(また、笑ってしまったら――)
心のどこかで、またあの瞬間を期待してしまっている自分がいる。
夜。
鏡の前で髪をとかしながら、自分の目元が、ほんの少し緩んでいることに気づいた。
「ああ……嬉しかったんだ、やっぱり」
無意識に口からこぼれた言葉。
(好きになっちゃ、ダメなのに)
ずっとそう思ってきた。
でも、そう思えば思うほど、嬉しさは増していく。
どうして、こんなに嬉しかったんだろう。
それが、ただの勘違いだったとしても。
たった一瞬の交差だったとしても。
私の心は、確かに揺れた。
そして――もう、止まらないところまで来てしまっていた。
時間に余裕を持って行動しているつもりでも、直前になればなるほど、細かい確認や忘れものの心配に追われて、頭も心もそわそわしてくる。
この日も例に漏れず、私は大きな資料を抱えて会議室を出たり入ったりしていた。
プロジェクターの接続確認、議事録フォーマットの再印刷、予備資料のクリップ留め、席次表の配置――
一つでも漏れがあれば、全部が台無しになる。
そんな緊張感に背中を押されながら、私は資料棚へと向かっていた。
ふと、何かを取りに戻ろうと振り返った瞬間。
目が合った。
会議室のガラス越しに、一ノ瀬専務がいた。
彼も同じように、机の上の書類に目を落としていたはずだったのに、なぜかこちらを見ていた。
(……え?)
目が、確かに合っていた。
それはほんの一瞬だったのに、時間が止まったように感じた。
反射的に、私は――にこっと、笑ってしまった。
(しまった……!)
笑顔なんて、業務中に。
しかも専務相手に。
しかも、こんなタイミングで――!
自分でも驚くほど自然な笑みがこぼれてしまったことに、後から気づいた。
でも、それ以上に驚いたのは――
一ノ瀬専務の反応だった。
手元の書類を、彼が閉じようとした――けれど、向きを間違えた。
それに気づいた彼は、すぐにそれを正したが、その指先がどこかぎこちなくて、そしてその瞬間、彼は少しだけ目をそらした。
(……え?)
(今……動揺、してた?)
思わず、胸の奥でざわめきが広がる。
(私の笑顔に、反応した……?)
考えすぎかもしれない。
たまたま見つめ合ってしまっただけかもしれない。
でも、あのわずかな“閉じ間違え”は、今まで一度も見たことがなかった。
彼はいつも冷静で、正確で、無駄がない。
それなのに。
まるで――目を奪われていたかのような、手の動きだった。
(まさか……)
(そんなはず、ないよね)
思考の隅で、自分の中の“期待”が暴れ出す。
でも、それと同時に、現実が重くのしかかる。
(だって、私は“婚約者がいる”ことになってる)
社内の誰もが、私に“相手がいる”と思っている。
それが前提の立ち位置で、私は一ノ瀬専務の秘書としてここにいる。
それに――
(専務には、子どもがいる)
大学近くで偶然見かけた、あの女の子。
笑顔で「パパ」と呼んだ、あの無垢な声。
あの子が、専務の“家族”のすべてを物語っていた。
(だから、勘違いなんてしちゃいけない)
彼が私を見ていたのも。
書類を閉じ間違えたのも。
目をそらしたのも。
すべて、偶然――そう思わなければいけない。
でも。
(……嬉しかった)
それでも、私は――
ほんの一瞬、恋愛対象として見てもらえたような気がして。
誰にも言えないけれど、心の中ではずっと、その瞬間がリフレインしていた。
目が合ったこと。
笑ったこと。
彼が動揺した“ように見えた”こと。
そして、そのあと彼が何も言わずに書類を整理し直して、淡々と会議を始めたこと。
(何でもないふりをしていたけれど――)
(もしかしたら、少しだけ……同じように感じてくれてたのかもしれない)
期待と、現実と、感情のはざまで心が揺れた。
「婚約者がいる」「子どもがいる」
そういう“前提”を何重にも積み上げて、ようやく落ち着いた場所だったのに。
その土台が、今、小さく軋みはじめていた。
帰り道。スマートフォンを開いて、ふと今日のスケジュールを見返す。
「15:00 役員会議」
それだけの記録。
でも、その横に手書きで小さく“資料・向きミス”とメモしてあった。
あの瞬間、彼が間違えたこと。
それが、私の中では“記憶に残したい”出来事になってしまっていた。
それがどんなにくだらないことでも。
意味がないとわかっていても。
私にとっては、“彼が動揺した唯一の瞬間”だった。
(また明日、顔を合わせる)
それが楽しみで、怖かった。
(今度は……私は、どんな顔をすればいいの)
(また、笑ってしまったら――)
心のどこかで、またあの瞬間を期待してしまっている自分がいる。
夜。
鏡の前で髪をとかしながら、自分の目元が、ほんの少し緩んでいることに気づいた。
「ああ……嬉しかったんだ、やっぱり」
無意識に口からこぼれた言葉。
(好きになっちゃ、ダメなのに)
ずっとそう思ってきた。
でも、そう思えば思うほど、嬉しさは増していく。
どうして、こんなに嬉しかったんだろう。
それが、ただの勘違いだったとしても。
たった一瞬の交差だったとしても。
私の心は、確かに揺れた。
そして――もう、止まらないところまで来てしまっていた。