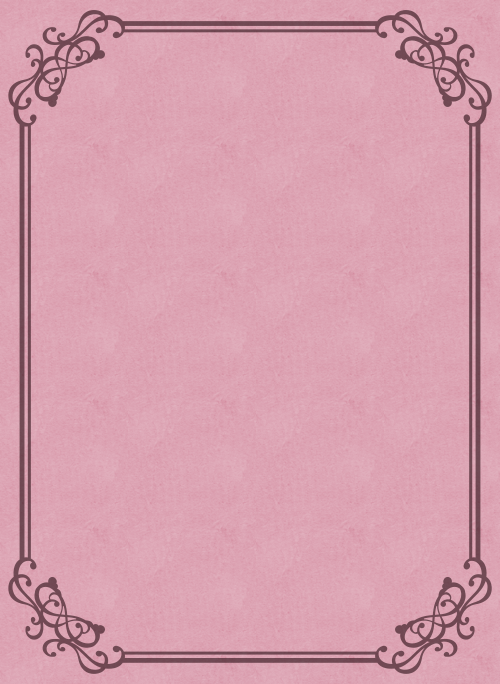「今日は、午後からのプレゼン……不安なら、一度説明してみるか?」
昼前、会議室のホワイトボードをチェックしていたとき、ふと背後から声がした。
振り向けば、そこには一ノ瀬専務の姿。
「え……あ、はい」
私は慌てて資料を持ち直しながら、彼の顔をまともに見られなかった。
「……でも、大丈夫です。準備は万端なので」
そう返すと、専務はふっと目を細めて、ほんの少しだけ頷いた。
「そうか。じゃあ、任せたよ」
いつもよりもわずかに柔らかい声音。
その一言が、まるでご褒美のように胸に落ちた。
(……頼られてる)
その言葉に甘えてしまいそうになる。
(この人の隣に、いたい)
そう思ってしまった自分がいた。
“頼りたい”でもなく、“褒められたい”でもなく、“支えてあげたい”でもない。
ただ、あの人のそばにいたい。
疲れているときに、そっと肩を貸してあげたい。
それくらいの、何でもない関係になりたくて――
(でも、それは……)
その瞬間、胸に鋭い痛みが走った。
思い出してしまった。
あの子のことを。
夕暮れ時の歩道橋。
大学のフェンス越しに見えた小さな背中。
「パパ!」と笑いながら手を振る、あの声。
ふわりと揺れるツインテール。
お揃いのリュック。
無邪気な笑顔。
あの子の存在が、一ノ瀬専務の「父親としての顔」を確かに証明していた。
私は、その光景を、確かに見てしまった。
(あの子のいる場所が、あの人の帰る場所)
(あの子の笑顔が、あの人の一番の癒し)
(私は……そこには、いられない)
目を閉じる。
呼吸を整える。
(そうだよ、私はただの“秘書”)
(この人の隣にいられるのは、業務の中だけ)
そう何度も心の中で繰り返した。
けれど、どうしてだろう。
言えば言うほど、逆に感情があふれそうになる。
午後の会議。
プロジェクトの進行管理を補佐する立場として、資料を一ノ瀬専務に代わって説明することになっていた。
「以上が今月分の進捗と課題です。次回のレビューまでに、調整項目の洗い出しを進めてまいります」
きちんと話せた。
声も震えなかった。
同席した他部署の課長からも「わかりやすかった」と言われ、内心で小さくガッツポーズを取った。
(よかった……無事に終わった)
そのとき、隣にいた専務が小さく言った。
「……堂々としてたな。助かった」
それだけの言葉。
けれど私は、一瞬心臓が止まりそうになった。
声を聞いた瞬間――“寄りかかりたい”と思ってしまった。
終わったあと、彼の前で、ただ静かに肩を落としたい。
「頑張りましたね」と言ってもらいたい。
そのまま、あたたかい声の中で、今日一日の疲れを流したかった。
(だめ……だめ)
(それは……仕事じゃない)
私は、自分にそう言い聞かせた。
夕方、コピー機の前。
紙が出てくる音を聞きながら、私はぼんやりと宙を見ていた。
(家庭がある人を、好きになるなんて)
(自分がこんなにも愚かだなんて、思ってもみなかった)
彼のことを知れば知るほど、好きになってしまう。
彼の声を聞くたびに、心があたたかくなる。
でも、そんな気持ちの先にあるのは、誰かの居場所を奪うことかもしれない。
(あの子の笑顔を壊してしまうかもしれない)
(そんなこと、絶対にしたくない)
私は、あの人の幸せを壊したくて好きになったわけじゃない。
ただ、惹かれてしまった。
ただ、目を逸らせなかった。
でも、それだけでは許されない。
だから私は、決めた。
(私は、秘書という役割を全うする)
この想いは、表に出さない。
誰にも知られないまま、静かに、心の奥にしまっておく。
そして――彼にとって、“やりやすい秘書”でいることだけを、考えよう。
夜。
帰宅して、化粧を落として、髪をほどいても――鏡に映る自分の目は、どこか泣き出しそうだった。
寄りかかりたかった。
頼られたかった。
あの優しさに包まれたかった。
でも、私はそれを選ばなかった。
選んではいけなかった。
(この気持ちを、なかったことにはできない)
けれど――
(せめて、誰の迷惑にもならないように)
それが、私にできる、最後の“誠実”だった。
昼前、会議室のホワイトボードをチェックしていたとき、ふと背後から声がした。
振り向けば、そこには一ノ瀬専務の姿。
「え……あ、はい」
私は慌てて資料を持ち直しながら、彼の顔をまともに見られなかった。
「……でも、大丈夫です。準備は万端なので」
そう返すと、専務はふっと目を細めて、ほんの少しだけ頷いた。
「そうか。じゃあ、任せたよ」
いつもよりもわずかに柔らかい声音。
その一言が、まるでご褒美のように胸に落ちた。
(……頼られてる)
その言葉に甘えてしまいそうになる。
(この人の隣に、いたい)
そう思ってしまった自分がいた。
“頼りたい”でもなく、“褒められたい”でもなく、“支えてあげたい”でもない。
ただ、あの人のそばにいたい。
疲れているときに、そっと肩を貸してあげたい。
それくらいの、何でもない関係になりたくて――
(でも、それは……)
その瞬間、胸に鋭い痛みが走った。
思い出してしまった。
あの子のことを。
夕暮れ時の歩道橋。
大学のフェンス越しに見えた小さな背中。
「パパ!」と笑いながら手を振る、あの声。
ふわりと揺れるツインテール。
お揃いのリュック。
無邪気な笑顔。
あの子の存在が、一ノ瀬専務の「父親としての顔」を確かに証明していた。
私は、その光景を、確かに見てしまった。
(あの子のいる場所が、あの人の帰る場所)
(あの子の笑顔が、あの人の一番の癒し)
(私は……そこには、いられない)
目を閉じる。
呼吸を整える。
(そうだよ、私はただの“秘書”)
(この人の隣にいられるのは、業務の中だけ)
そう何度も心の中で繰り返した。
けれど、どうしてだろう。
言えば言うほど、逆に感情があふれそうになる。
午後の会議。
プロジェクトの進行管理を補佐する立場として、資料を一ノ瀬専務に代わって説明することになっていた。
「以上が今月分の進捗と課題です。次回のレビューまでに、調整項目の洗い出しを進めてまいります」
きちんと話せた。
声も震えなかった。
同席した他部署の課長からも「わかりやすかった」と言われ、内心で小さくガッツポーズを取った。
(よかった……無事に終わった)
そのとき、隣にいた専務が小さく言った。
「……堂々としてたな。助かった」
それだけの言葉。
けれど私は、一瞬心臓が止まりそうになった。
声を聞いた瞬間――“寄りかかりたい”と思ってしまった。
終わったあと、彼の前で、ただ静かに肩を落としたい。
「頑張りましたね」と言ってもらいたい。
そのまま、あたたかい声の中で、今日一日の疲れを流したかった。
(だめ……だめ)
(それは……仕事じゃない)
私は、自分にそう言い聞かせた。
夕方、コピー機の前。
紙が出てくる音を聞きながら、私はぼんやりと宙を見ていた。
(家庭がある人を、好きになるなんて)
(自分がこんなにも愚かだなんて、思ってもみなかった)
彼のことを知れば知るほど、好きになってしまう。
彼の声を聞くたびに、心があたたかくなる。
でも、そんな気持ちの先にあるのは、誰かの居場所を奪うことかもしれない。
(あの子の笑顔を壊してしまうかもしれない)
(そんなこと、絶対にしたくない)
私は、あの人の幸せを壊したくて好きになったわけじゃない。
ただ、惹かれてしまった。
ただ、目を逸らせなかった。
でも、それだけでは許されない。
だから私は、決めた。
(私は、秘書という役割を全うする)
この想いは、表に出さない。
誰にも知られないまま、静かに、心の奥にしまっておく。
そして――彼にとって、“やりやすい秘書”でいることだけを、考えよう。
夜。
帰宅して、化粧を落として、髪をほどいても――鏡に映る自分の目は、どこか泣き出しそうだった。
寄りかかりたかった。
頼られたかった。
あの優しさに包まれたかった。
でも、私はそれを選ばなかった。
選んではいけなかった。
(この気持ちを、なかったことにはできない)
けれど――
(せめて、誰の迷惑にもならないように)
それが、私にできる、最後の“誠実”だった。