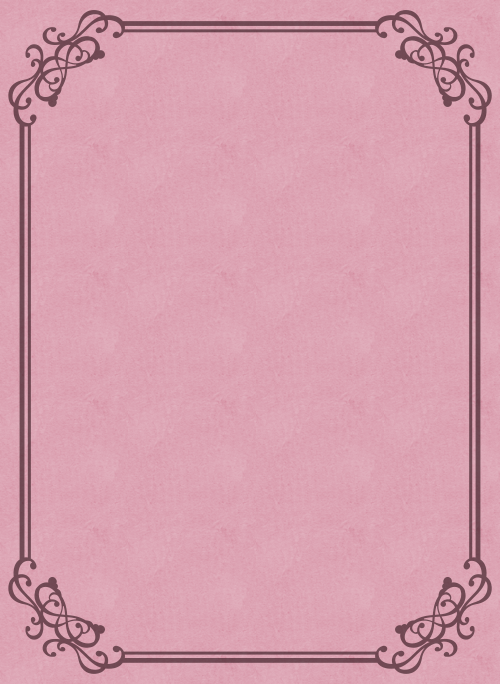「今日から、社会人かぁ……」
口に出してみても、実感は湧かなかった。手にした社員証の角が、指先にひりつく。春の朝。緊張で早く目が覚めてしまった私は、指定されたオフィスビルの前でしばらく深呼吸を繰り返していた。
背筋を伸ばして見上げる高層ビル。その無機質なガラス張りの建物は、まるでこれから私が飛び込もうとしている社会そのものを象徴しているようで、言葉にはできない不安が胸の奥からじんわりと広がっていく。
私は大学を卒業したばかりの新入社員。就職活動中には「自分の強みは行動力です!」なんてキラキラした目で言っていたけれど、いざ本当に入社となると、足元がぐらつくような心許なさばかりが募る。
受付で名前と配属先を告げると、社員証とフロアマップが手渡された。
「秘書課は11階になります。こちらのエレベーターをご利用ください」
静かな声とともに差し出されたカードを握りしめ、案内されたエレベーターに乗り込む。上昇するたびに耳がツンとし、胸の奥がざわついた。
(なんで秘書課なんだろう)
正直に言えば、私は秘書志望ではなかった。学生時代、部活動やゼミで人をまとめる役目をしていたせいか、最終面接の際には「総合職として現場にも出てみたいです」と意欲を語った。まさか配属通知で『秘書課』と告げられるとは思わなかった。
秘書――それはどこか遠い存在のように感じていた。上司のスケジュールを管理し、会議の準備をし、常に誰かの“後ろ”にいる職業。自分とはあまり縁のない仕事だと勝手に思っていた。でも、そんな私が、今まさにその世界に足を踏み入れようとしている。
エレベーターの扉が静かに開いた瞬間、空気が変わった。
磨き上げられたフロアの床、淡いベージュで統一された内装。静けさの中に、靴音だけが控えめに響いていた。どこか背筋が伸びるような緊張感に包まれている。社員たちはみな穏やかな表情で業務にあたっているように見えるけれど、その内側にピンと張り詰めた糸のようなものを感じた。
案内されたのは、奥まった一角にある秘書課のエリアだった。
「失礼します。本日より配属されました、新入社員の――」
声が震えないように気をつけたつもりだったが、挨拶を終えると喉がからからになっていることに気づいた。緊張で背中にはじんわり汗が滲んでいる。
「あなたが、新しく来た子?」
奥から近づいてきたのは、タイトなスカートに身を包んだ、三十代前半ほどの女性だった。巻いた髪をゆるくまとめていて、きりりとした目元が印象的。化粧は控えめだけれど、洗練された雰囲気があり、一目で“できる人”だとわかる。
「私は吉原。秘書課の主任をしているわ。今日からよろしくね」
柔らかい笑みとは裏腹に、その視線は冷静で、私の立ち姿から靴の先までを一瞬で見定めていた。まるで、試されているような気分だった。
「とりあえず、あなたの席を案内するわ。机の整理もお願いね。それから、後で書類の補充も頼むことになると思うから、備品の場所も覚えておいて」
はい、と返事をしながら必死に歩調を合わせた。どんなに緊張しても、ここで食らいつかなければならない。
案内されたデスクのあるエリアには、すでに数名の女性たちが座っていた。私より少し年上に見える人もいれば、落ち着いた雰囲気のベテランらしき人もいる。ちらりとこちらを見た彼女たちの視線が一瞬で交差し、すぐにヒソヒソとした会話が始まった。
「……この子が新人?」 「また秘書課に?今年で何人目?」
明らかにこちらを見ながら交わされる小声。それでも笑顔を崩さず、私は空いたデスクにバッグを置いた。座ると、背中に張りついていた汗が一層冷たくなった気がした。
慣れない椅子の高さを調整しながら、私は呼吸を整える。目の前のパソコンを起動させる手もぎこちない。キーボードを打つたびに指がかすかに震える。自分がどこに何をしまうべきなのか、それすらわからない。
「そうそう、言い忘れてたけど」
吉原主任がふと声をかけてきた。
「あなたの担当は専務だから。あとでご挨拶に行くからね」
一瞬、意味が飲み込めなかった。
「……専務、ですか?」
聞き返した声が思わず裏返ってしまった。主任は口元だけで笑いながら、肩をすくめてみせた。
「そう。専務。直々に“新人を担当につけてくれ”って依頼が来たのよ。不思議よね」
専務。つまり、この会社の中でも社長に次ぐポジション。まさか自分のような新米が、そんな重要なポジションの秘書になるなんて。
「がんばってね。あの人、厳しいけど、実力は本物だから。……まあ、泣かされないように気をつけて」
主任の言葉が冗談なのか本気なのかわからず、私はただ苦笑いするしかなかった。
(やっていけるんだろうか、私に)
初日から圧倒されることばかりの環境。だけど、ここが私のスタート地点。もう後戻りはできない。
深呼吸をして、私はパソコンの画面を見つめ直した。震える手を握りしめる。不安は尽きないけれど、それでも前に進まなければ。
今はまだ、知らない。この日、配属されたことが――私の運命を大きく揺るがす始まりになることを。
口に出してみても、実感は湧かなかった。手にした社員証の角が、指先にひりつく。春の朝。緊張で早く目が覚めてしまった私は、指定されたオフィスビルの前でしばらく深呼吸を繰り返していた。
背筋を伸ばして見上げる高層ビル。その無機質なガラス張りの建物は、まるでこれから私が飛び込もうとしている社会そのものを象徴しているようで、言葉にはできない不安が胸の奥からじんわりと広がっていく。
私は大学を卒業したばかりの新入社員。就職活動中には「自分の強みは行動力です!」なんてキラキラした目で言っていたけれど、いざ本当に入社となると、足元がぐらつくような心許なさばかりが募る。
受付で名前と配属先を告げると、社員証とフロアマップが手渡された。
「秘書課は11階になります。こちらのエレベーターをご利用ください」
静かな声とともに差し出されたカードを握りしめ、案内されたエレベーターに乗り込む。上昇するたびに耳がツンとし、胸の奥がざわついた。
(なんで秘書課なんだろう)
正直に言えば、私は秘書志望ではなかった。学生時代、部活動やゼミで人をまとめる役目をしていたせいか、最終面接の際には「総合職として現場にも出てみたいです」と意欲を語った。まさか配属通知で『秘書課』と告げられるとは思わなかった。
秘書――それはどこか遠い存在のように感じていた。上司のスケジュールを管理し、会議の準備をし、常に誰かの“後ろ”にいる職業。自分とはあまり縁のない仕事だと勝手に思っていた。でも、そんな私が、今まさにその世界に足を踏み入れようとしている。
エレベーターの扉が静かに開いた瞬間、空気が変わった。
磨き上げられたフロアの床、淡いベージュで統一された内装。静けさの中に、靴音だけが控えめに響いていた。どこか背筋が伸びるような緊張感に包まれている。社員たちはみな穏やかな表情で業務にあたっているように見えるけれど、その内側にピンと張り詰めた糸のようなものを感じた。
案内されたのは、奥まった一角にある秘書課のエリアだった。
「失礼します。本日より配属されました、新入社員の――」
声が震えないように気をつけたつもりだったが、挨拶を終えると喉がからからになっていることに気づいた。緊張で背中にはじんわり汗が滲んでいる。
「あなたが、新しく来た子?」
奥から近づいてきたのは、タイトなスカートに身を包んだ、三十代前半ほどの女性だった。巻いた髪をゆるくまとめていて、きりりとした目元が印象的。化粧は控えめだけれど、洗練された雰囲気があり、一目で“できる人”だとわかる。
「私は吉原。秘書課の主任をしているわ。今日からよろしくね」
柔らかい笑みとは裏腹に、その視線は冷静で、私の立ち姿から靴の先までを一瞬で見定めていた。まるで、試されているような気分だった。
「とりあえず、あなたの席を案内するわ。机の整理もお願いね。それから、後で書類の補充も頼むことになると思うから、備品の場所も覚えておいて」
はい、と返事をしながら必死に歩調を合わせた。どんなに緊張しても、ここで食らいつかなければならない。
案内されたデスクのあるエリアには、すでに数名の女性たちが座っていた。私より少し年上に見える人もいれば、落ち着いた雰囲気のベテランらしき人もいる。ちらりとこちらを見た彼女たちの視線が一瞬で交差し、すぐにヒソヒソとした会話が始まった。
「……この子が新人?」 「また秘書課に?今年で何人目?」
明らかにこちらを見ながら交わされる小声。それでも笑顔を崩さず、私は空いたデスクにバッグを置いた。座ると、背中に張りついていた汗が一層冷たくなった気がした。
慣れない椅子の高さを調整しながら、私は呼吸を整える。目の前のパソコンを起動させる手もぎこちない。キーボードを打つたびに指がかすかに震える。自分がどこに何をしまうべきなのか、それすらわからない。
「そうそう、言い忘れてたけど」
吉原主任がふと声をかけてきた。
「あなたの担当は専務だから。あとでご挨拶に行くからね」
一瞬、意味が飲み込めなかった。
「……専務、ですか?」
聞き返した声が思わず裏返ってしまった。主任は口元だけで笑いながら、肩をすくめてみせた。
「そう。専務。直々に“新人を担当につけてくれ”って依頼が来たのよ。不思議よね」
専務。つまり、この会社の中でも社長に次ぐポジション。まさか自分のような新米が、そんな重要なポジションの秘書になるなんて。
「がんばってね。あの人、厳しいけど、実力は本物だから。……まあ、泣かされないように気をつけて」
主任の言葉が冗談なのか本気なのかわからず、私はただ苦笑いするしかなかった。
(やっていけるんだろうか、私に)
初日から圧倒されることばかりの環境。だけど、ここが私のスタート地点。もう後戻りはできない。
深呼吸をして、私はパソコンの画面を見つめ直した。震える手を握りしめる。不安は尽きないけれど、それでも前に進まなければ。
今はまだ、知らない。この日、配属されたことが――私の運命を大きく揺るがす始まりになることを。