それから二日は身の入らないまま花売りを続けていた所為か、売れる物も売れず、夕刻親方に呼び出されたイレーネはこっぴどく叱られて、長い時間を無駄に過ごすことになった。
──あのくそオヤジ、親方じゃなかったら、あのぶよぶよの頬を十本の爪で引っ掻いてやるんだから!
売れ残った花が入ったままの籠は、いつになく重く感じられる。誰もいなくなった暗い港を、とぼとぼと家路に向かっていた彼女の前に、白い揺らめきがさっと掠めた──何処からか走り来たアメルであった。
「あ、アメル!」
「え……?」
立ち止まって振り向いたその顔は、少し焦った様子で息も荒い。それでも呼吸を整えた彼は、いつもの笑顔を取り戻して、
「えっと、イレーネだよね? カ、カリメーラ?」
そんな挨拶に少女はプッと吹き出した。
「それは『おはよう』よ。今は『カリスベラ』」
「ああ、そっか……ごめん」
そう教授すると、アメルもまた同じように笑った。
「もしかして、そこの酒場から逃げ出してきたの? 左耳の手前、口紅付いてる」
「え! 参ったな……これだから酒場は苦手だよ」
慌てて手の甲で紅いそれを拭ったアメルは、困ったような笑みを見せた。彼の白いシャツからは微かに百合の香水が匂っていた。
「ねぇ、その香り……誘ってきたのはレリアなんじゃない? まさかこの街一番の美女を振ってきたの?」
「ん? そんな名前だったかな……。いや……きっと、からかわれたんだよ」
爽やかなアメルの返答に、イレーネは目を見開かせてしまった。
──違う……アメルの外見はレリアの好きなタイプだ。きっと彼女は本気だったのに、それを振り切ってきただなんて──。
既に三十路となった母親はとっくに一線を退いたが、そのクロエの再来と称えられ、酒場の二階を占めた娼館の中でも飛びきりの美女だというのに、その彼女ですら──彼の心はともかくとして──肉体も得られなかったとは、レリアのプライドは相当傷ついたことだろう。
イレーネは心の中で苦笑してみせたが、どうせ寝取られるのならプロの方がマシね、と変に冷めた嗤いも起こしていた。
「あなた、自分の魅力にちっとも気付いてないのね。どうしてそんなに真っ直ぐでいられるの?」
「え?」
「……ううん、何でもない。ね、少し話せる?」
二人はアメル達の船のすぐ横で、海を目前に腰を降ろした。
星明りに照らされた紺色の海を、柔らかな眼差しで見つめるすっとした横顔を見て、少女は手の届かない現実に我が身を憂いた。
自分の周りには、美しい母親に媚を売るいやらしい男達しかいなかったのだ。なのにジョルジョの瞳もアメルのそれも、いつ会えるとも知れない愛しい女性しか映していなかった。そんなことってあるのだろうか? この二人が特別なだけなのか? 余りにすさんだ環境に、彼らは自分には眩し過ぎると思えてならなかった。
「ねぇ……忘れることはないの?」
「?」
アメルの「何?」と問いかける瞳が少女へと振り向いた。
「船長の娘さんを、忘れることはないの?」
「あ……聞いたの?」
一瞬驚きというよりも気まずさを隠せないといった様相を見せたが、すぐに平静を取り戻したアメルは、
「うん」
間髪容れず、はっきりと頷いてみせた。
正直過ぎる彼に少し意地悪をしてみたくなったイレーネは、つい口走っていた。
「忘れちゃいなさいよ」
「え?」
──わたしが忘れさせてあげるわ。
よっぽどそんな大胆な言葉で、目の前の青年がうろたえる姿を見てみたかったが、どうせ不発に終わることは目に見えていると、心に言い聞かせてぐっとこらえる。
「このまま待ってたらお爺さんになっちゃうわよ?」
「そうだね……でも僕は彼女のカケラを手に入れたし、彼女は僕の心の一部を持ち去ってしまったから──」
アメルは胸元に手をやって微笑んだ。
──彼女のカケラ? それがそのポケットに入っているの?
「心の一部を持ち去られただなんて、随分ロマンティックなこと言うのね」
そんなに想われている彼女が、どれだけ羨ましいか知れなかった。
「ちょっと気障だったかな……」
目を細めて笑うアメル。けれど向けた先のイレーネの表情が淋しそうなことに気付いて、咄嗟に思いついたことに話を変えていた。
「……イレーネって名前、何か意味があるの?」
自分に少しでも興味を持たれたことに、思わず喜びを感じてしまう。けれど、
「『平和』……つまらない名前だわ」
まったく面白味のない返答しか出来ないことが、知らず溜息をつかせていた。膝を抱えて顎を乗せ、口を尖らせ目を伏せる。
「そんなことないよ。とても素敵な名前だと思う」
アメルの言葉に嘘はないことが窺えて、少し元気を取り戻したイレーネは、何となく続きを話し出した。
「『一応父親』だって人がつけてくれたの。あなたと同じ船乗りよ。小さい頃はこの島に立ち寄る度会いに来てくれたけど、母さんがいつも違う男性と一緒にいるのに呆れて、いつの間にか来なくなっちゃったわ」
皮肉めいた言葉と共に、それが表情に表れたことを自分でも気付いていた。でも……その通りの話だ。
「また……会えるといいね」
「え?」
温かな声に、勢い良く顔を向けた。アメルはイレーネが想像したままの心ある瞳で見つめていて、刹那彼女は頬の熱を感じた。
「僕の名前も父さんがつけてくれた。僕の父さんも船乗りだったんだ」
「だったって……?」
語尾の過去形が気になって尋ねてしまう。
「僕が十歳の時に、海の嵐で亡くなったから」
「そうだったの……あっ、お母さんは元気なんでしょ?」
「最近は随分元気になってきたけど、ずっと病院にいるよ」
「……」
アメルの面は微塵も辛いことなど示していなかったが、訊いてはいけないことに触れてしまった気がして、イレーネは少し焦りを見せた。──この人も寂しい想いや、沢山の苦労をしてきたんだ──そう思えば自分の吐いた愚痴など、どれだけ小さなことか知れない。
「そういえば……船長の娘さんは何ていうの?」
ふと話を元へ戻されたことに、アメルは一瞬動揺の色を見せた。
「……ルーラ、だよ」
久し振りに声に出したその愛しい名に、彼の視線は照れたように海の遠くへ向けられ、発した唇は笑みを刻んでいた。
「ルーラ」
イレーネもまた思い出す。船長と再会した時に彼から聞かされた名だ。
「彼女の名前にも意味があるの?」
「うん……ジョルジョの『ル』に、お母さんの名──テラの『ラ』」
アメルはそう言って、その名の由来を知ったあの嵐のやんだ朝に身を置いていた。あれこそ『運命』だったのだと思う。結界の外に出たその晩に、父親と再会するなんて──自分もまた自己の持つ『運命』が、ルーラの許へと導いてくれるだろうか? いや、待つんじゃない。『運命』とは、自身で手繰り寄せるものなのかもしれない──。
「綺麗な名前ね」
穏やかさを取り戻したイレーネの言葉に、アメルも同意するように視線を戻した。
「ルーラのお母さんも、彼女が二歳になる前に病気で亡くなったんだ。だから……船長は、愛する人に会えなかった──」
「えっ!?」
イレーネは、娘がいると聞かされたあの朝よりも驚いていた。ジョルジョはテラのことを、顔を真っ赤にして語ったのだ。あれは今でも恋をしている顔だった。まさかその相手が死んでいるだなんて──。
「ジョルジョ船長も、そのことは知っているのよね?」
「もちろん。再会出来た次の朝には、ルーラが話したから……」
──何て人なんだ──。
一年も前に恋人の死を知らされたのに、再会したジョルジョは何も変わっていなかった。十六年愛し続けた気持ちとは、そんなに揺るがないものなのだろうか? そしてこの世にいなくても、愛し続けられるものなのだろうか──?
「あなた達って……本当におめでたいわね」
普通であったら怒りを覚えそうなその返答に、それでもアメルは笑ってみせた。そう呟いて笑いをこらえるイレーネの目からは、愛情溢れる涙が零れ落ちていたから。
「……そうかもしれないね」
アメルの返事を最後に、しばらく二人は言葉を交わさなかった。ただ海を見つめて、波の音を聞いていた。
「わたし、前言撤回するわ」
それでも十分も経たない内にぽつりと一言、イレーネが口を開いた。
「忘れちゃいなさいよって言ったこと。……忘れなくていいわ。きっと会える日が……きっと来るから」
「ありがとう、イレーネ」
繰り返された「きっと」に、背中を押された気がして、アメルの顔に満面の笑みが戻る。
「これ……売れ残りで悪いけど、あなたにあげるわ。はなむけよ」
自分の隣に置いた花籠から残り全ての花を取り、少女は青年に差し出してみせた。
「えっ……? いや、こんなに悪いよ! あ、僕こそ今夜のお礼に買うから」
「それじゃ意味がないじゃない。はなむけだって言ってるのに」
「でも……」
「んー!」
強引に受け取らせ、すっきりとした気持ちを表す。白い釣鐘型の花を沢山つけたその花束を、アメルは大事そうに抱えてお礼を言った。
「カンパニュラっていうの。あなたにピッタリの花だわ。その花言葉『誠実な恋』だから」
「誠実な……」
胸の中で咲き誇るカンパニュラを見下ろしたアメルは、ある考えが閃いて、パッと彼女の許へ顔を上げた。嬉しそうな瞳──何だろうと少女は首を傾げた。
「これ、明日の航海で海に流してもいい?」
「もちろん、もうあなたの物なんだから、どうしてくれてもいいわ。それまで水に差しておけば、少しは花も保つ筈よ」
「一輪くらいは、届くかもしれないね」
「え?」
「ありがとう、イレーネ」
もう一度お礼を言ってアメルは立ち上がり、イレーネもまたその後に続いた。
「夜道は危ないから送るよ」
「いいわ、うちすぐそこだから」
そんなこと、何だかこそばゆくてと感じて、つい嘘をついた。それにこれ以上一緒にいたら、抱きついて「行かないで!」と駄々を捏ねてしまいそうな悪い虫が、現れないとも限らない。
「それじゃ……」
胸の前に出されたすらりとした手に、彼女は少しはにかみながらも応じて、温かな握手を交わした。
「えっと……ヘレテ?」
「合ってるわよ。アディオでも構わないけど」
再び笑顔を見合わせ、アメルは背中を向けてゆっくりと歩き出す。
「あーあっ」
彼の後ろ姿が闇に消えて、やっと逆方向に身を返したイレーネは大きく息を吐いた。
──振ってくれた相手を応援しちゃうなんて……よっぽどわたしの方がおめでたいわね。
それでも進めた足取りは軽く感じられた。胸の奥が温かくなって、晴れ晴れとした気持ちも存在する。
暗く沈んだ海岸を独り、空の花籠を振り回しスキップしながら、イレーネは今度父親が港に現れたら、会ってみようと心に決めていた。
生きている限り、きっと会えるのだから──。
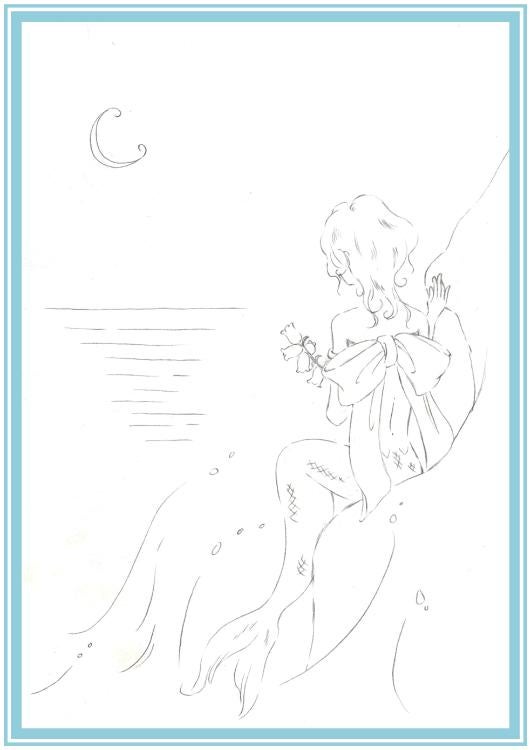
◆ 今作はアメル視点ではない「アメルを見詰める瞳」を描きたいと思って書きました* ルーラと再会するまでには、彼にも女泣かせな部分があっても良いのではないかと思いまして(笑)。
しかし・・・サファラグの一人称「僕」萌えw小説ばかり書いていた所為で、数年振りの三人称小説は厳しかった(涙)。
最終部の会話が少々長いのはご了承ください(汗)。アメルの父とテラが亡くなっている事がイレーネに伝わらないと、結末に持って行けなかったものですから(大汗)。
最後まで有難うございます! 次の物語にも是非お進みください♡
──あのくそオヤジ、親方じゃなかったら、あのぶよぶよの頬を十本の爪で引っ掻いてやるんだから!
売れ残った花が入ったままの籠は、いつになく重く感じられる。誰もいなくなった暗い港を、とぼとぼと家路に向かっていた彼女の前に、白い揺らめきがさっと掠めた──何処からか走り来たアメルであった。
「あ、アメル!」
「え……?」
立ち止まって振り向いたその顔は、少し焦った様子で息も荒い。それでも呼吸を整えた彼は、いつもの笑顔を取り戻して、
「えっと、イレーネだよね? カ、カリメーラ?」
そんな挨拶に少女はプッと吹き出した。
「それは『おはよう』よ。今は『カリスベラ』」
「ああ、そっか……ごめん」
そう教授すると、アメルもまた同じように笑った。
「もしかして、そこの酒場から逃げ出してきたの? 左耳の手前、口紅付いてる」
「え! 参ったな……これだから酒場は苦手だよ」
慌てて手の甲で紅いそれを拭ったアメルは、困ったような笑みを見せた。彼の白いシャツからは微かに百合の香水が匂っていた。
「ねぇ、その香り……誘ってきたのはレリアなんじゃない? まさかこの街一番の美女を振ってきたの?」
「ん? そんな名前だったかな……。いや……きっと、からかわれたんだよ」
爽やかなアメルの返答に、イレーネは目を見開かせてしまった。
──違う……アメルの外見はレリアの好きなタイプだ。きっと彼女は本気だったのに、それを振り切ってきただなんて──。
既に三十路となった母親はとっくに一線を退いたが、そのクロエの再来と称えられ、酒場の二階を占めた娼館の中でも飛びきりの美女だというのに、その彼女ですら──彼の心はともかくとして──肉体も得られなかったとは、レリアのプライドは相当傷ついたことだろう。
イレーネは心の中で苦笑してみせたが、どうせ寝取られるのならプロの方がマシね、と変に冷めた嗤いも起こしていた。
「あなた、自分の魅力にちっとも気付いてないのね。どうしてそんなに真っ直ぐでいられるの?」
「え?」
「……ううん、何でもない。ね、少し話せる?」
二人はアメル達の船のすぐ横で、海を目前に腰を降ろした。
星明りに照らされた紺色の海を、柔らかな眼差しで見つめるすっとした横顔を見て、少女は手の届かない現実に我が身を憂いた。
自分の周りには、美しい母親に媚を売るいやらしい男達しかいなかったのだ。なのにジョルジョの瞳もアメルのそれも、いつ会えるとも知れない愛しい女性しか映していなかった。そんなことってあるのだろうか? この二人が特別なだけなのか? 余りにすさんだ環境に、彼らは自分には眩し過ぎると思えてならなかった。
「ねぇ……忘れることはないの?」
「?」
アメルの「何?」と問いかける瞳が少女へと振り向いた。
「船長の娘さんを、忘れることはないの?」
「あ……聞いたの?」
一瞬驚きというよりも気まずさを隠せないといった様相を見せたが、すぐに平静を取り戻したアメルは、
「うん」
間髪容れず、はっきりと頷いてみせた。
正直過ぎる彼に少し意地悪をしてみたくなったイレーネは、つい口走っていた。
「忘れちゃいなさいよ」
「え?」
──わたしが忘れさせてあげるわ。
よっぽどそんな大胆な言葉で、目の前の青年がうろたえる姿を見てみたかったが、どうせ不発に終わることは目に見えていると、心に言い聞かせてぐっとこらえる。
「このまま待ってたらお爺さんになっちゃうわよ?」
「そうだね……でも僕は彼女のカケラを手に入れたし、彼女は僕の心の一部を持ち去ってしまったから──」
アメルは胸元に手をやって微笑んだ。
──彼女のカケラ? それがそのポケットに入っているの?
「心の一部を持ち去られただなんて、随分ロマンティックなこと言うのね」
そんなに想われている彼女が、どれだけ羨ましいか知れなかった。
「ちょっと気障だったかな……」
目を細めて笑うアメル。けれど向けた先のイレーネの表情が淋しそうなことに気付いて、咄嗟に思いついたことに話を変えていた。
「……イレーネって名前、何か意味があるの?」
自分に少しでも興味を持たれたことに、思わず喜びを感じてしまう。けれど、
「『平和』……つまらない名前だわ」
まったく面白味のない返答しか出来ないことが、知らず溜息をつかせていた。膝を抱えて顎を乗せ、口を尖らせ目を伏せる。
「そんなことないよ。とても素敵な名前だと思う」
アメルの言葉に嘘はないことが窺えて、少し元気を取り戻したイレーネは、何となく続きを話し出した。
「『一応父親』だって人がつけてくれたの。あなたと同じ船乗りよ。小さい頃はこの島に立ち寄る度会いに来てくれたけど、母さんがいつも違う男性と一緒にいるのに呆れて、いつの間にか来なくなっちゃったわ」
皮肉めいた言葉と共に、それが表情に表れたことを自分でも気付いていた。でも……その通りの話だ。
「また……会えるといいね」
「え?」
温かな声に、勢い良く顔を向けた。アメルはイレーネが想像したままの心ある瞳で見つめていて、刹那彼女は頬の熱を感じた。
「僕の名前も父さんがつけてくれた。僕の父さんも船乗りだったんだ」
「だったって……?」
語尾の過去形が気になって尋ねてしまう。
「僕が十歳の時に、海の嵐で亡くなったから」
「そうだったの……あっ、お母さんは元気なんでしょ?」
「最近は随分元気になってきたけど、ずっと病院にいるよ」
「……」
アメルの面は微塵も辛いことなど示していなかったが、訊いてはいけないことに触れてしまった気がして、イレーネは少し焦りを見せた。──この人も寂しい想いや、沢山の苦労をしてきたんだ──そう思えば自分の吐いた愚痴など、どれだけ小さなことか知れない。
「そういえば……船長の娘さんは何ていうの?」
ふと話を元へ戻されたことに、アメルは一瞬動揺の色を見せた。
「……ルーラ、だよ」
久し振りに声に出したその愛しい名に、彼の視線は照れたように海の遠くへ向けられ、発した唇は笑みを刻んでいた。
「ルーラ」
イレーネもまた思い出す。船長と再会した時に彼から聞かされた名だ。
「彼女の名前にも意味があるの?」
「うん……ジョルジョの『ル』に、お母さんの名──テラの『ラ』」
アメルはそう言って、その名の由来を知ったあの嵐のやんだ朝に身を置いていた。あれこそ『運命』だったのだと思う。結界の外に出たその晩に、父親と再会するなんて──自分もまた自己の持つ『運命』が、ルーラの許へと導いてくれるだろうか? いや、待つんじゃない。『運命』とは、自身で手繰り寄せるものなのかもしれない──。
「綺麗な名前ね」
穏やかさを取り戻したイレーネの言葉に、アメルも同意するように視線を戻した。
「ルーラのお母さんも、彼女が二歳になる前に病気で亡くなったんだ。だから……船長は、愛する人に会えなかった──」
「えっ!?」
イレーネは、娘がいると聞かされたあの朝よりも驚いていた。ジョルジョはテラのことを、顔を真っ赤にして語ったのだ。あれは今でも恋をしている顔だった。まさかその相手が死んでいるだなんて──。
「ジョルジョ船長も、そのことは知っているのよね?」
「もちろん。再会出来た次の朝には、ルーラが話したから……」
──何て人なんだ──。
一年も前に恋人の死を知らされたのに、再会したジョルジョは何も変わっていなかった。十六年愛し続けた気持ちとは、そんなに揺るがないものなのだろうか? そしてこの世にいなくても、愛し続けられるものなのだろうか──?
「あなた達って……本当におめでたいわね」
普通であったら怒りを覚えそうなその返答に、それでもアメルは笑ってみせた。そう呟いて笑いをこらえるイレーネの目からは、愛情溢れる涙が零れ落ちていたから。
「……そうかもしれないね」
アメルの返事を最後に、しばらく二人は言葉を交わさなかった。ただ海を見つめて、波の音を聞いていた。
「わたし、前言撤回するわ」
それでも十分も経たない内にぽつりと一言、イレーネが口を開いた。
「忘れちゃいなさいよって言ったこと。……忘れなくていいわ。きっと会える日が……きっと来るから」
「ありがとう、イレーネ」
繰り返された「きっと」に、背中を押された気がして、アメルの顔に満面の笑みが戻る。
「これ……売れ残りで悪いけど、あなたにあげるわ。はなむけよ」
自分の隣に置いた花籠から残り全ての花を取り、少女は青年に差し出してみせた。
「えっ……? いや、こんなに悪いよ! あ、僕こそ今夜のお礼に買うから」
「それじゃ意味がないじゃない。はなむけだって言ってるのに」
「でも……」
「んー!」
強引に受け取らせ、すっきりとした気持ちを表す。白い釣鐘型の花を沢山つけたその花束を、アメルは大事そうに抱えてお礼を言った。
「カンパニュラっていうの。あなたにピッタリの花だわ。その花言葉『誠実な恋』だから」
「誠実な……」
胸の中で咲き誇るカンパニュラを見下ろしたアメルは、ある考えが閃いて、パッと彼女の許へ顔を上げた。嬉しそうな瞳──何だろうと少女は首を傾げた。
「これ、明日の航海で海に流してもいい?」
「もちろん、もうあなたの物なんだから、どうしてくれてもいいわ。それまで水に差しておけば、少しは花も保つ筈よ」
「一輪くらいは、届くかもしれないね」
「え?」
「ありがとう、イレーネ」
もう一度お礼を言ってアメルは立ち上がり、イレーネもまたその後に続いた。
「夜道は危ないから送るよ」
「いいわ、うちすぐそこだから」
そんなこと、何だかこそばゆくてと感じて、つい嘘をついた。それにこれ以上一緒にいたら、抱きついて「行かないで!」と駄々を捏ねてしまいそうな悪い虫が、現れないとも限らない。
「それじゃ……」
胸の前に出されたすらりとした手に、彼女は少しはにかみながらも応じて、温かな握手を交わした。
「えっと……ヘレテ?」
「合ってるわよ。アディオでも構わないけど」
再び笑顔を見合わせ、アメルは背中を向けてゆっくりと歩き出す。
「あーあっ」
彼の後ろ姿が闇に消えて、やっと逆方向に身を返したイレーネは大きく息を吐いた。
──振ってくれた相手を応援しちゃうなんて……よっぽどわたしの方がおめでたいわね。
それでも進めた足取りは軽く感じられた。胸の奥が温かくなって、晴れ晴れとした気持ちも存在する。
暗く沈んだ海岸を独り、空の花籠を振り回しスキップしながら、イレーネは今度父親が港に現れたら、会ってみようと心に決めていた。
生きている限り、きっと会えるのだから──。
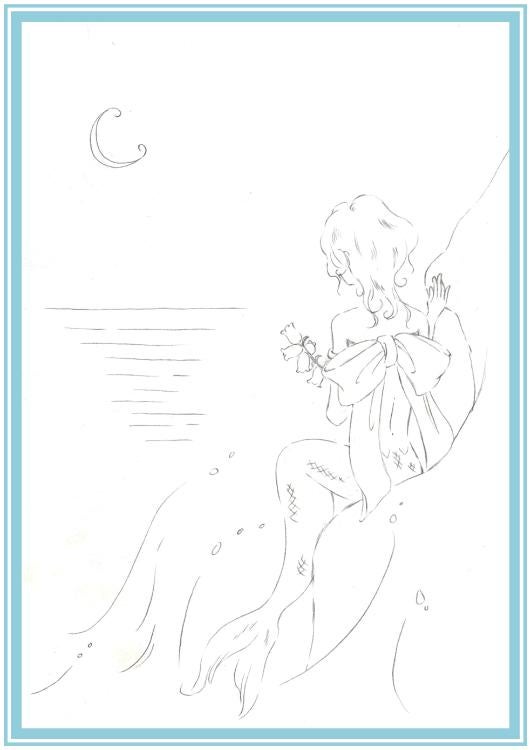
◆ 今作はアメル視点ではない「アメルを見詰める瞳」を描きたいと思って書きました* ルーラと再会するまでには、彼にも女泣かせな部分があっても良いのではないかと思いまして(笑)。
しかし・・・サファラグの一人称「僕」萌えw小説ばかり書いていた所為で、数年振りの三人称小説は厳しかった(涙)。
最終部の会話が少々長いのはご了承ください(汗)。アメルの父とテラが亡くなっている事がイレーネに伝わらないと、結末に持って行けなかったものですから(大汗)。
最後まで有難うございます! 次の物語にも是非お進みください♡
 | 野いちご](https://www.no-ichigo.jp/assets/1.0.787/img/logo.svg)




![月とガーネット[下]](https://www.no-ichigo.jp/img/member/1247997/zcrelg1uqj-thumb.jpg)