──冷たい。
僕は頬を濡らす雫の感覚で目を覚ました。
瞼をゆっくりと持ち上げる。視界はぼやけているのか、明るさだけは理解したが、はっきりとした物の輪郭は見つけられない。横倒しになっているらしく、逆の頬にさらさらとした砂の粒子を感じる──砂浜? 僕達はラグーンへ辿り着くことなく、何処かへ打ち上げられてしまったのだろうか?
「……ア……メル……」
──ルーラ?
背後から呻くような僕を呼ぶ声が聞こえた。
重い身体を引きずり反対方向へ向きを変える。繋いだ手の先に砂にまみれたルーラの姿があった。一粒一粒が辺りの光を吸い込み、ルーラはまるで細かなダイヤを散りばめているようだ。
「ルーラ……大丈夫?」
僕はだるそうに起き上がって、彼女の髪と頬の砂を優しく指の腹で払った。眩しそうな顔をしてルーラも半身を起こした。
「うん……ここ、どこかしら? ラグーンの中?」
ルーラの鱗を小さな波が濡らしていた。そういった近くの物は何とか判別がつくが、遠くを見渡そうとしても、まるで世界を包み込むようなまばゆい明るさに邪魔されて目を覆いたくなる。
「父様達、無事かしら……」
座り込んだルーラの呟きにつぶさに、
──船は無事じゃよ。
天上から見知らぬ声が答えてきたので上空を見上げ、僕達はあっと声を上げた。
「頭の上に、海がある……?」
立ち上がって背伸びをすれば届きそうな位置に、まるで世界をひっくり返したように『海』が存在していた。その表面は穏やかな波を立て、時々発生した水しぶきが僕達に降りかかってくる。
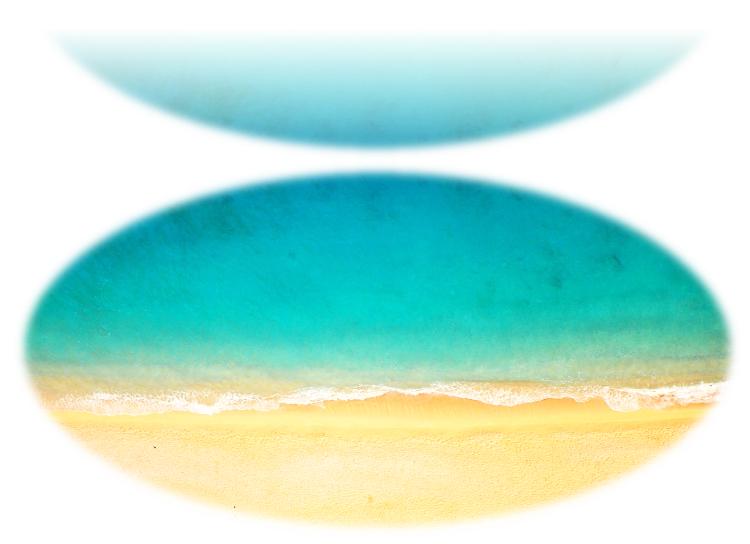
「アーラ……様? アーラ様ですか?」
ルーラはハッとしてその海へと叫んだ。もし声の主がアーラ様ならば。此処はサファイア・ラグーンということになる。
「そうじゃよ」
天上を見つめて答えを待つ僕達へ、意外なことにその声は背後から聞こえ、二人同時に振り返った。砂浜の延長上に広がる──つまりルーラの鱗を濡らす波の先の海面すれすれに、白いローブの小じんまりした姿が浮かんでいた。
「ようこそ、サファイア・ラグーンへ……ルーラ、アメリゴ……いや、そなた幼少から両親より呼ばれた愛称を好むのだったな。ようこそ、アメル」
深く被ったフードの端から見え隠れする、皺の寄った口角が少々吊り上った。何故だ? ルーラにも話していないことをこの人は知っている。
「あたし達が来るのを、ご存知だったのですか?」
自分の名を呼ばれたことに驚いたルーラは、僕と顔を見合わせアーラ様へと問うた。
「まあな……手荒い招きで失礼したが。許せ……此処は本来生きた者の来られぬ場所。色々訊きたいことも有ろうが、少し休みなさい。朝食も未だじゃろう」
そう言ってアーラ様は、ローブの袖から指先だけを出し手招きした。
僕達は再び目を合わせ、彼女の許へ向かった。ルーラと手を繋ごうとして手を伸ばしたが、そうせずとも既に空気の膜が出来ていることに気付かされる。刹那アーラ様は少し振り向いて、
「いつまでもそれでは不便じゃろ? いや……その方がそなたには良いのかな、アメル」
にんまりとした口元に、僕は頬を赤くして俯いた。ルーラは不思議そうに僕を横から見上げたが、音もなく海へと沈んでいくアーラ様を追ってスイスイと泳ぎ、僕は不恰好に手足をバタつかせて彼女達へと続いた。
海底は緩やかな傾斜で、先に進むほど深さが増し、青のグラデーションは次第に黒へと変化していった。海岸からずっと砂の地面が続いているが、両腕の幅程度で一直線に伸び、ラグーンと呼ばれる通り両端には珊瑚礁が広がっている。
やがて正面にぼんやりと白く光る空間が現れ、ドーム状の薄い膜で覆われたその中は、水中とも空中とも言い難い不思議な世界だった。入口もなく急に其処へと切り替わり、僕を包む空気の層は失ってはいないものの視覚的には消え、しかもルーラは普通に泳ぎ回ることが出来た。
「まぁ、座りなさい」
アーラ様は中央にしつらえた白い丸テーブルと簡素な三脚の椅子へ僕達を誘い、促すように自ら腰をかけた。まるで予見していたように用意された調度──いや、アーラ様は僕達が来ることを知っていたと言った。
とにかく家主たるこの魔法使いに従うことしか出来ない今、返事もそこそこにその言葉に応じたが、一体これからどうなるというのだろう。右隣に腰かけたルーラの横顔も僕と同じ緊張した面持ちで、アーラ様の次の句を待っている。
すると喉の奥からくっくと笑って、小さな背中を揺らしたアーラ様は、
「おかしな二人じゃのう……望んで来たのはお主等じゃろう? 何を怖がる? 誰も取って食おうなどと思っておらぬのじゃから落ち着きなされ。それより朝から何も食べぬまま、もうお昼じゃぞ。毒など入れておらぬから、ささ、召し上がれ」
そう言って伸ばしたしわくちゃの手の先を見たが、いつの間にかテーブルの上には大そうなご馳走が並んでいた。
この世の物とは思えない良い匂い──その途端ルーラと僕は、胃が活発に動き出すのを感じて思わずお腹を押さえた。どちらともなく恐る恐る食事に手を伸ばしたが、あまりの美味しさに気が付けば無我夢中で大半を食べ終えていた。
「ごっ、ごちそう様でした……」
突如として現れた飲み物らしきカップに口をつけ、僕はそう言いホッと息を吐いた。じっと石のように動かず、やっと見える口元に微笑みを湛えて見守っていたアーラ様は、少し間を置いて満足そうに「うむ」と頷き、
「ようやく落ち着いたかの……まぁ、また落ち着いている場合ではなくなるじゃろが……」
言い終わらぬ内にフードに手を掛け、ゆっくりとこちらへ向けられた姿は、声も出なくなるほどに驚きの、あの懐かしい人物のものであった。
「おっ……大ばば様!」
僕達は思わず立ち上がって叫んでいた。
そう……ずっと気になっていた白いローブ。この声、この背丈。皺だらけの肌。全てが似ていた、大ばば様に。──似ていた?
「大ばば様! 生きていたのね……良かった! 大ばば様……」
ルーラは既にアーラと名乗った老婆に抱きつき、泣いて再会を喜んでいた。優しく髪を撫でるアーラ様、しかし、
「ほぉ……やはりそんなに似ているかの。昔も双子のように瓜二つであったが……歳をとっても変わらぬのだから、血の繋がりとは強きものじゃ」
ハッとして動きを止めた僕達に、にっこりと微笑んだアーラ様のその表情は、確かにちょっと違うニュアンスを持っているように思えた。
そうだ、微妙に声色も高い……初めに聞いた時、見知らぬ声と感じたのもその所為だ。それなのにこの姿・装いに、僕らは大ばば様であってほしい・生きていてほしいという願望からか、幻を見ていたのかもしれない。
「大ばば……様じゃない?」
しがみついた腕そのままに、ルーラはじっとアーラ様を見つめた。大ばば様でないと気付いた彼女の表情の変化は、少し離れて立ち尽くす僕にさえも見て取れた。
「我はウイスタの姉……たった一つ違いじゃがの」
涙を溜めたまま驚きを隠せず沈黙するルーラに、アーラ様は再びニッと笑って彼女の首元に手をやった。
「懐かしいのぉ……ウィズの石。百五十年振りじゃろか。これもまたそなたの物と同様、母親の涙じゃ……我とウイスタの母親。父親の涙までは交じっておらぬがの」
そっとウィズの石に触れた途端、再びあのオレンジ色の光が、ぼぉっとアーラ様の身体を包み込んだ──まるで再会を喜ぶように──大ばば様が……それとも二人の母親だろうか?
「あの……アーラ様」
「何じゃ? 我も“ばば”で良いぞ、ルーラ」
涙を拭いて席に戻ったルーラに、アーラ様はほほっと笑っておどけて答えた。
「何故結界の皆はあたしに、石は深海で採れると嘘をついたのですか?」
僕も気を取り直して椅子に腰かけた。アーラ様はこれまでの調子を崩さず、穏やかな表情でルーラを見つめ説明を始めた。
「誰も嘘はついておらぬよ……ただ知らなかっただけじゃ。あの結界の中で唯一知っていたのはウイスタのみ──厳密に言えばウイスタは嘘をついたのかもしれぬな……あれがもし生きていたら、訊かれぬから答えなかったのだと言い訳するかもしれぬが……」
細い目を更に細くして、懐かしそうに笑んだアーラ様は息を継いで、
「さて、何処から話したら良いかの……うむ……まずルーラ、そなたは既に父親から自分の出生のいきさつを聞いたな。銀色の髪を持つ母親と人間の父親……ウイスタもまた、同じ境遇じゃった。そしてそのような人魚はあの結界の中に二人きり──いや、ウイスタが死んだ今、そなただけになったのじゃ」
「あたし……だけ?」
ルーラは自分の首に架かる二つの石を見て、再びアーラ様へと視線を戻した。
「そうじゃ。二人に共通することは更に二つ。金色の髪を持ち、母親の涙を石とする──つまり、それがシレーネを継ぐ条件じゃった。逆を言えば、二人以外の人魚は母親の涙を石としない──そう、皆の持つ石は深海から得た物じゃった」
「だとしたら、誰も嘘はついていないということ……」
疑問が疑問を呼んでいく。僕はそんな感じがしていた。でも此処はアーラ様の話を聴こう。絡み合った糸を一つ一つほどいていくには時間が必要なようだ。
「母親の涙と深海で採れる石──この二つはまるで異質な物のようだが、果たしてそうでもないのじゃ。そなた達は知らぬじゃろが、結界の底──海溝には幾つもの屍が眠っている。あそこは云わば人魚の墓場……ウイスタの死を見たお主等は、泡となり消えゆく肉体が何処へ向かったか分かるか? あれは無となったのではない。気化して空中を舞い、海中へと流れ、海溝に降り積もるのじゃ……生前抜き取られた鱗以外はな」
僕は無意識にズボンのポケットに入れてある大ばば様の鱗に触れた。確かに大ばば様が自ら剥ぎ取ったこの鱗だけが残り、他は全て消えてしまったように見えたが、となると、死んだ人魚達の魂さえも其処に眠っているのだろうか。
「基本的に人魚は時期を見て独自に妊娠し出産をする……我も、そなたの姉カミルもそうして生まれてきた。そして生まれ落ちる時、海溝に眠るその者の先祖──血の結び付きを持つ者が石と化して守護を司るのじゃ。人魚として生きる為の能力・受け継がれてきた魔法はその石によって発せられ保持され発展し、そして石がその肌身から取り去られた時、石と共に自身も滅びゆく……これが人魚の宿命と云えよう」
血によって継承され、血によって守られる。母親の涙も先祖の亡き骸も確かに血縁の象徴だ。けれど石と共に自身も──ならば何故ウィズの石は……?
「ふむ、二人共気付いたようじゃな。何故かのう、涙から作られた石はそれを持つ者の命が尽きても消えぬのじゃ。それから銀色の髪の人魚が持つ先祖の石も……カミルも持っているであろう、母親の石を」
「確かに……」
ルーラの呟きに、僕は結界の中でルーラの姉さんと対面した時を思い出した。カミルの首には涙型と輪状の石が輝いていた。どちらかが母親テラの持っていた石なのだろう。
「我の勝手な見解じゃがな、どちらも残された者の使命が大きい故の結果なのじゃろう。涙石を持つ人魚はシレーネとして人魚界を統率せねばならぬし、銀髪の人魚が独自に産んだ娘──これは必ず銀髪で生まれてくるのじゃが──それにもまた、シレーネの補佐という重要な任務がある。その運命を平らかに繋ぐ為、石は残り、遍く導いてゆく道標となるのじゃろ」
「重要な……任務」
ルーラの顔色が変わった。それこそが姉カミルを豹変させた理由ならば。二人の蟠りを解く鍵になるのかもしれない。
けれど当のアーラ様はルーラの疑問に気付いたのか気付かなかったのか、その先は語らず話を変えてしまった。
「さて、枝葉の話が長過ぎてしまったな。そろそろ本題に入ろう。ウイスタはシレーネを頂点に立たせ、以前のように人魚界を統治する道を選んだ。ルーラ……そなたにシレーネを継ぐ意志が有るのならば、これから話すことは聴かねばならぬじゃろう……はて、どうかな?」
目の前に現れた飲み物を口元へ寄せて喉を潤したアーラ様は、横目でチラリとルーラの表情を探った。
ルーラはと言えば、その質問は意外だったらしい。既に儀式も終え、立派なシレーネとなるため此処へ来たのだ。何を今更──そんな気持ちが面にありありと表れていた。
「あんな儀式は形式だけじゃ。そなたが嫌だと言えば今でも後戻り出来るぞよ?」
そう言ったアーラ様の眼つきはちょっと悪戯めいていた。しかしルーラはピンと背筋を伸ばし、アーラ様の方を真剣に見つめて、
「いえ。あたしも今の人魚界には不満があります。もし自分でそれを変えられるのなら……」
その言葉に呼応するように、アーラ様もまた「うむ」と頷き意を決した。
太古より紡ぎ続けられた物語が、今解き放たれようとしていた──。
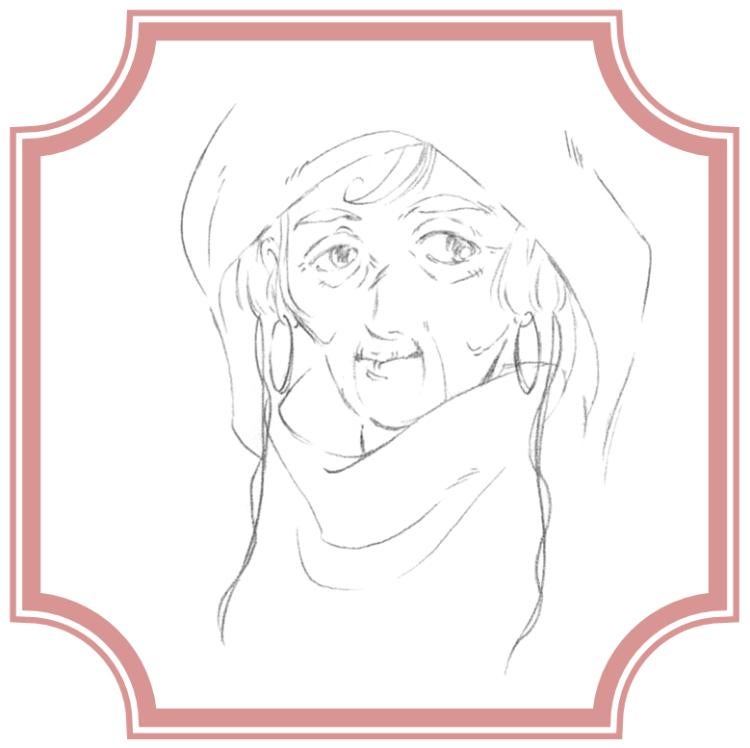
◇此処までお付き合いくださいまして、誠にありがとうございます<(_ _)>
以前からリクエスト(?)の多かった「大ばば様」のイラストを挿入致しました。
投稿後に少しイメージが違う感じがしまして、手直しをしようか迷ったのですが、自分の亡き祖母に似ている事に気が付きまして! 直さない事に致しました(笑)。
フードから出ている左右の長い物は、絵的に寂しい感じが致しまして描き込んでみましたが、髪の毛ととるか飾りととるかは皆様の自由でございます~(^_-)
それでは引き続き何卒宜しくお願い致します!
僕は頬を濡らす雫の感覚で目を覚ました。
瞼をゆっくりと持ち上げる。視界はぼやけているのか、明るさだけは理解したが、はっきりとした物の輪郭は見つけられない。横倒しになっているらしく、逆の頬にさらさらとした砂の粒子を感じる──砂浜? 僕達はラグーンへ辿り着くことなく、何処かへ打ち上げられてしまったのだろうか?
「……ア……メル……」
──ルーラ?
背後から呻くような僕を呼ぶ声が聞こえた。
重い身体を引きずり反対方向へ向きを変える。繋いだ手の先に砂にまみれたルーラの姿があった。一粒一粒が辺りの光を吸い込み、ルーラはまるで細かなダイヤを散りばめているようだ。
「ルーラ……大丈夫?」
僕はだるそうに起き上がって、彼女の髪と頬の砂を優しく指の腹で払った。眩しそうな顔をしてルーラも半身を起こした。
「うん……ここ、どこかしら? ラグーンの中?」
ルーラの鱗を小さな波が濡らしていた。そういった近くの物は何とか判別がつくが、遠くを見渡そうとしても、まるで世界を包み込むようなまばゆい明るさに邪魔されて目を覆いたくなる。
「父様達、無事かしら……」
座り込んだルーラの呟きにつぶさに、
──船は無事じゃよ。
天上から見知らぬ声が答えてきたので上空を見上げ、僕達はあっと声を上げた。
「頭の上に、海がある……?」
立ち上がって背伸びをすれば届きそうな位置に、まるで世界をひっくり返したように『海』が存在していた。その表面は穏やかな波を立て、時々発生した水しぶきが僕達に降りかかってくる。
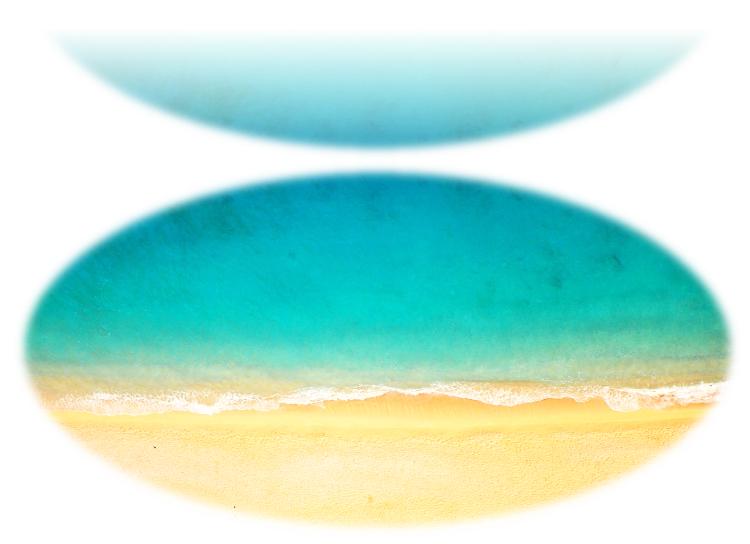
「アーラ……様? アーラ様ですか?」
ルーラはハッとしてその海へと叫んだ。もし声の主がアーラ様ならば。此処はサファイア・ラグーンということになる。
「そうじゃよ」
天上を見つめて答えを待つ僕達へ、意外なことにその声は背後から聞こえ、二人同時に振り返った。砂浜の延長上に広がる──つまりルーラの鱗を濡らす波の先の海面すれすれに、白いローブの小じんまりした姿が浮かんでいた。
「ようこそ、サファイア・ラグーンへ……ルーラ、アメリゴ……いや、そなた幼少から両親より呼ばれた愛称を好むのだったな。ようこそ、アメル」
深く被ったフードの端から見え隠れする、皺の寄った口角が少々吊り上った。何故だ? ルーラにも話していないことをこの人は知っている。
「あたし達が来るのを、ご存知だったのですか?」
自分の名を呼ばれたことに驚いたルーラは、僕と顔を見合わせアーラ様へと問うた。
「まあな……手荒い招きで失礼したが。許せ……此処は本来生きた者の来られぬ場所。色々訊きたいことも有ろうが、少し休みなさい。朝食も未だじゃろう」
そう言ってアーラ様は、ローブの袖から指先だけを出し手招きした。
僕達は再び目を合わせ、彼女の許へ向かった。ルーラと手を繋ごうとして手を伸ばしたが、そうせずとも既に空気の膜が出来ていることに気付かされる。刹那アーラ様は少し振り向いて、
「いつまでもそれでは不便じゃろ? いや……その方がそなたには良いのかな、アメル」
にんまりとした口元に、僕は頬を赤くして俯いた。ルーラは不思議そうに僕を横から見上げたが、音もなく海へと沈んでいくアーラ様を追ってスイスイと泳ぎ、僕は不恰好に手足をバタつかせて彼女達へと続いた。
海底は緩やかな傾斜で、先に進むほど深さが増し、青のグラデーションは次第に黒へと変化していった。海岸からずっと砂の地面が続いているが、両腕の幅程度で一直線に伸び、ラグーンと呼ばれる通り両端には珊瑚礁が広がっている。
やがて正面にぼんやりと白く光る空間が現れ、ドーム状の薄い膜で覆われたその中は、水中とも空中とも言い難い不思議な世界だった。入口もなく急に其処へと切り替わり、僕を包む空気の層は失ってはいないものの視覚的には消え、しかもルーラは普通に泳ぎ回ることが出来た。
「まぁ、座りなさい」
アーラ様は中央にしつらえた白い丸テーブルと簡素な三脚の椅子へ僕達を誘い、促すように自ら腰をかけた。まるで予見していたように用意された調度──いや、アーラ様は僕達が来ることを知っていたと言った。
とにかく家主たるこの魔法使いに従うことしか出来ない今、返事もそこそこにその言葉に応じたが、一体これからどうなるというのだろう。右隣に腰かけたルーラの横顔も僕と同じ緊張した面持ちで、アーラ様の次の句を待っている。
すると喉の奥からくっくと笑って、小さな背中を揺らしたアーラ様は、
「おかしな二人じゃのう……望んで来たのはお主等じゃろう? 何を怖がる? 誰も取って食おうなどと思っておらぬのじゃから落ち着きなされ。それより朝から何も食べぬまま、もうお昼じゃぞ。毒など入れておらぬから、ささ、召し上がれ」
そう言って伸ばしたしわくちゃの手の先を見たが、いつの間にかテーブルの上には大そうなご馳走が並んでいた。
この世の物とは思えない良い匂い──その途端ルーラと僕は、胃が活発に動き出すのを感じて思わずお腹を押さえた。どちらともなく恐る恐る食事に手を伸ばしたが、あまりの美味しさに気が付けば無我夢中で大半を食べ終えていた。
「ごっ、ごちそう様でした……」
突如として現れた飲み物らしきカップに口をつけ、僕はそう言いホッと息を吐いた。じっと石のように動かず、やっと見える口元に微笑みを湛えて見守っていたアーラ様は、少し間を置いて満足そうに「うむ」と頷き、
「ようやく落ち着いたかの……まぁ、また落ち着いている場合ではなくなるじゃろが……」
言い終わらぬ内にフードに手を掛け、ゆっくりとこちらへ向けられた姿は、声も出なくなるほどに驚きの、あの懐かしい人物のものであった。
「おっ……大ばば様!」
僕達は思わず立ち上がって叫んでいた。
そう……ずっと気になっていた白いローブ。この声、この背丈。皺だらけの肌。全てが似ていた、大ばば様に。──似ていた?
「大ばば様! 生きていたのね……良かった! 大ばば様……」
ルーラは既にアーラと名乗った老婆に抱きつき、泣いて再会を喜んでいた。優しく髪を撫でるアーラ様、しかし、
「ほぉ……やはりそんなに似ているかの。昔も双子のように瓜二つであったが……歳をとっても変わらぬのだから、血の繋がりとは強きものじゃ」
ハッとして動きを止めた僕達に、にっこりと微笑んだアーラ様のその表情は、確かにちょっと違うニュアンスを持っているように思えた。
そうだ、微妙に声色も高い……初めに聞いた時、見知らぬ声と感じたのもその所為だ。それなのにこの姿・装いに、僕らは大ばば様であってほしい・生きていてほしいという願望からか、幻を見ていたのかもしれない。
「大ばば……様じゃない?」
しがみついた腕そのままに、ルーラはじっとアーラ様を見つめた。大ばば様でないと気付いた彼女の表情の変化は、少し離れて立ち尽くす僕にさえも見て取れた。
「我はウイスタの姉……たった一つ違いじゃがの」
涙を溜めたまま驚きを隠せず沈黙するルーラに、アーラ様は再びニッと笑って彼女の首元に手をやった。
「懐かしいのぉ……ウィズの石。百五十年振りじゃろか。これもまたそなたの物と同様、母親の涙じゃ……我とウイスタの母親。父親の涙までは交じっておらぬがの」
そっとウィズの石に触れた途端、再びあのオレンジ色の光が、ぼぉっとアーラ様の身体を包み込んだ──まるで再会を喜ぶように──大ばば様が……それとも二人の母親だろうか?
「あの……アーラ様」
「何じゃ? 我も“ばば”で良いぞ、ルーラ」
涙を拭いて席に戻ったルーラに、アーラ様はほほっと笑っておどけて答えた。
「何故結界の皆はあたしに、石は深海で採れると嘘をついたのですか?」
僕も気を取り直して椅子に腰かけた。アーラ様はこれまでの調子を崩さず、穏やかな表情でルーラを見つめ説明を始めた。
「誰も嘘はついておらぬよ……ただ知らなかっただけじゃ。あの結界の中で唯一知っていたのはウイスタのみ──厳密に言えばウイスタは嘘をついたのかもしれぬな……あれがもし生きていたら、訊かれぬから答えなかったのだと言い訳するかもしれぬが……」
細い目を更に細くして、懐かしそうに笑んだアーラ様は息を継いで、
「さて、何処から話したら良いかの……うむ……まずルーラ、そなたは既に父親から自分の出生のいきさつを聞いたな。銀色の髪を持つ母親と人間の父親……ウイスタもまた、同じ境遇じゃった。そしてそのような人魚はあの結界の中に二人きり──いや、ウイスタが死んだ今、そなただけになったのじゃ」
「あたし……だけ?」
ルーラは自分の首に架かる二つの石を見て、再びアーラ様へと視線を戻した。
「そうじゃ。二人に共通することは更に二つ。金色の髪を持ち、母親の涙を石とする──つまり、それがシレーネを継ぐ条件じゃった。逆を言えば、二人以外の人魚は母親の涙を石としない──そう、皆の持つ石は深海から得た物じゃった」
「だとしたら、誰も嘘はついていないということ……」
疑問が疑問を呼んでいく。僕はそんな感じがしていた。でも此処はアーラ様の話を聴こう。絡み合った糸を一つ一つほどいていくには時間が必要なようだ。
「母親の涙と深海で採れる石──この二つはまるで異質な物のようだが、果たしてそうでもないのじゃ。そなた達は知らぬじゃろが、結界の底──海溝には幾つもの屍が眠っている。あそこは云わば人魚の墓場……ウイスタの死を見たお主等は、泡となり消えゆく肉体が何処へ向かったか分かるか? あれは無となったのではない。気化して空中を舞い、海中へと流れ、海溝に降り積もるのじゃ……生前抜き取られた鱗以外はな」
僕は無意識にズボンのポケットに入れてある大ばば様の鱗に触れた。確かに大ばば様が自ら剥ぎ取ったこの鱗だけが残り、他は全て消えてしまったように見えたが、となると、死んだ人魚達の魂さえも其処に眠っているのだろうか。
「基本的に人魚は時期を見て独自に妊娠し出産をする……我も、そなたの姉カミルもそうして生まれてきた。そして生まれ落ちる時、海溝に眠るその者の先祖──血の結び付きを持つ者が石と化して守護を司るのじゃ。人魚として生きる為の能力・受け継がれてきた魔法はその石によって発せられ保持され発展し、そして石がその肌身から取り去られた時、石と共に自身も滅びゆく……これが人魚の宿命と云えよう」
血によって継承され、血によって守られる。母親の涙も先祖の亡き骸も確かに血縁の象徴だ。けれど石と共に自身も──ならば何故ウィズの石は……?
「ふむ、二人共気付いたようじゃな。何故かのう、涙から作られた石はそれを持つ者の命が尽きても消えぬのじゃ。それから銀色の髪の人魚が持つ先祖の石も……カミルも持っているであろう、母親の石を」
「確かに……」
ルーラの呟きに、僕は結界の中でルーラの姉さんと対面した時を思い出した。カミルの首には涙型と輪状の石が輝いていた。どちらかが母親テラの持っていた石なのだろう。
「我の勝手な見解じゃがな、どちらも残された者の使命が大きい故の結果なのじゃろう。涙石を持つ人魚はシレーネとして人魚界を統率せねばならぬし、銀髪の人魚が独自に産んだ娘──これは必ず銀髪で生まれてくるのじゃが──それにもまた、シレーネの補佐という重要な任務がある。その運命を平らかに繋ぐ為、石は残り、遍く導いてゆく道標となるのじゃろ」
「重要な……任務」
ルーラの顔色が変わった。それこそが姉カミルを豹変させた理由ならば。二人の蟠りを解く鍵になるのかもしれない。
けれど当のアーラ様はルーラの疑問に気付いたのか気付かなかったのか、その先は語らず話を変えてしまった。
「さて、枝葉の話が長過ぎてしまったな。そろそろ本題に入ろう。ウイスタはシレーネを頂点に立たせ、以前のように人魚界を統治する道を選んだ。ルーラ……そなたにシレーネを継ぐ意志が有るのならば、これから話すことは聴かねばならぬじゃろう……はて、どうかな?」
目の前に現れた飲み物を口元へ寄せて喉を潤したアーラ様は、横目でチラリとルーラの表情を探った。
ルーラはと言えば、その質問は意外だったらしい。既に儀式も終え、立派なシレーネとなるため此処へ来たのだ。何を今更──そんな気持ちが面にありありと表れていた。
「あんな儀式は形式だけじゃ。そなたが嫌だと言えば今でも後戻り出来るぞよ?」
そう言ったアーラ様の眼つきはちょっと悪戯めいていた。しかしルーラはピンと背筋を伸ばし、アーラ様の方を真剣に見つめて、
「いえ。あたしも今の人魚界には不満があります。もし自分でそれを変えられるのなら……」
その言葉に呼応するように、アーラ様もまた「うむ」と頷き意を決した。
太古より紡ぎ続けられた物語が、今解き放たれようとしていた──。
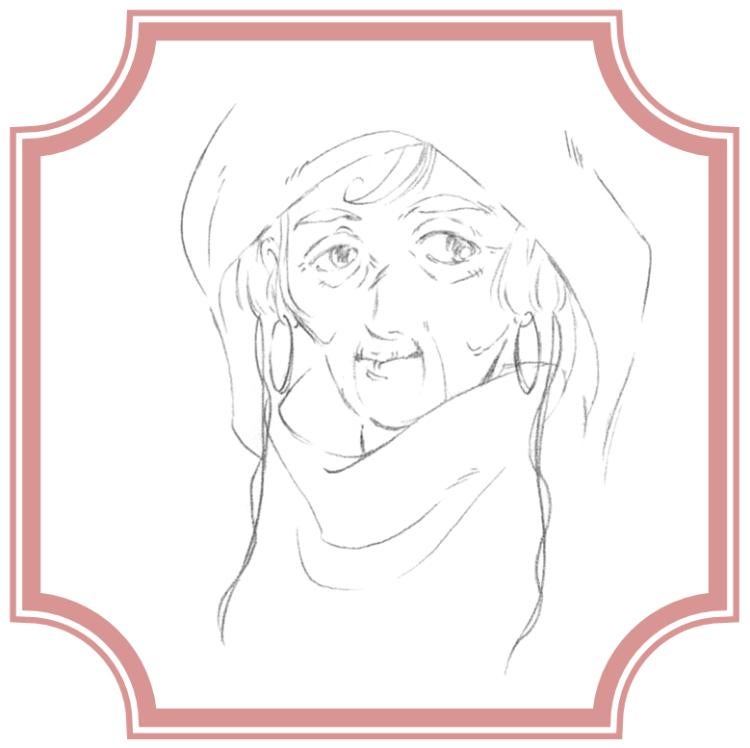
◇此処までお付き合いくださいまして、誠にありがとうございます<(_ _)>
以前からリクエスト(?)の多かった「大ばば様」のイラストを挿入致しました。
投稿後に少しイメージが違う感じがしまして、手直しをしようか迷ったのですが、自分の亡き祖母に似ている事に気が付きまして! 直さない事に致しました(笑)。
フードから出ている左右の長い物は、絵的に寂しい感じが致しまして描き込んでみましたが、髪の毛ととるか飾りととるかは皆様の自由でございます~(^_-)
それでは引き続き何卒宜しくお願い致します!
 | 野いちご](https://www.no-ichigo.jp/assets/1.0.787/img/logo.svg)




![月とガーネット[下]](https://www.no-ichigo.jp/img/member/1247997/zcrelg1uqj-thumb.jpg)