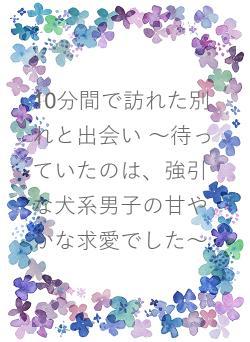「……あぁ、そうだった」
慎くんは思い出したのか、自分のカバンからお弁当箱を取り出して広げ始める。
「慎くん、何度も言ったから分かってると思うけど……私が慎くんのお家で暮らしてるってことは、絶対に秘密だからね。くれぐれもバレないように、注意してほしいの」
周囲に人がいないことを確認してから、声を潜めて伝えれば、おかずのミニハンバーグを頬張っていた慎くんは、きょとんとした顔をする。
そして、口の中のものをゴクンと飲み込んだかと思えば、何か考えるような素振りをして、私の耳元に顔を近づけてくる。
「――それじゃあバレないように、千夏子は俺のこと、ちゃーんと見張っておくことだね」
私の耳元でそう囁いてきた慎くんは、意地の悪い顔で微笑んだ。
私は咄嗟に慎くんから距離をとって、前を向く。
「話は終わった? ……って、千夏子どうした? 何か顔が赤いけど」
「な、何でもないよ! ちょっと暑いだけだから!」
スマホをいじっていた朱里ちゃんは、私の顔を見て不思議そうに首をかしげている。
後ろでお弁当を食べているであろう慎くんに対して、私は熱くなった頬に手を当てて冷やしながら、何だか悔しい気持ちでいっぱいになっていた。