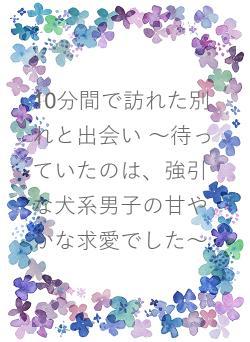「わ、分かったから! ちょっと離れて!」
「え~」
慎くんの頬をぐいぐい押して距離をとってから、私はまた早歩きになる。
だけど足の長い慎くんはすぐに追いついてきて、隣に並ぶ。
「それじゃあ、家まで手つないで帰ろ」
慎くんの大きな手のひらが、私の左手を包み込んだ。
どうせまた、私の反応を見て揶揄おうとしてるんだろうなって、そう思いながら隣を見上げてみた。
だけど、私を見下ろす慎くんが、すごく幸せそうな顔で笑っているように見えたから。
(っ、そんな顔して笑うのは、ずるいよ……)
――胸がくすぐったくなるような、甘やかな痺れに、私はそれ以上言葉を返すこともできずに黙って歩いた。
家に着くまで、繋がれた手が離れることはなかった。