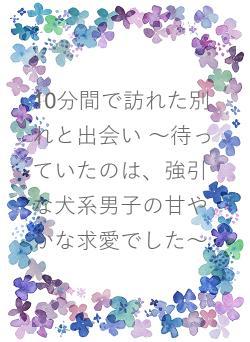――正直、慣れない至近距離に心臓はバクバクしていたけど、照れていることがバレたら最後、由紀さんのことだし、面白がってもっと揶揄ってくるに決まってる。
だから私は必死に無表情を保った。
もしかしから、顔はちょっとだけ赤くなっているかもしれないけど……由紀さんにはバレていないみたいで良かった。
「でもまぁ、さっきに女の子たちの顔はしーっかり覚えたからさ。もし千夏子ちゃんに危害を加えた時は……俺がちゃーんと挨拶に行っておくから、安心していいよ~」
由紀さんは笑っているけど、細められた目の奥は、全然笑っていない。
どことなくピリピリした雰囲気を感じる。
空気を換えたくて、私は何か話題はないかと頭を働かせる。
「ゆ、由紀さんは、この後はまっすぐ家に帰るんですか? それともどこかに寄って帰ります?」
「ん~、ちょっと街で遊んでくる。でも夕飯は食べるから、俺の分も用意しておいてね」
「わかりました」
「あ、それからさぁ」
普段通りに戻った由紀さんは、腰を折って再び顔を近づけてくる。