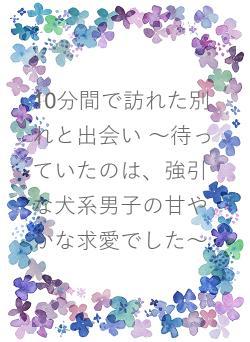お粥を手渡せば、由紀さんは素直にお椀を受け取ってくれた。
いつもの由紀さんなら、絶対に何かしらのちょっかいをかけてきたり、揶揄いの言葉の一つや二つが飛び出してきている頃だ。
だけどそんな素振りもない。
こんなにしおらしい由紀さんは初めて見るし、相当しんどいのかもしれない。
「まだ熱いので、冷まして食べてくださいね。それから、一哉くんがスポーツドリンクを買ってきてくれたので、あとで持ってきますね。水と薬はサイドテーブルに置いておきますから。あと、他にも何か欲しいものがあれば言ってください」
「……千夏子ちゃん、母親みてぇじゃん」
甲斐甲斐しく世話を焼いていれば、気だるげな顔をしていた由紀さんが、ほんの少しだけ口角を持ち上げて笑った。