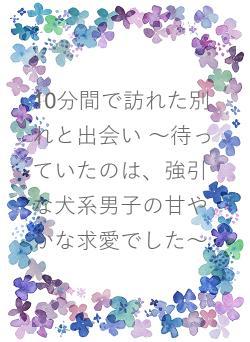「そ、そろそろ本当に帰るぞ! ……千夏子」
「っ、え? 今、名前で呼んでくれたよね?」
一哉くんの背中を慌てて追いかけて、確認の意味も込めて尋ねてみた。
だけど一哉くんに、フイッと視線を逸らされる。
照れているのか、さっきから全然目が合わないし、声もどこか素っ気ない。
「……気のせいじゃねーの?」
「えー、絶対に気のせいじゃない! ……と、思ってる!」
聞き間違いなんかじゃなかったはずだ。
今までは「お前」とか「ババア」とか、そんな呼ばれ方しかされていなかったから……名前で呼んでもらえたことは、認めてもらえたみたいですごく嬉しい。
「ふっ、喜びすぎだろ」
目を輝かせていた私を見た一哉くんは、不機嫌そうな顔を崩して笑った。
私を見つめるまなざしは、とても優しく見えて――子どもたちに向けていたものに似ているなって、そう思った。
一哉くんとの距離が少し縮まったように感じた、そんな秘密の休日の話だ。