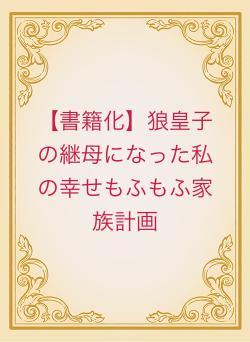「離せっ! わかった。ミランダ、私の誘いを断ったこと、後悔することになるぞ!?」
「はいはい。とーっても後悔しておきますね」
「本当だ! あとから働きたいと泣いて縋っても私は絶対に雇わないからな!?」
「大丈夫です。働くのは嫌いなので」
「強がっても無駄だ!」
イーサン殿下は一通り叫ぶと、逃げるように修道院から去って行った。
本当に何しに来たのかしら?
逃げるように帰っていく馬車を窓から見て、わたしはほくそ笑んだ。
だって、この後のことは見なくても手に取るようにわかる。
王妃様は厳しい人よ。きっと、あのふわふわ頭を王太子妃に相応しくなるように教育しなおす筈。
私が十年で身につけたことを、結婚までできるとは思えない。
その前に音を上げるに決まっている。
想像するだけで、溜飲が下がった。
すると、オルトがわたしの側に跪き、わたしの手を取った。
「どうしたの?」
赤く腫れているわたしの腕に唇を落とした。そして、彼は上目遣いでわたしを見る。
綺麗な黄金の瞳と目が合って、心臓が跳ねる。
わたしはそれを隠したくて、慌てて腕を引っ込めた。
「これくらい大丈夫よ」
いつもどおり、わたしはオルトの頭を撫でる。
乱暴に。
なぜか、心臓がうるさかった。
「あいつ、嫌い」
「気が合うわね。わたしも嫌いよ」
「俺の、傷つけた」
俺の?
わたしが首を傾げる前に、オルトがわたしを後ろから抱きしめる。
「ちょっと!」
「ミランダは俺の」
オルトはわたしの首筋に顔を埋める。
ふわふわとした黒髪がくすぐったい。
心臓がいまだ早歩きしている。心臓がこんなに忙しなく動くのは初めてで、わたしはどんな顔をしていいのかわからなかった。
その日から、オルトはわたしの足元から横で眠るようになった。
気持ちよさそうに眠るオルトを見て、わたしはため息を吐く。
この拾いもの、失敗したかも。
少し幼さの残る寝顔。わたしは彼の額に唇を落とした。
FIN