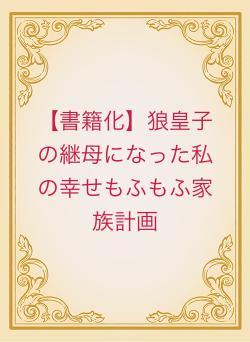みんな辞めてしまうと思っていたのよ? だって、わたしが見つけてきた人材だったから。
王太子妃となることが決まった十年前から、わたしの素晴らしきぐーたら生活への準備は始まっていた。
わたしの力なんてたかが知れている。だから、わたしはわたしよりも能力の高い人間を探すことに時間を割いたのだ。
書類整理に長けている者、計算能力の高い者、情報収集が得意な者……。
わたしって、人の才能を見抜くのは得意だったみたい。身分関係なく、能力のある人を採用していった。
すべては私の怠惰な王太子妃生活を送るために。
その計画が壊れて、みんなには手紙を書いておいたのよ。どうするかは自由だけど、王宮が嫌だったらいつでもいらっしゃいってね。
この様子だと、みんな辞めちゃったのかしら?
「おまえのせいで、母上にも怒られ散々だ!」
「あの可愛い彼女に頑張っていただけばいいじゃない? 王太子妃になると決めたのだから、それくらいの気合いはあるでしょう?」
わたしは何も悪いことはしていない。
ただ、一緒に仕事をする予定だった友人たちに、事情が変わったと手紙を書いただけだ。イーサン殿下は王太子妃の側で働く予定の者と言っているけれど、元々、わたしの元で働く予定だった者だもの。
主人が変わったら、退職を希望する可能性を考えられないのかしら?
イーサン殿下はわたしの腕を掴んで離さない。
「そろそろ離してくださらない?」
わたしが言うと、イーサン殿下の力が強くなる。
「痛いわ!」
女性の腕を掴む力じゃないわ!
すると、オルトがイーサン殿下の腕を掴んだ。
「離せ」
「……くっ!」
オルトが掴んだ手に力を加えると、イーサン殿下の手から力が抜けた。
わたしは慌てて、イーサン殿下の手から腕を引き抜く。
ああ、赤くなっているじゃない。痣になっちゃうかも。
「おまえ、嫌い」