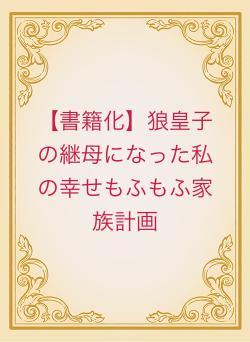わたしが王都を去って、まだ一か月。
いつかこの日が来ることは予測していた。
一台の馬車の周りを兵が厳重に囲んでいる。
「オルト、あれは放っておいていいわ。相手にしていると時間を無駄にするから」
わたしはそれだけ言うと、もう一度ベッドの上に転がった。
ああ、眠りすぎて背中が痛い。
この痛みがまた最高なのよ。
オルトは何度か窓の外を気にしていたけれど、すぐに興味を失った。
馬の蹄の音が遠くに、聞こえる。それすらもわたしには子守歌のようだ。
うとうととしていると、足音が遠くから聞こえて来た。
そして、大きな音を立てて、扉が開いた。
「ミランダ・オロレイン! どういうつもりだ!」
怒号が部屋中に響いた。
「うるさいわ。少しは静かにできないのかしら?」
ベッドから起き上がる気にもならず、わたしはわずかに顔を上げただけで対応した。
それが、イーサン殿下の逆鱗に触れたのだろう。イーサン殿下は大股でまっすぐわたしの元まで歩くと、わたしの腕を掴んだ。
「婚約を破棄した相手に、なんのご用かしら?」
「言ったはずだ。君にはエミリアの補佐をしてもらうと」
「申し訳ございません。ご覧のとおり、婚約を破棄されたことを父に怒られ、修道院に入れられましたの」
イーサン殿下が顔を歪める。
正確には自ら進んで修道院に来たのだけれど、その辺はどうでもいい。
「しかも、王太子妃の周りで働く予定だった者たちが一斉に辞めた! 君の差し金だろう!?」
「あらあら。一介の令嬢にそんな力はありませんわよ」