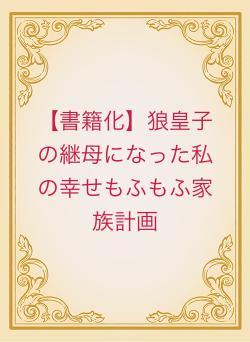オルトは深く頷く。
オルトを連れて帰ってきてから一ヶ月。オルトはわたしにだけ懐いた。
修道院に暮らす人々を威嚇し、わたしの執事にも警戒し、わたしの側を離れない。
まあ、今までの一人で北の塔に閉じ込められていたのだから、これくらいは可愛いものだと思う。
そして、オルトはわたしの頼み事や願い事のためだけに、せっせと働いた。
わたしが「肉が食べたい」と言ったら、山に住む動物を狩り、「寒いから毛皮がほしい」と言えば、こうやって熊を狩ってくる。
「ありがとう。これでぬくぬくで眠れそうだわ」
わたしは礼を言うと、オルトが背を屈める。
これは、頭を撫でろという合図だ。
彼はわたしよりも身長が高い。座っている時は安易に撫でられる。だから、わたしは彼が座っているときにだけ撫でていた。そうしたら、いつの間にか撫でられに来るようになったのだ。
減るものでもないし、彼の髪は手触りもいいので嫌ではない。
オルトは満足そうに頭を上げると、太陽を見上げた。
「昼寝」
「そうね。そろそろお昼寝の時間だわ」
北の修道院に来てよかったことは、毎日同じ時間にお昼寝ができることだ。
それだけで、どれほど幸せだろうか。
イーサン殿下の婚約者だったときは、昼寝がしたくても社交や勉強でどうしても時間が取れなかった。
もっと早く、イーサン殿下に見切りをつけて、ここに来ればよかったのよ。
考え事をしていると、オルトがわたしをひょいっと抱き上げる。
これも日常茶飯事になってしまって、驚かなくなった。最初こそ驚いたけど。
わたしの部屋は修道院の最上階。
階段を上るのも大変なのよ。オルトが嫌がっていない以上、任せてもいいと思ったのだ。
はー、快適快適。
部屋に到着したオルトは、わたしをベッドの上に置いた。
そして、寝っ転がる私の足元に小さくなって座る。
「オルトも寝るの?」
「寝る」