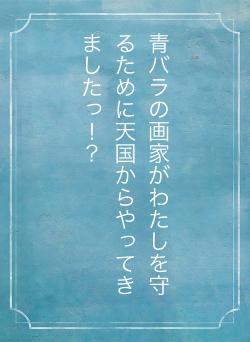中学校の休み時間。
わたしは、今日も柚希の推し活の話を聞かされてる。
柚希はわたしの前の席だから、授業が終わったら、流れるように「そういえばさ」なんていって、推しの話がはじまるんだ。
わたしは、六年間ずっと、星成術の修行をしていたから、話せることといったら、星成術のことと、セルヴァン会長の愚痴くらい。
だから、柚希の話は、すごく興味津々なんだ。
柚希は、話すのがすごくうまいから、聞いてて飽きないしね。
「何、話してるの」
顔をあげると、燐くんがいた。
「燐くん。職員室の用事、おわったの?」
「うん。教科書、届いたみたいだから、取りに行ってきた」
「よかった。もう、自分の教科書で授業、受けられるんだね」
「そうだね。まあ、ぼくは別に今のままでも、かまわなかったけど」
机に積みあがった教科書を机にしまいながら、燐くんはちらりとわたしたちのほうを見た。
「それで、何話してたの」
「あたしの最推し! 蓮華くんのこと!」
柚希は、前のめりになりながら、目をきらきらと輝かせた。
「蓮華くんはね、いま一番ノリにノってるアイドルグループ『NOAH』のメンバーなんだ♡ ちょ~かっこよくて、でも練習のオニで、ファンのことを第一に考えてくれる最高の推しなの♡」
「さいおし? なにそれ?」
それを聞いた、柚希はガタンと席を立つと、得意げに胸をはった。
「『最推し』っていうのは、あたしの人生の星のこと! または~生きる道しるべだね!」
へえ~すてき! わたし、最推しって『すきな人』って意味だと思ってたけど。
わたしが知らないだけで、『最推し』って言葉には、もっと深い意味がこめられているんだなあ。
「人生の生きる道しるべ、ね。なんか、いい言葉」
ぽつり、と燐くんがつぶやいた。
柚希は、それを聞き逃さなかったみたいで、うれしそうに燐くんにつめ寄る。
「おおー! 推し活をする才能があるね!」
「ぼくは、そんなものしないよ。だって、星には、ぼくの手なんて届かないでしょ」
そういう燐くんの視線は、なぜかわたしを見つめていた。
どうしたんだろう?
そのとき、突然、廊下が騒がしくなってきた。
教室のクラスメイトたちが、ざわざわと騒ぎだす。
「おい、あれ……。二年の時任先輩じゃないか?」
「えっ。なんで一年の教室に……?」
なぜだか、不穏な雰囲気で会話をしている男子たち。
時任先輩――どこかで、聞いたことがあるような名前だな。
時任……時任……。
考えていると、立ったままだった柚希が背伸びをして、廊下のほうをのぞきこんだ。
「うわ。ほんとうだ。時任先輩がいる」
「知ってるの?」
燐くんが聞くと、柚希は「有名人だよ」と苦笑した。
「時任出流。二年の先輩。かなりの変人で、いっつもクラスメイトともめてるってうわさだよ。『おかしなひとりごと』をよくいってるんだって。『祝祭』がどうとか、『財団』がどうとか。それに、自分の意見はぜったいに曲げないし、急に教室を出て行って、先生を困らせたり、めっちゃ自由人みたい!」
「へえ。たしかに、変わってる」
燐くんのそっけない反応が不満だったのか、柚希は目をキランと光らせて、とっておきとばかりに、人さし指を立てた。
「それだけじゃないよ! なんでも、時任家っていうのは、宝井町の旧家で昔、アヤシイ術を使って、町の人々から恐れられていたっていう都市伝説まであるんだって!」
「アヤシイ術って……なにそれ。おとぎ話?」
「も~佐々波くん! これガチ! 都市伝説じゃないらしいよ」
そのとき、廊下から女子の悲鳴が響いた。
見ると、うちのクラスの女子が、時任先輩に腕を掴まれている。
「――オレは質問をしているだけだ。つまり、おまえは、すみやかに答えればいい」
「ひいっ。ごめんなさいっ」
「もう一度、いう。歌仙陽菜はどこにいる」
「こここ、この教室に、いると思いますっ」
クラスの女子は、おびえた目をして、答えている。
ふと、その子とわたしの視線があった。
申し訳なさそうにしているその子に、わたしは「気にしないで」と視線で返した。
時任先輩は、その子を解放すると、うちの教室にずかずかと入ってきた。
燐くんが、わたしのそばに着いてきて、耳打ちをしてくる。
「陽菜。あの先輩、へんだ。近寄らないほうがいい」
「……うん、ありがと」
だけど、わたしは時任先輩のことを知っている。
思い出した。
セルヴァン会長から、聞いてたんだ。
アステル百年祝祭に登録されている、三人の星成士のひとりだ。
ひとりは、わたし。
そして、ふたり目が時任という名の星成士だと。
時任家は、さっき柚希が説明したとおり、古くから宝井町にいる旧家だ。
そして代々、星成士をしている家系。
時任先輩は、その血筋を受け継いでいるんだろう。
でもまさか、同じ学校だったなんて……。
「ったく。セルヴァン会長、教えてくれてもいいのに」
教室に入ってきた時任先輩は、わたしのことを視界にとらえる。
長い足をコンパスのように動かし、あっというまに近づいてきて、品定めをするようなまなざしで見下ろしてきた。
だけど、なんで――。
「なんでわたしが歌仙だって、わかったんですか」
「その髪色を見ればわかる」
「髪色……?」
「歌仙陽菜の髪色は、夜明け色だと聞いている」
時任先輩は、中学生とは思えないほど身長が高かった。
すらりとした長い手足、歩き方も仕草も、優雅でおとなっぽい。
冷たい切れ長の瞳に、赤さび色の短髪。
「アステル百年祝祭では『星』に登録された星成士でないと、『アステル』を手に入れることはできない」
淡々と説明する時任先輩の言葉を、この場にいる全員がぽかんと聞いている。
みんな、先輩の『ひとりごと』だと思っているんだろうな。
でも、わたしにはわかってしまう。
先輩が、何をいっているのか。
「星成士の家系でもない出来そこないのようだが、ムダにあがいている。拍手がいるか?」
ワシのクチバシに似た高い鼻をあげ、おかしそうに笑う、時任先輩。
すると燐くんが、わたしをかばうように、時任先輩の前に立った。
見た人を凍りつかせるような冷たい視線を時任先輩に投げかけ、いら立ちを隠すことなく吐き捨てた。
「用がないなら、出て行ってくれない」
「用なら、あるぜ。そこの出来そこないにな。他に、用はない」
時任先輩が、わたしの手を掴もうとする。
しかし、すぐに燐くんが、時任先輩の手をきつく払った。
「陽菜に触るな」
「おまえは……歌仙陽菜の番犬か?」
「ばかにしてる?」
「よく吠える番犬には、しつけがいるな」
時任先輩の大きな手が、燐くんに向けられる。
「――燐くん!」
わたしは、その場から飛び出し、時任先輩の前に立ちふさがった。
燐くんを背中にかばい、時任先輩へ、何かを訴えるように見あげる。
みんなの前だし、この場を丸く収めたいところだけど。
「えっと……ここ、教室なんで……すみませんけど……」
「どうでもいい。オレとおまえ以外の連中に、気を配る必要性を感じない」
淡々という時任先輩に、後ろから、燐くんの息を飲む音が聞こえた。
周囲のざわめきも、一気に増していく。
なんとか、時任先輩の話を止めさせないといけない。
これ以上、クラスのみんなを……燐くんを巻きこめない。
なにより、燐くんが『アステル』だってことを時任先輩に知られるわけにはいかない――。
わたしは、今日も柚希の推し活の話を聞かされてる。
柚希はわたしの前の席だから、授業が終わったら、流れるように「そういえばさ」なんていって、推しの話がはじまるんだ。
わたしは、六年間ずっと、星成術の修行をしていたから、話せることといったら、星成術のことと、セルヴァン会長の愚痴くらい。
だから、柚希の話は、すごく興味津々なんだ。
柚希は、話すのがすごくうまいから、聞いてて飽きないしね。
「何、話してるの」
顔をあげると、燐くんがいた。
「燐くん。職員室の用事、おわったの?」
「うん。教科書、届いたみたいだから、取りに行ってきた」
「よかった。もう、自分の教科書で授業、受けられるんだね」
「そうだね。まあ、ぼくは別に今のままでも、かまわなかったけど」
机に積みあがった教科書を机にしまいながら、燐くんはちらりとわたしたちのほうを見た。
「それで、何話してたの」
「あたしの最推し! 蓮華くんのこと!」
柚希は、前のめりになりながら、目をきらきらと輝かせた。
「蓮華くんはね、いま一番ノリにノってるアイドルグループ『NOAH』のメンバーなんだ♡ ちょ~かっこよくて、でも練習のオニで、ファンのことを第一に考えてくれる最高の推しなの♡」
「さいおし? なにそれ?」
それを聞いた、柚希はガタンと席を立つと、得意げに胸をはった。
「『最推し』っていうのは、あたしの人生の星のこと! または~生きる道しるべだね!」
へえ~すてき! わたし、最推しって『すきな人』って意味だと思ってたけど。
わたしが知らないだけで、『最推し』って言葉には、もっと深い意味がこめられているんだなあ。
「人生の生きる道しるべ、ね。なんか、いい言葉」
ぽつり、と燐くんがつぶやいた。
柚希は、それを聞き逃さなかったみたいで、うれしそうに燐くんにつめ寄る。
「おおー! 推し活をする才能があるね!」
「ぼくは、そんなものしないよ。だって、星には、ぼくの手なんて届かないでしょ」
そういう燐くんの視線は、なぜかわたしを見つめていた。
どうしたんだろう?
そのとき、突然、廊下が騒がしくなってきた。
教室のクラスメイトたちが、ざわざわと騒ぎだす。
「おい、あれ……。二年の時任先輩じゃないか?」
「えっ。なんで一年の教室に……?」
なぜだか、不穏な雰囲気で会話をしている男子たち。
時任先輩――どこかで、聞いたことがあるような名前だな。
時任……時任……。
考えていると、立ったままだった柚希が背伸びをして、廊下のほうをのぞきこんだ。
「うわ。ほんとうだ。時任先輩がいる」
「知ってるの?」
燐くんが聞くと、柚希は「有名人だよ」と苦笑した。
「時任出流。二年の先輩。かなりの変人で、いっつもクラスメイトともめてるってうわさだよ。『おかしなひとりごと』をよくいってるんだって。『祝祭』がどうとか、『財団』がどうとか。それに、自分の意見はぜったいに曲げないし、急に教室を出て行って、先生を困らせたり、めっちゃ自由人みたい!」
「へえ。たしかに、変わってる」
燐くんのそっけない反応が不満だったのか、柚希は目をキランと光らせて、とっておきとばかりに、人さし指を立てた。
「それだけじゃないよ! なんでも、時任家っていうのは、宝井町の旧家で昔、アヤシイ術を使って、町の人々から恐れられていたっていう都市伝説まであるんだって!」
「アヤシイ術って……なにそれ。おとぎ話?」
「も~佐々波くん! これガチ! 都市伝説じゃないらしいよ」
そのとき、廊下から女子の悲鳴が響いた。
見ると、うちのクラスの女子が、時任先輩に腕を掴まれている。
「――オレは質問をしているだけだ。つまり、おまえは、すみやかに答えればいい」
「ひいっ。ごめんなさいっ」
「もう一度、いう。歌仙陽菜はどこにいる」
「こここ、この教室に、いると思いますっ」
クラスの女子は、おびえた目をして、答えている。
ふと、その子とわたしの視線があった。
申し訳なさそうにしているその子に、わたしは「気にしないで」と視線で返した。
時任先輩は、その子を解放すると、うちの教室にずかずかと入ってきた。
燐くんが、わたしのそばに着いてきて、耳打ちをしてくる。
「陽菜。あの先輩、へんだ。近寄らないほうがいい」
「……うん、ありがと」
だけど、わたしは時任先輩のことを知っている。
思い出した。
セルヴァン会長から、聞いてたんだ。
アステル百年祝祭に登録されている、三人の星成士のひとりだ。
ひとりは、わたし。
そして、ふたり目が時任という名の星成士だと。
時任家は、さっき柚希が説明したとおり、古くから宝井町にいる旧家だ。
そして代々、星成士をしている家系。
時任先輩は、その血筋を受け継いでいるんだろう。
でもまさか、同じ学校だったなんて……。
「ったく。セルヴァン会長、教えてくれてもいいのに」
教室に入ってきた時任先輩は、わたしのことを視界にとらえる。
長い足をコンパスのように動かし、あっというまに近づいてきて、品定めをするようなまなざしで見下ろしてきた。
だけど、なんで――。
「なんでわたしが歌仙だって、わかったんですか」
「その髪色を見ればわかる」
「髪色……?」
「歌仙陽菜の髪色は、夜明け色だと聞いている」
時任先輩は、中学生とは思えないほど身長が高かった。
すらりとした長い手足、歩き方も仕草も、優雅でおとなっぽい。
冷たい切れ長の瞳に、赤さび色の短髪。
「アステル百年祝祭では『星』に登録された星成士でないと、『アステル』を手に入れることはできない」
淡々と説明する時任先輩の言葉を、この場にいる全員がぽかんと聞いている。
みんな、先輩の『ひとりごと』だと思っているんだろうな。
でも、わたしにはわかってしまう。
先輩が、何をいっているのか。
「星成士の家系でもない出来そこないのようだが、ムダにあがいている。拍手がいるか?」
ワシのクチバシに似た高い鼻をあげ、おかしそうに笑う、時任先輩。
すると燐くんが、わたしをかばうように、時任先輩の前に立った。
見た人を凍りつかせるような冷たい視線を時任先輩に投げかけ、いら立ちを隠すことなく吐き捨てた。
「用がないなら、出て行ってくれない」
「用なら、あるぜ。そこの出来そこないにな。他に、用はない」
時任先輩が、わたしの手を掴もうとする。
しかし、すぐに燐くんが、時任先輩の手をきつく払った。
「陽菜に触るな」
「おまえは……歌仙陽菜の番犬か?」
「ばかにしてる?」
「よく吠える番犬には、しつけがいるな」
時任先輩の大きな手が、燐くんに向けられる。
「――燐くん!」
わたしは、その場から飛び出し、時任先輩の前に立ちふさがった。
燐くんを背中にかばい、時任先輩へ、何かを訴えるように見あげる。
みんなの前だし、この場を丸く収めたいところだけど。
「えっと……ここ、教室なんで……すみませんけど……」
「どうでもいい。オレとおまえ以外の連中に、気を配る必要性を感じない」
淡々という時任先輩に、後ろから、燐くんの息を飲む音が聞こえた。
周囲のざわめきも、一気に増していく。
なんとか、時任先輩の話を止めさせないといけない。
これ以上、クラスのみんなを……燐くんを巻きこめない。
なにより、燐くんが『アステル』だってことを時任先輩に知られるわけにはいかない――。