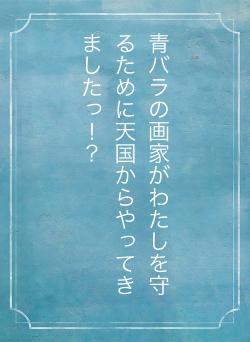燐くんが引っ越していったのは、わたしたちが小学校にあがる前。
幼稚園の年長クラス、夏が終わりがけのころだった。
燐くんの病気は、とても深刻なものだったみたいで。
海外への引っ越しも、もっといい環境で治療を受けるためのもの。
通っていた幼稚園は、だいたいいつも休みがちで、園庭での運動や遊びには参加せず、いつも見学だった。
幼稚園がおわったあと、他の子から家に招待されたり、近所での遊びに誘われても、いつもさみしそうに断っていた。
でも、わたしが誘うと、うれしそうな顔をしてくれた。
「ぼくのからだのことをわかってくれてる陽菜ちゃんなら、お母さんも許してくれると思う。帰ったら、聞いてみる」
燐くんと遊ぶのはとても楽しいから、そういってくれるのが、すごく嬉しかった。
いっしょに遊ぶ時間があっというまで、家に帰る時間になっても燐くんと別れるのはいつだってさみしかった。
てっきり、いっしょに小学校にあがるんだと思っていたのに――。
引っ越すことを告げられたときは、悲しくてさみしくて、またわたしは、わんわん泣いちゃって、燐くんを困らせた。
でも、すぐに燐くんもいっしょに泣きはじめちゃって。
いつも遊んでいた燐くんの部屋で、ふたりして、大泣きした。
さんざん泣いたあとは、手をつないで、窓の外から、夕陽をながめた。
いつまでも、この時間がおわらなければいいのに、って思ったんだ。
その次の日。
燐くんは、海外へ引っ越していった。
引っ越し当日、燐くんはお父さんが運転する車の窓から顔を出して、ずっと手を振ってくれた。
わたしも、ずっとずっと、手を振っていた。
小学校に入学しても、わたしはしばらく、燐くんとの別れから、立ち直れない日々が続いていた。
運命を変えるあの日がやってきたのは、小学一年の秋だった。
その日は、短縮授業だった。
「……痛っ!」
誰もいない家のなか、いきなり頭のなかがズキン、と痛んだ。
ズキン、ズキンと頭の痛みに必死で耐えていると、おかしな現象がはじまった。
じわじわと脳内に、へんな指示みたいなものが流れこんでくる。
いったい、何が起こってるの――。
心臓が、ばくばくと跳ねあがっていく。
ただ、指示の通りにしないといけない。
そう、思った。
わけがわからないまま、わたしは家を飛び出すと、キッチンへと走った。
キッチンのシンク下の棚から、大きな鍋を取り出し、コンロの上に置いた。
火は、つけなくてもいいらしい。
緊張して、手が震えてきた。
だけど、ふしぎと恐怖はなかった。
これをやることで、いまわたしが抱えている、悩みやさみしさが、なくなるんじゃないか、という期待を、勝手に抱いていたんだと思う。
鍋のなかに、指示通りの材料を放りこんだ。
天然水、あら塩、ブラックペッパー、純正はちみつ、こんぺいとう。
それぞれを、思うようにいれる。
思うようにっていうのが、よくわからなかったけど、たまたま、ぜんぶ家にあったから助かった。
あとは……マジックペンで描いた、星のイラスト。
こんなんでいいのかな? と、思いつつ、鍋に投げ入れた。
まるで、魔法使いみたいなをことしてるなあ、と思った。
「燐くんに会える。そんな魔法だったら、いいのに」
失敗してはいけない緊張感で、手汗がすごい。
着ているフーディのすそで、汗を拭いつつ、鍋の中身を、くるくるとかき混ぜていく。
気づけば、一時間半も経っていた。
「えーと……一定のリズムでかき混ぜ続ける……すべて溶けきるまで、気をぬいてはならない……星のイラストは、溶けきらなくても問題はない……これで、いいんだよね。頭のなかに浮かんだとおりにやってるし、間違いはないと思うけど」
ここまでがんばったけど……失敗したら、どうなるんだろう。
何が起こるのかわからないことを続けるのは……こわい。
「でももし、これをやって、何かが変わったら」
いまの、何も手がつかない、ぬけがらみたいなわたしを変えてくれる何かが起こるとしたら……。
「続けてみよう。呪文を唱えれば、いったんはおわりだし……」
バクバクする心臓のリズムを抑えるように、深呼吸をした。
脳内にこびりつきそうなほどに浮かびあがっている呪文を、たどたどしく、ゆっくり読みあげていく。
「星よ、聴け――我が青き導力の煌めきを見よ。遠きアステルの導きに従い、生まれ出で、満ちよ」
とたん鍋のなかから、青の光がぶわりと舞いあがり、強い風が吹きはじめる。
激しい光に、思わず、腕で顔をおおった。
うっすら目を開けると、青い光のなかに、誰かが立っているのが見えた。
「燐くん……?」
しゅうう、と光が収まっていく。
少し離れたキッチンマットのうえに、誰かが立っている。
わたしと同い年くらいの男の子。
ウェーブがかった月光のような金髪に、切れ長の赤い瞳。
夜空色のスーツに、上品な革靴を履いている。
緊張がピークを過ぎたことで力がぬけたのか、わたしは床にぺたりと座りこんでしまった。
男の子の琥珀色の瞳が、そんなわたしを見つけて、コツコツと靴を鳴らし、近づいてくる。
「――待って。ここ、家のなかなんだけど!」
「はい?」
思わず叫ぶわたしに、男の子は小首を傾げる。
わたしが、靴を指さしているのを見て、「おや」と目を見開く。
「申し訳ありません。あなたの家は、靴を脱ぐ文化があるのですね」
「ふ……不審者?」
怪訝に顔をしかめるわたしに、男の子は苦笑する。
「——だったら、どうしますか? 叫びます?」
「うう……あなた急に現れたけど、どこからうちに入ったの?」
「あなたが行った星成術が成功したので、ぼくが財団本部からひとっ飛び、駆けつけただけですよ」
「は?」
「あなたの星成術は成功。ということで、ぶじに祝祭への登録は完了しました。ぼくは、それをお知らせにきたんです。導力を持っている星成士は今回、三人だけのようです。星成士も減りましたよねー。まあ、財団としては、願ったりかなったりで……」
「……えーと、ずっとなんの話?」
すると、男の子はきょとんとした顔をして、ふしぎそうにいう。
「六年後に行われる、アステル百年祝祭の話に決まってるじゃないですか」
「なにそれっ? 知らないよ!」
すると、男の子はまじまじとわたしの顔を見つめたあと、すぐに納得したように両手をポンと鳴らした。
「……あなたは、『星』に選ばれた星成士だったんですね。だから、自覚がない。これは財団としては――ひじょうに面倒ですねー?」
男の子が何をいっているのか、ひとつもわからない。
わたしは、ただただ茫然と、さっきまで触っていた鍋と、男の子を見比べていた。
「あなた、誰?」
「まずは、あなたの名前から、聞かせてくださいよ」
名前を聞きたいんなら、最初は自分から名乗るものなんじゃないのかな、とは思いつつも、いい返す元気がなくて、わたしはおとなしく答えることにした。
「……歌仙陽菜」
「歌仙くん! かわいい名前ですね」
じろじろと、わたしを観察してくる男の子。
平気でかわいいとかいってくるし、家には土足で入ってくるし、やっぱり不審者なのかな。
「あの、あなたの名前は?」
「ぼくは、セルヴァン=ズヴィズダー。代々、星成士であるズヴィズダー家の末裔で、アステル星成士財団の会長でもあります。けっこう偉い人なんですよ? あと、えげつないほどのお金持ちでもある! すごいでしょう?」
「あ、アステル星成士財団?」
「この世界にいる星成士をたばねている、でっかい組織ですね。いまは、ほとんど年寄りしかいないのが悩みです」
聞きなれない言葉ばかりで、わたしは頭のうえにハテナを浮びかう。
セルヴァン会長は、それを目ざとく察したみたいで、わたしの目をジッと、のぞきこんできた。
さっきから、この人、距離が近いよ……!
「あれ? お金持ちには、興味ありませんか?」
「話が見えないってだけ! さっきいってた、アステル百年祝祭とか、わたしがそれに選ばれた星成士とか……」
「そうか。いちから説明しないとですね。星成士とは、この世のエネルギーと自分の力をかけあわせ、あらゆるものを生み出すことのできる術士のことです」
「わたしが、それだっていうの?」
「ええ。そして、あなたを星成士として選んだのが、『星』という存在です」
「星……って、空に浮かんでいる星?」
「いいえ。それとはまた、違った存在です」
「それじゃあ、なんなの『星』って」
セルヴァン会長は、腕を組み、あらたまったように、ひと呼吸おいて、いった。
「星とは、この世に存在する、膨大な『自然エネルギー』の総称のことです。星は、意思を持ち、ぼくたちを異次元から見守っている。神さまみたいなもんだと思ってください」
小難しい説明に、わたしはますます頭がこんがらがる。
すると、セルヴァン会長はおかしそうに「ぷっ」と、吹き出した。
「まあ、すごい存在ってことですよ。話を続けますが――星の自然エネルギーは、この世を作り出すほどの強力なものなんです。そして、それは百年周期で、この世からあふれだしてしまう」
「それって……なんかヤバいの?」
「定期的に放出しないと、天変地異が起きます」
天変地異って、ふだん起こらないような自然災害だとか、異常なできごとのことをいうんだったよね。
それがほんとうだったら、かなり一大事だけど。
ようやく、わたしが、ことの重大さを理解できるようになってきたところで、セルヴァン会長がコホンと咳ばらいをした。
「そこで、星がもうけたのが、『アステル百年祝祭』なんです。星に選ばれた星成士だけが参加する祝祭。そして――」
セルヴァン会長はそっと、目を伏せた。
「アステル百年祝祭に勝ち残ったものは、星から放出された自然エネルギーの結晶である星の器――『アステル』を得ることができます」
「賞品みたいなもの?」
「わかりやすくいえば、そうです。それは、星成士たちにとって、無限の力を手に入れたことと同じ。すべての星成士たちが、この祝祭に参加することを願ってやまない——というわけです。どうですか? ご理解いただけましたか?」
頭では、なんとなくわかった。
心が追いついてないけど。
でも、そんなことよりも――聞きたいことがある。
「なんでそれに、わたしが選ばれたの……?」
セルヴァンは、あごに手を添えると、おもしろそうに歯を見せて笑った。
「あなたもぼくたちと同じ、導力を持っているようです」
「どーりょく?」
「星成士だけが持つ力のことです。魔術師の魔力みたいなものですよ。家系から生まれたわけでもないのに――これは、運命的な何かを感じます!」
興奮気味にいう、セルヴァン会長。
対して、わたしの心は冷めきっていた。
へんなことに巻きこまれはじめている気配。
鍋まで引っ張り出してがんばったのに、こんなことになるなんて。
「そんなもの、わたし参加しません」
「まあ、聞いて。選ばれたのには、もうひとつ理由があるようですよ」
「もう……なんなんですか」
「今回のアステル百年祝祭の『アステル』とあなたは、深い縁があるようです」
アステルとかいうのと、わたしが深い縁?
そんな記憶まったくなくて、わたしは半信半疑で聞いていた。
「意味が解らな――」
「星が、教えてくれました。今回の祝祭では、佐々波燐という人間が、『星の器』に選ばれた……と」
それを聞いたとたん、わたしの頭のなかは、いよいよ真っ白になってしまった。
「アステル百年祝祭は、今日から六年後です。それまでに、強くなっておかないといけませんね。六年後、あなたのライバルの星成士たちは、問答無用で佐々波燐に襲い掛るでしょう。佐々波燐……いや、アステルを、じぶんのものにするために」
幼稚園の年長クラス、夏が終わりがけのころだった。
燐くんの病気は、とても深刻なものだったみたいで。
海外への引っ越しも、もっといい環境で治療を受けるためのもの。
通っていた幼稚園は、だいたいいつも休みがちで、園庭での運動や遊びには参加せず、いつも見学だった。
幼稚園がおわったあと、他の子から家に招待されたり、近所での遊びに誘われても、いつもさみしそうに断っていた。
でも、わたしが誘うと、うれしそうな顔をしてくれた。
「ぼくのからだのことをわかってくれてる陽菜ちゃんなら、お母さんも許してくれると思う。帰ったら、聞いてみる」
燐くんと遊ぶのはとても楽しいから、そういってくれるのが、すごく嬉しかった。
いっしょに遊ぶ時間があっというまで、家に帰る時間になっても燐くんと別れるのはいつだってさみしかった。
てっきり、いっしょに小学校にあがるんだと思っていたのに――。
引っ越すことを告げられたときは、悲しくてさみしくて、またわたしは、わんわん泣いちゃって、燐くんを困らせた。
でも、すぐに燐くんもいっしょに泣きはじめちゃって。
いつも遊んでいた燐くんの部屋で、ふたりして、大泣きした。
さんざん泣いたあとは、手をつないで、窓の外から、夕陽をながめた。
いつまでも、この時間がおわらなければいいのに、って思ったんだ。
その次の日。
燐くんは、海外へ引っ越していった。
引っ越し当日、燐くんはお父さんが運転する車の窓から顔を出して、ずっと手を振ってくれた。
わたしも、ずっとずっと、手を振っていた。
小学校に入学しても、わたしはしばらく、燐くんとの別れから、立ち直れない日々が続いていた。
運命を変えるあの日がやってきたのは、小学一年の秋だった。
その日は、短縮授業だった。
「……痛っ!」
誰もいない家のなか、いきなり頭のなかがズキン、と痛んだ。
ズキン、ズキンと頭の痛みに必死で耐えていると、おかしな現象がはじまった。
じわじわと脳内に、へんな指示みたいなものが流れこんでくる。
いったい、何が起こってるの――。
心臓が、ばくばくと跳ねあがっていく。
ただ、指示の通りにしないといけない。
そう、思った。
わけがわからないまま、わたしは家を飛び出すと、キッチンへと走った。
キッチンのシンク下の棚から、大きな鍋を取り出し、コンロの上に置いた。
火は、つけなくてもいいらしい。
緊張して、手が震えてきた。
だけど、ふしぎと恐怖はなかった。
これをやることで、いまわたしが抱えている、悩みやさみしさが、なくなるんじゃないか、という期待を、勝手に抱いていたんだと思う。
鍋のなかに、指示通りの材料を放りこんだ。
天然水、あら塩、ブラックペッパー、純正はちみつ、こんぺいとう。
それぞれを、思うようにいれる。
思うようにっていうのが、よくわからなかったけど、たまたま、ぜんぶ家にあったから助かった。
あとは……マジックペンで描いた、星のイラスト。
こんなんでいいのかな? と、思いつつ、鍋に投げ入れた。
まるで、魔法使いみたいなをことしてるなあ、と思った。
「燐くんに会える。そんな魔法だったら、いいのに」
失敗してはいけない緊張感で、手汗がすごい。
着ているフーディのすそで、汗を拭いつつ、鍋の中身を、くるくるとかき混ぜていく。
気づけば、一時間半も経っていた。
「えーと……一定のリズムでかき混ぜ続ける……すべて溶けきるまで、気をぬいてはならない……星のイラストは、溶けきらなくても問題はない……これで、いいんだよね。頭のなかに浮かんだとおりにやってるし、間違いはないと思うけど」
ここまでがんばったけど……失敗したら、どうなるんだろう。
何が起こるのかわからないことを続けるのは……こわい。
「でももし、これをやって、何かが変わったら」
いまの、何も手がつかない、ぬけがらみたいなわたしを変えてくれる何かが起こるとしたら……。
「続けてみよう。呪文を唱えれば、いったんはおわりだし……」
バクバクする心臓のリズムを抑えるように、深呼吸をした。
脳内にこびりつきそうなほどに浮かびあがっている呪文を、たどたどしく、ゆっくり読みあげていく。
「星よ、聴け――我が青き導力の煌めきを見よ。遠きアステルの導きに従い、生まれ出で、満ちよ」
とたん鍋のなかから、青の光がぶわりと舞いあがり、強い風が吹きはじめる。
激しい光に、思わず、腕で顔をおおった。
うっすら目を開けると、青い光のなかに、誰かが立っているのが見えた。
「燐くん……?」
しゅうう、と光が収まっていく。
少し離れたキッチンマットのうえに、誰かが立っている。
わたしと同い年くらいの男の子。
ウェーブがかった月光のような金髪に、切れ長の赤い瞳。
夜空色のスーツに、上品な革靴を履いている。
緊張がピークを過ぎたことで力がぬけたのか、わたしは床にぺたりと座りこんでしまった。
男の子の琥珀色の瞳が、そんなわたしを見つけて、コツコツと靴を鳴らし、近づいてくる。
「――待って。ここ、家のなかなんだけど!」
「はい?」
思わず叫ぶわたしに、男の子は小首を傾げる。
わたしが、靴を指さしているのを見て、「おや」と目を見開く。
「申し訳ありません。あなたの家は、靴を脱ぐ文化があるのですね」
「ふ……不審者?」
怪訝に顔をしかめるわたしに、男の子は苦笑する。
「——だったら、どうしますか? 叫びます?」
「うう……あなた急に現れたけど、どこからうちに入ったの?」
「あなたが行った星成術が成功したので、ぼくが財団本部からひとっ飛び、駆けつけただけですよ」
「は?」
「あなたの星成術は成功。ということで、ぶじに祝祭への登録は完了しました。ぼくは、それをお知らせにきたんです。導力を持っている星成士は今回、三人だけのようです。星成士も減りましたよねー。まあ、財団としては、願ったりかなったりで……」
「……えーと、ずっとなんの話?」
すると、男の子はきょとんとした顔をして、ふしぎそうにいう。
「六年後に行われる、アステル百年祝祭の話に決まってるじゃないですか」
「なにそれっ? 知らないよ!」
すると、男の子はまじまじとわたしの顔を見つめたあと、すぐに納得したように両手をポンと鳴らした。
「……あなたは、『星』に選ばれた星成士だったんですね。だから、自覚がない。これは財団としては――ひじょうに面倒ですねー?」
男の子が何をいっているのか、ひとつもわからない。
わたしは、ただただ茫然と、さっきまで触っていた鍋と、男の子を見比べていた。
「あなた、誰?」
「まずは、あなたの名前から、聞かせてくださいよ」
名前を聞きたいんなら、最初は自分から名乗るものなんじゃないのかな、とは思いつつも、いい返す元気がなくて、わたしはおとなしく答えることにした。
「……歌仙陽菜」
「歌仙くん! かわいい名前ですね」
じろじろと、わたしを観察してくる男の子。
平気でかわいいとかいってくるし、家には土足で入ってくるし、やっぱり不審者なのかな。
「あの、あなたの名前は?」
「ぼくは、セルヴァン=ズヴィズダー。代々、星成士であるズヴィズダー家の末裔で、アステル星成士財団の会長でもあります。けっこう偉い人なんですよ? あと、えげつないほどのお金持ちでもある! すごいでしょう?」
「あ、アステル星成士財団?」
「この世界にいる星成士をたばねている、でっかい組織ですね。いまは、ほとんど年寄りしかいないのが悩みです」
聞きなれない言葉ばかりで、わたしは頭のうえにハテナを浮びかう。
セルヴァン会長は、それを目ざとく察したみたいで、わたしの目をジッと、のぞきこんできた。
さっきから、この人、距離が近いよ……!
「あれ? お金持ちには、興味ありませんか?」
「話が見えないってだけ! さっきいってた、アステル百年祝祭とか、わたしがそれに選ばれた星成士とか……」
「そうか。いちから説明しないとですね。星成士とは、この世のエネルギーと自分の力をかけあわせ、あらゆるものを生み出すことのできる術士のことです」
「わたしが、それだっていうの?」
「ええ。そして、あなたを星成士として選んだのが、『星』という存在です」
「星……って、空に浮かんでいる星?」
「いいえ。それとはまた、違った存在です」
「それじゃあ、なんなの『星』って」
セルヴァン会長は、腕を組み、あらたまったように、ひと呼吸おいて、いった。
「星とは、この世に存在する、膨大な『自然エネルギー』の総称のことです。星は、意思を持ち、ぼくたちを異次元から見守っている。神さまみたいなもんだと思ってください」
小難しい説明に、わたしはますます頭がこんがらがる。
すると、セルヴァン会長はおかしそうに「ぷっ」と、吹き出した。
「まあ、すごい存在ってことですよ。話を続けますが――星の自然エネルギーは、この世を作り出すほどの強力なものなんです。そして、それは百年周期で、この世からあふれだしてしまう」
「それって……なんかヤバいの?」
「定期的に放出しないと、天変地異が起きます」
天変地異って、ふだん起こらないような自然災害だとか、異常なできごとのことをいうんだったよね。
それがほんとうだったら、かなり一大事だけど。
ようやく、わたしが、ことの重大さを理解できるようになってきたところで、セルヴァン会長がコホンと咳ばらいをした。
「そこで、星がもうけたのが、『アステル百年祝祭』なんです。星に選ばれた星成士だけが参加する祝祭。そして――」
セルヴァン会長はそっと、目を伏せた。
「アステル百年祝祭に勝ち残ったものは、星から放出された自然エネルギーの結晶である星の器――『アステル』を得ることができます」
「賞品みたいなもの?」
「わかりやすくいえば、そうです。それは、星成士たちにとって、無限の力を手に入れたことと同じ。すべての星成士たちが、この祝祭に参加することを願ってやまない——というわけです。どうですか? ご理解いただけましたか?」
頭では、なんとなくわかった。
心が追いついてないけど。
でも、そんなことよりも――聞きたいことがある。
「なんでそれに、わたしが選ばれたの……?」
セルヴァンは、あごに手を添えると、おもしろそうに歯を見せて笑った。
「あなたもぼくたちと同じ、導力を持っているようです」
「どーりょく?」
「星成士だけが持つ力のことです。魔術師の魔力みたいなものですよ。家系から生まれたわけでもないのに――これは、運命的な何かを感じます!」
興奮気味にいう、セルヴァン会長。
対して、わたしの心は冷めきっていた。
へんなことに巻きこまれはじめている気配。
鍋まで引っ張り出してがんばったのに、こんなことになるなんて。
「そんなもの、わたし参加しません」
「まあ、聞いて。選ばれたのには、もうひとつ理由があるようですよ」
「もう……なんなんですか」
「今回のアステル百年祝祭の『アステル』とあなたは、深い縁があるようです」
アステルとかいうのと、わたしが深い縁?
そんな記憶まったくなくて、わたしは半信半疑で聞いていた。
「意味が解らな――」
「星が、教えてくれました。今回の祝祭では、佐々波燐という人間が、『星の器』に選ばれた……と」
それを聞いたとたん、わたしの頭のなかは、いよいよ真っ白になってしまった。
「アステル百年祝祭は、今日から六年後です。それまでに、強くなっておかないといけませんね。六年後、あなたのライバルの星成士たちは、問答無用で佐々波燐に襲い掛るでしょう。佐々波燐……いや、アステルを、じぶんのものにするために」