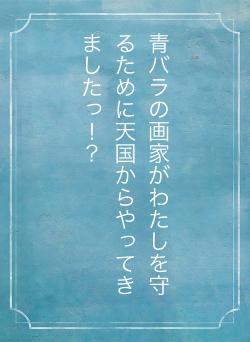スピーカーから、聞き慣れたチャイムが鳴った。
ホームルームが、はじまる。
しばらくして、担任の可児先生が転校生を連れて、教室に入ってきた。
燐くんだ! 転校初日なのに、まったく緊張してないみたい。
「はーい、静かに。今日は、転校生を紹介します。みなさんの新しいクラスメイトですよー」
クラスの女子たちが、「わあっ」と声をあげた。
色白で整った顔立ち、猫のような吊り目の燐くん。
さらに、宝井中学校の斬新なデザインの制服をクールに着こなしたすがたは、まるでモデルみたいだった。
「めっちゃイケメンじゃないっ?」、「肌きれーい!」、「アイドルみたいっ」とそこかしこから、歓声があがる。
すると、燐くんが教室をきょろきょろと見渡しはじめた。
わたしと視線がピッタリあうと、にこっとほほえんでくれる。
あのころと、変わらない笑顔に嬉しくなってしまう。
先生は、教卓の隣に燐くんを立たせ、黒板に彼の名前を書いた。
「じゃあ、佐々波くん。自己紹介をしてください」
「……はい。佐々波燐です。六年間、海外に住んでいましたが、英語の成績は特別いいってわけじゃないと思います。よろしくお願いします」
燐くんの自己紹介に、どっと笑いが起きた。
「じゃあ佐々波くんの席はー、歌仙さんの隣ね」
急に、可児先生に名前を呼ばれて、ドキッと肩を揺らした。
すると、燐くんがじんわりとした笑みを浮かべ、わたしの席にやってきた。
「ぼく、陽菜の隣の席だって」
燐くんは、にっこりとほほ笑んで、わたしの隣の席に座った。
わたしの隣の席が、燐くんか。
こんな日がくるなんて、嬉しいな。
「よろしく」
「うん、よろしくね」
とたん、クラス中が、どよめきだした。
「えっ! ふたりとも、知り合いなのっ?」
わたしの前の席の、柚希が驚いたようすで振り返ってきた。
どう答えようかと迷っていると、燐くんが席から身を乗り出して、ぶっきらぼうにいう。
「知り合いじゃない。幼なじみ」
「ええーっ! 佐々波くん、むかし宝井町に住んでたの?」
「そんなに驚くこと? というか、きみ誰? 初対面なんだから、せめて自己紹介くらいしてから、話しかけるべきじゃない?」
とたん、教室中がシーンとなる。
忘れてた。
燐くんって、わたし以外にはなぜか、こんな態度なんだよね。
中学生になっても、それは変わらないみたい。
「あはは! ごめん、ごめん! あたし、夏野柚希! よろしく〜っ」
それでも、柚希だけはまったく気にしていないみたいで、ハイテンションで逆ピースをして燐くんに応えた。
わたしがホッとしたのも束の間、柚希はどんどん燐くんのほうへと身を乗り出す。
「なになに〜ふたりは家近いの?」
「……近いけど、それがなに」
「佐々波くんは、いつぶりにこっちに戻ってきたわけ?」
「小学校にあがる前に引っ越したから、六年ぶり」
「そうだったんだーっ。なんかすごーい! ドラマチック的な?」
柚希はいつもの調子で、目をきらきらさせながら、わたしのほうを向いた。
柚希はアイドルの推し活をやっていて、よくわたしにその話をしてくれる。
推しのどこがいいのか、というところを、ものすごい熱量で話してくれる。
ノリがよくて、話してて気持ちがいいから、大すきな友達なんだ。
すると、燐くんがこそっとわたしに耳打ちをしてきた。
「陽菜」
「どうしたの?」
「ぼく、まだ教科書もらってないんだ。……いっしょに見せて」
「いいよ!」
いまの柚希の盛りあがりのせいか、クラスの女子たちみんな、きらきらした目で燐くんのことを見てる。
たしかに燐くん、カッコいいもんなあ。
「……なに?」
「え?」
「こっち、ジッと見てる。ぼくの顔、なんかついてる?」
「いや、燐くんはあいかわらず、モテるなあと思って」
「へえ。それで?」
「それでって?」
「……はあ」
えっ、ため息つかれちゃった。
わたし、変なことでもいったのかな。
「モテたくないひとたちに、モテたところで、何になるの? ちっとも、うれしくない」
「そうなのかな。人気なのは、いいことじゃない?」
「――ある特定の人からの人気がないと、ぼくとしては意味がない」
一気に、機嫌がわるくなってしまった、燐くん。
でも、教科書をいっしょに見るために、机をくっつけようとしたら、燐くんのほうから寄ってきてくれた。
怒ってはないみたい?
一時限目がおわった、休み時間。
女子たちが、燐くんの席のまわりに集まりはじめた。
教室の廊下にも、燐くんを見に来たらしい、女子の集団がいる。
噂が広まるの、早いなあ。
「陽菜」
隣の席から燐くんが手を伸ばし、わたしの机を人さし指で、トントンと突いた。
「燐くん。なに?」
「学校、案内して」
「え? わたし?」
「あたりまえ。きみじゃなくて、誰がやるの」
そういって立ちあがった燐くんは、パッとわたしの手を掴む。
あっというまに、わたしを廊下へと引っ張っていくと、女の子たちのざわめきがいっそう激しくなる。
でも、燐くんはそんなのおかまいなしみたいで。
わたしの手をぐいぐい引っ張っていく燐くんは、上機嫌だった。
子どものころの、病弱だった面影は、もうほとんどない。
「燐くん。ほんとうに、元気になったね」
「うん。だから、こっちに戻ってきたんだよ」
「よかった」
「……心配、かけてたよね。ごめん」
北側、いちばん奥にある家庭科室。
その手前の階段から、旧校舎の屋上へ行ける。
燐くんが、ドアノブを掴んで、ガチャリと回した。
扉が開かれると、秋の涼やかな風が、わたしの頬をさらりと撫ぜた。
屋上に入ったとたん、わたしたちの頭上いっぱいに、さわやかな青空が広がる。
空気を吸いこむと、からだじゅうに、秋のかおりが染みわたっていく。
あのときの金色の雨が、いまにも降りだしそうな空で、懐かしさに胸が詰まりそうになる。
隣から「ふう」と、息をつくのが聞こえた。
燐くんも、すべてから解放されたかのような清々しい表情で、秋空を見あげていた。
「地元の景色、一望だ」
「燐くんにとっては、六年ぶりの景色だもんね」
「陽菜」
「ん?」
「……ぼくのいない六年間、どう過ごしてた?」
「え。どうって?」
「ぼくは」
燐くんは辛そうに、まゆを歪め、わたしをじっと見つめた。
「ずっと、宝井町に帰りたいと思ってた。情けないけど、アメリカにいても、宝井町のことを忘れることなんて、できなかった。何をしていても、陽菜といっしょだったら、もっと楽しかったのにって、考えてしまうんだ。陽菜のことを忘れた日なんてなかったよ」
「わたしだって、燐くんのことを忘れたことなんてなかったよ」
だって、わたしの六年は——。
でも、それをいま、燐くんにいうことはできない。
燐くんにいったら、きっと、心配かけちゃう。
「ねえ、燐くん。昨日、あげた石……」
「ああ、ちゃんと持ってるよ。あたりまえでしょ」
燐くんは、首から下げていたペンダントを、制服のなかから、するりと出した。
シルクのヒモで編まれたペンダントホルダーになっていて、ペンダントトップの部分に石を入れられるようになっている。
わたしの導力で作った青い星成石が、朝の太陽の光に照らされて、燐くんの胸元で光っている。
「すごい。ペンダントにしてくれたんだ」
「うん。ぼく、こういうのすきだから」
「えっ。このペンダントホルダー、燐くんが作ったの? すごい! 昔から、器用だったもんね」
「そんなにむずかしいものじゃない。気に入ったんなら、こんど陽菜にも作ってあげる」
「ほんと? やった!」
「ところで」
首からさげたペンダントを制服のなかにしまいながら、燐くんがまじめな顔をしていう。
「きみさ……この石、どこで買ったの?」
「え?」
「高かったんじゃない?」
「い、いやいや……」
というか、これは買えるものじゃない。
わたしの導力で作った石だし……。
「ふうん。じゃあ、シーグラスみたいに、砂浜でひろったの?」
「う、うーん……」
「……陽菜」
「えっ」
「まさか……ぼくに隠しごとしてる?」
「してないってばっ」
思わず、心臓がバクンと跳ねて、大きな声になってしまう。
燐くんの顔が見れない。
でも、こんな態度、変に思われちゃうよ。
あからさまに、視線を泳がせているわたしに、燐くんは「ふう」と息をついた。
あ、呆れられちゃった……?
「陽菜」
「あ……あの」
「きみ、再会してから、ずっとぼくのこと、心配そうに見てる」
まだ夏の気配の残る湿った風が、青葉をつけた桜の木をざわりと揺らした。
「ぼく、そんなに陽菜に心配かけたんだね。ごめん」
「今朝、燐くん、いってくれてたでしょ?」
燐くんは、かなしそうに眉をさげて、わたしを見つめている。
「もっともっと、ふたりで思い出を作りたかったって……。わたしだって、同じ気持ちだったんだよ」
すると、燐くんはグッとなにかをこらえるような表情で、顔を赤らめた。
それを見て、つられてわたしの顔も熱くなる。
秋の涼しい風が、わたしたちの頬にふわりと吹いた。
「あのさ……この青い石、つけてると……ふしぎな気持ちになるんだ」
「ふしぎな、気持ち?」
「そばに、陽菜がいるような気がして、ひとりじゃないって気持ちになれる。だから、むりして買ったんなら、申し訳ないって思ったんだ」
「そんなこと……」
「でも、陽菜が気にする必要ないっていうんなら、いい。この石、ずっと大切にする。きみがぼくに、くれたものだから」
燐くんが、わたしに向かって、うれしそうに目を細めた。
制服に隠れたペンダントトップのあたりで、そっと手を握ってくれる。
わたしがそばにいるような……って。
じんわりと、嬉しさがこみあげる。
燐くん、わたしの導力を感じ取ってくれてるってことだよね。
でも、星成士でもないのに、導力を感じとることができるなんて。
やっぱり、燐くんは『星に選ばれたアステル』なんだ――と思ってしまって、胸の奥がざわめいた。
ホームルームが、はじまる。
しばらくして、担任の可児先生が転校生を連れて、教室に入ってきた。
燐くんだ! 転校初日なのに、まったく緊張してないみたい。
「はーい、静かに。今日は、転校生を紹介します。みなさんの新しいクラスメイトですよー」
クラスの女子たちが、「わあっ」と声をあげた。
色白で整った顔立ち、猫のような吊り目の燐くん。
さらに、宝井中学校の斬新なデザインの制服をクールに着こなしたすがたは、まるでモデルみたいだった。
「めっちゃイケメンじゃないっ?」、「肌きれーい!」、「アイドルみたいっ」とそこかしこから、歓声があがる。
すると、燐くんが教室をきょろきょろと見渡しはじめた。
わたしと視線がピッタリあうと、にこっとほほえんでくれる。
あのころと、変わらない笑顔に嬉しくなってしまう。
先生は、教卓の隣に燐くんを立たせ、黒板に彼の名前を書いた。
「じゃあ、佐々波くん。自己紹介をしてください」
「……はい。佐々波燐です。六年間、海外に住んでいましたが、英語の成績は特別いいってわけじゃないと思います。よろしくお願いします」
燐くんの自己紹介に、どっと笑いが起きた。
「じゃあ佐々波くんの席はー、歌仙さんの隣ね」
急に、可児先生に名前を呼ばれて、ドキッと肩を揺らした。
すると、燐くんがじんわりとした笑みを浮かべ、わたしの席にやってきた。
「ぼく、陽菜の隣の席だって」
燐くんは、にっこりとほほ笑んで、わたしの隣の席に座った。
わたしの隣の席が、燐くんか。
こんな日がくるなんて、嬉しいな。
「よろしく」
「うん、よろしくね」
とたん、クラス中が、どよめきだした。
「えっ! ふたりとも、知り合いなのっ?」
わたしの前の席の、柚希が驚いたようすで振り返ってきた。
どう答えようかと迷っていると、燐くんが席から身を乗り出して、ぶっきらぼうにいう。
「知り合いじゃない。幼なじみ」
「ええーっ! 佐々波くん、むかし宝井町に住んでたの?」
「そんなに驚くこと? というか、きみ誰? 初対面なんだから、せめて自己紹介くらいしてから、話しかけるべきじゃない?」
とたん、教室中がシーンとなる。
忘れてた。
燐くんって、わたし以外にはなぜか、こんな態度なんだよね。
中学生になっても、それは変わらないみたい。
「あはは! ごめん、ごめん! あたし、夏野柚希! よろしく〜っ」
それでも、柚希だけはまったく気にしていないみたいで、ハイテンションで逆ピースをして燐くんに応えた。
わたしがホッとしたのも束の間、柚希はどんどん燐くんのほうへと身を乗り出す。
「なになに〜ふたりは家近いの?」
「……近いけど、それがなに」
「佐々波くんは、いつぶりにこっちに戻ってきたわけ?」
「小学校にあがる前に引っ越したから、六年ぶり」
「そうだったんだーっ。なんかすごーい! ドラマチック的な?」
柚希はいつもの調子で、目をきらきらさせながら、わたしのほうを向いた。
柚希はアイドルの推し活をやっていて、よくわたしにその話をしてくれる。
推しのどこがいいのか、というところを、ものすごい熱量で話してくれる。
ノリがよくて、話してて気持ちがいいから、大すきな友達なんだ。
すると、燐くんがこそっとわたしに耳打ちをしてきた。
「陽菜」
「どうしたの?」
「ぼく、まだ教科書もらってないんだ。……いっしょに見せて」
「いいよ!」
いまの柚希の盛りあがりのせいか、クラスの女子たちみんな、きらきらした目で燐くんのことを見てる。
たしかに燐くん、カッコいいもんなあ。
「……なに?」
「え?」
「こっち、ジッと見てる。ぼくの顔、なんかついてる?」
「いや、燐くんはあいかわらず、モテるなあと思って」
「へえ。それで?」
「それでって?」
「……はあ」
えっ、ため息つかれちゃった。
わたし、変なことでもいったのかな。
「モテたくないひとたちに、モテたところで、何になるの? ちっとも、うれしくない」
「そうなのかな。人気なのは、いいことじゃない?」
「――ある特定の人からの人気がないと、ぼくとしては意味がない」
一気に、機嫌がわるくなってしまった、燐くん。
でも、教科書をいっしょに見るために、机をくっつけようとしたら、燐くんのほうから寄ってきてくれた。
怒ってはないみたい?
一時限目がおわった、休み時間。
女子たちが、燐くんの席のまわりに集まりはじめた。
教室の廊下にも、燐くんを見に来たらしい、女子の集団がいる。
噂が広まるの、早いなあ。
「陽菜」
隣の席から燐くんが手を伸ばし、わたしの机を人さし指で、トントンと突いた。
「燐くん。なに?」
「学校、案内して」
「え? わたし?」
「あたりまえ。きみじゃなくて、誰がやるの」
そういって立ちあがった燐くんは、パッとわたしの手を掴む。
あっというまに、わたしを廊下へと引っ張っていくと、女の子たちのざわめきがいっそう激しくなる。
でも、燐くんはそんなのおかまいなしみたいで。
わたしの手をぐいぐい引っ張っていく燐くんは、上機嫌だった。
子どものころの、病弱だった面影は、もうほとんどない。
「燐くん。ほんとうに、元気になったね」
「うん。だから、こっちに戻ってきたんだよ」
「よかった」
「……心配、かけてたよね。ごめん」
北側、いちばん奥にある家庭科室。
その手前の階段から、旧校舎の屋上へ行ける。
燐くんが、ドアノブを掴んで、ガチャリと回した。
扉が開かれると、秋の涼やかな風が、わたしの頬をさらりと撫ぜた。
屋上に入ったとたん、わたしたちの頭上いっぱいに、さわやかな青空が広がる。
空気を吸いこむと、からだじゅうに、秋のかおりが染みわたっていく。
あのときの金色の雨が、いまにも降りだしそうな空で、懐かしさに胸が詰まりそうになる。
隣から「ふう」と、息をつくのが聞こえた。
燐くんも、すべてから解放されたかのような清々しい表情で、秋空を見あげていた。
「地元の景色、一望だ」
「燐くんにとっては、六年ぶりの景色だもんね」
「陽菜」
「ん?」
「……ぼくのいない六年間、どう過ごしてた?」
「え。どうって?」
「ぼくは」
燐くんは辛そうに、まゆを歪め、わたしをじっと見つめた。
「ずっと、宝井町に帰りたいと思ってた。情けないけど、アメリカにいても、宝井町のことを忘れることなんて、できなかった。何をしていても、陽菜といっしょだったら、もっと楽しかったのにって、考えてしまうんだ。陽菜のことを忘れた日なんてなかったよ」
「わたしだって、燐くんのことを忘れたことなんてなかったよ」
だって、わたしの六年は——。
でも、それをいま、燐くんにいうことはできない。
燐くんにいったら、きっと、心配かけちゃう。
「ねえ、燐くん。昨日、あげた石……」
「ああ、ちゃんと持ってるよ。あたりまえでしょ」
燐くんは、首から下げていたペンダントを、制服のなかから、するりと出した。
シルクのヒモで編まれたペンダントホルダーになっていて、ペンダントトップの部分に石を入れられるようになっている。
わたしの導力で作った青い星成石が、朝の太陽の光に照らされて、燐くんの胸元で光っている。
「すごい。ペンダントにしてくれたんだ」
「うん。ぼく、こういうのすきだから」
「えっ。このペンダントホルダー、燐くんが作ったの? すごい! 昔から、器用だったもんね」
「そんなにむずかしいものじゃない。気に入ったんなら、こんど陽菜にも作ってあげる」
「ほんと? やった!」
「ところで」
首からさげたペンダントを制服のなかにしまいながら、燐くんがまじめな顔をしていう。
「きみさ……この石、どこで買ったの?」
「え?」
「高かったんじゃない?」
「い、いやいや……」
というか、これは買えるものじゃない。
わたしの導力で作った石だし……。
「ふうん。じゃあ、シーグラスみたいに、砂浜でひろったの?」
「う、うーん……」
「……陽菜」
「えっ」
「まさか……ぼくに隠しごとしてる?」
「してないってばっ」
思わず、心臓がバクンと跳ねて、大きな声になってしまう。
燐くんの顔が見れない。
でも、こんな態度、変に思われちゃうよ。
あからさまに、視線を泳がせているわたしに、燐くんは「ふう」と息をついた。
あ、呆れられちゃった……?
「陽菜」
「あ……あの」
「きみ、再会してから、ずっとぼくのこと、心配そうに見てる」
まだ夏の気配の残る湿った風が、青葉をつけた桜の木をざわりと揺らした。
「ぼく、そんなに陽菜に心配かけたんだね。ごめん」
「今朝、燐くん、いってくれてたでしょ?」
燐くんは、かなしそうに眉をさげて、わたしを見つめている。
「もっともっと、ふたりで思い出を作りたかったって……。わたしだって、同じ気持ちだったんだよ」
すると、燐くんはグッとなにかをこらえるような表情で、顔を赤らめた。
それを見て、つられてわたしの顔も熱くなる。
秋の涼しい風が、わたしたちの頬にふわりと吹いた。
「あのさ……この青い石、つけてると……ふしぎな気持ちになるんだ」
「ふしぎな、気持ち?」
「そばに、陽菜がいるような気がして、ひとりじゃないって気持ちになれる。だから、むりして買ったんなら、申し訳ないって思ったんだ」
「そんなこと……」
「でも、陽菜が気にする必要ないっていうんなら、いい。この石、ずっと大切にする。きみがぼくに、くれたものだから」
燐くんが、わたしに向かって、うれしそうに目を細めた。
制服に隠れたペンダントトップのあたりで、そっと手を握ってくれる。
わたしがそばにいるような……って。
じんわりと、嬉しさがこみあげる。
燐くん、わたしの導力を感じ取ってくれてるってことだよね。
でも、星成士でもないのに、導力を感じとることができるなんて。
やっぱり、燐くんは『星に選ばれたアステル』なんだ――と思ってしまって、胸の奥がざわめいた。