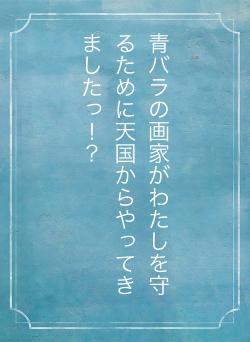あれからも、燐くんとわたしの関係は、少しも変わっていない。
むしろ、前よりも関係が近くなったような感じがしてる。
時任先輩は、校舎の廊下で戦って以来、学校を休んでいるらしい。
竜胆先輩にいたっては、実は、二年生の二学期からずっと不登校なんだって。
三年生に進級してからも、竜胆先輩のすがたは滅多に見ないみたい。
同じ学年じゃないから、ちっとも知らなかった。
下校しようと席から立ちあがったわたしに、燐くんがいった。
「陽菜、いっしょに帰……」
燐くんが何かをいいかけたとき、後ろから誰かがあいだに、割りこんで来た。
「――歌仙くん。見てください、これ!」
聞き慣れた声に驚いて、見あげると、セルヴァン会長が、満開の笑顔で着ているものを見せつけてきた。
いつもの夜空色のスーツではなく、宝井中学の制服を着た会長が、得意げに両腕を広げている。
しかも、光の術を使ってない。
どうどうと、学校の廊下にすがたを現してる。
燐くんが、「はあ?」と呆れたようにいった。
「きみ、なんでうちの制服着てんの」
「アステル。ただただ、目の前の事実を受け入れ、ぼくのこのすがたを褒めてはくれないんですか?」
「あいかわらず、面倒くさい」
燐くんとセルヴァンのいい争いがはじまると、ふたりの存在に気づいた周りの生徒たちが、ざわざわと騒ぎはじめた。
「ちょっと、あそこにいる金髪の人、めっちゃかっこよくないっ? あんな人、うちの学校にいたっけ? 何年生なんだろ~?」
「先輩じゃない? うちの学年にはいないよ~見たことないもん」
「佐々波くんの知り合いなのかな? あとで、聞いてみよっかっ?」
女の子たちのきゃあきゃあという、歓声があがりはじめた。
わたしは、あわてて、ふたりの手を取る。
「ちょっと、帰るならはやく帰ろう。ふたりのせいで、めちゃくちゃ目立ってるよ」
「目立つと、だめなんですか?」
ふしぎそうにいうセルヴァン会長に、燐くんが再び噛みつく。
「その制服、どうしたの」
「落ちてたんです。だから、ふたりといっしょの恰好になれたんですよっ。すてきでしょう?」
「――落ちてたって……そんなわけ」
不審そうにつぶやく、燐くん。
そのとき、少し離れた一年五組の教室から、困ったような大声が聞こえてきた。
「あれー? おれの制服知らねえ?」
「知らねえよ。掃除の時間で、わざわざ体操服に着替えたんかよ」
「だって、今日裏庭の側溝掃除だったからさー。制服汚れるのいやだったんだよ。おっかしいなー。机のうえに置いといたんだけど」
「おまえ、雑に置いて、よく床に落としてるから、風で飛んでったんじゃね?」
聞こえた話の内容に、わたしと燐くんは、思わず顔を見あわせた。
セルヴァン会長の手をふたりで、ガッと掴む。
ふしぎそうにしているセルヴァン会長をそのまま屋上への階段まで、引きずっていった。
最上段のところで手を放すと、燐くんがセルヴァン会長の胸元を、ぐいっと掴む。
「さっさと返してきて」
「ええっ? 返す? どうしてですか?」
「それ、落ちてたんじゃない。誰かの制服」
燐くんにお説教をされた、セルヴァン会長はつまらなさそうに、くちびるを曲げた。
不満そうに、パチンとフィンガースナップをすると、会長の制服は一瞬にして、もとの夜空色のスーツに変わる。
手には、ちゃんと畳んだ制服を持っていた。
燐くんが、諭すようにもう一度うながす。
「ほら、さっさと行く」
「わかりましたよ。そんなに、怒らないでくださいってば」
光の術で自分のすがたを消したセルヴァン会長の気配が、じょじょに遠のいていく。
燐くんは、呆れたといわんばかりに、ため息をついた。
「陽菜、ずっとあの人と修行してたんでしょ。大変だったんじゃない」
「セルヴァン会長は、自由だから」
昔っからあんな調子だから、わたしは慣れっこだけど、燐くんはずっと信じられないものを見たって顔してる。
くすくすと笑っていると、ふいに、会長との厳しい修行風景が脳裏によみがえる。
はじめて、術が成功したときのこと。
星成石の生成が、うまくいかなかったときのこと。
そして、自分の寿命を使って、導力を使うやり方を教わったときのこと。
「いろいろあったけど、ここまで来られたのは、セルヴァン会長がいてくれたからだからさ」
「――その人がいなければ、陽菜はこんなことに巻きこまれなかったじゃないか……」
燐くんが、ぼそっとなにかをいったように思ったけれど、わたしにはよく聞こえなかった。
ジッと、わたしを見つめている燐くんは、耐えられないとばかりに言葉をもらした。
「ぼくが六年、アメリカに行っているあいだ、陽菜はセルヴァン会長と修行か。いろいろ苦楽をともにした仲だもんね。そりゃ、ぼくなんて蚊帳の外か」
「燐くん……?」
辛そうにうつむく、燐くん。
「ぼくを守るっていってくれるのは、嬉しいよ。だって、ぼくはまだ、何が起こっているのかすら、うまく理解しきれていない。アステルが、陽菜以外の手に渡ったら、ぼくがこの世から消えること以外は」
「ごめんね。わたしが勝手に守るなんていったから……気を遣わせてるかもしれないけど……」
「――そんなこと思うわけない!」
わたしは、ビクッと肩をゆらした。
すると、燐くんは気まずそうに、わたしのほうへ手を伸ばしかけ、すぐに引っこめた。
「はあ……ごめん。ぼくが、おとなげないだけ。ずっと、もやもやして、落ち着かないんだ。頭では、わかってるのに、気持ちが追いつかない。きみに何をいっても、困らせるだけだって、わかってる」
そして、燐くんは、たまった息をそっと吐くようにいった。
「ぼくがいない、きみの六年に、ぼくの知らないきみの六年があるのが、腹が立つんだ。どうしようもなく……」
燐くんは、わたしのようすを伺うように、恐る恐る、目を上向かせた。
「これが、どういう意味なのか、わかる……?」
「燐くんが、わたしのこと、大切に思ってくれてるってことだよね? わかるよ」
燐くんの気持ちが嬉しくて、嬉しくて、わたしはすぐに答えた。
すると、燐くんは顔を引きつらせがら、大げさにため息をついた。
「……そう。そうだね……うん、そうだよ」
空いているほうの左手で額をおおうと、「わかってたけどね……」とつぶやいた。
燐くんは顔を赤らめながら、気を取り直したように、真面目な声でいう。
「陽菜」
「何?」
「陽菜にとって、ぼくと、セルヴァン会長って……どういう存在?」
「え?」
「大事なことだから、ちゃんと考えて」
「燐くんはわたしの守りたい人で、セルヴァン会長はお世話になってる人だよ」
「そっ。今は、それでいいよ」
燐くんは、ひとりで納得したように頷くと、階段の手すりに頬杖をついた。
「はあ……これからどうなるのか、想像もつかない」
「大丈夫だよ。燐くんは、わたしがぜったいに守るから」
「そっちじゃないよ。まあ……ありがとう。ぼくもできるだけ、自分の身は自分で守るようにするから」
「ふたりで何、話してるんですか?」
いつのまにか戻ってきていたセルヴァンが、急にすがたを現し、わたしと燐くんの顔のあいだで、おだやかにほほ笑んでいる。
いつもながら、神出鬼没だ。
「アステル。歌仙くんのこと、いじめてなかったですか?」
「いじめるわけない。きみこそ、勝手に人の制服を着てたりして、いったいどうしたの」
すると、セルヴァン会長は、待ってましたといわんばかりに、ゴホンと咳払いした。
「ぼくは以前から、この宝井中学校に興味があったんです。『星の器』が、この学校の生徒に多いという統計が取れているのは、歌仙くんも知っていると思いますが――」
むしろ、前よりも関係が近くなったような感じがしてる。
時任先輩は、校舎の廊下で戦って以来、学校を休んでいるらしい。
竜胆先輩にいたっては、実は、二年生の二学期からずっと不登校なんだって。
三年生に進級してからも、竜胆先輩のすがたは滅多に見ないみたい。
同じ学年じゃないから、ちっとも知らなかった。
下校しようと席から立ちあがったわたしに、燐くんがいった。
「陽菜、いっしょに帰……」
燐くんが何かをいいかけたとき、後ろから誰かがあいだに、割りこんで来た。
「――歌仙くん。見てください、これ!」
聞き慣れた声に驚いて、見あげると、セルヴァン会長が、満開の笑顔で着ているものを見せつけてきた。
いつもの夜空色のスーツではなく、宝井中学の制服を着た会長が、得意げに両腕を広げている。
しかも、光の術を使ってない。
どうどうと、学校の廊下にすがたを現してる。
燐くんが、「はあ?」と呆れたようにいった。
「きみ、なんでうちの制服着てんの」
「アステル。ただただ、目の前の事実を受け入れ、ぼくのこのすがたを褒めてはくれないんですか?」
「あいかわらず、面倒くさい」
燐くんとセルヴァンのいい争いがはじまると、ふたりの存在に気づいた周りの生徒たちが、ざわざわと騒ぎはじめた。
「ちょっと、あそこにいる金髪の人、めっちゃかっこよくないっ? あんな人、うちの学校にいたっけ? 何年生なんだろ~?」
「先輩じゃない? うちの学年にはいないよ~見たことないもん」
「佐々波くんの知り合いなのかな? あとで、聞いてみよっかっ?」
女の子たちのきゃあきゃあという、歓声があがりはじめた。
わたしは、あわてて、ふたりの手を取る。
「ちょっと、帰るならはやく帰ろう。ふたりのせいで、めちゃくちゃ目立ってるよ」
「目立つと、だめなんですか?」
ふしぎそうにいうセルヴァン会長に、燐くんが再び噛みつく。
「その制服、どうしたの」
「落ちてたんです。だから、ふたりといっしょの恰好になれたんですよっ。すてきでしょう?」
「――落ちてたって……そんなわけ」
不審そうにつぶやく、燐くん。
そのとき、少し離れた一年五組の教室から、困ったような大声が聞こえてきた。
「あれー? おれの制服知らねえ?」
「知らねえよ。掃除の時間で、わざわざ体操服に着替えたんかよ」
「だって、今日裏庭の側溝掃除だったからさー。制服汚れるのいやだったんだよ。おっかしいなー。机のうえに置いといたんだけど」
「おまえ、雑に置いて、よく床に落としてるから、風で飛んでったんじゃね?」
聞こえた話の内容に、わたしと燐くんは、思わず顔を見あわせた。
セルヴァン会長の手をふたりで、ガッと掴む。
ふしぎそうにしているセルヴァン会長をそのまま屋上への階段まで、引きずっていった。
最上段のところで手を放すと、燐くんがセルヴァン会長の胸元を、ぐいっと掴む。
「さっさと返してきて」
「ええっ? 返す? どうしてですか?」
「それ、落ちてたんじゃない。誰かの制服」
燐くんにお説教をされた、セルヴァン会長はつまらなさそうに、くちびるを曲げた。
不満そうに、パチンとフィンガースナップをすると、会長の制服は一瞬にして、もとの夜空色のスーツに変わる。
手には、ちゃんと畳んだ制服を持っていた。
燐くんが、諭すようにもう一度うながす。
「ほら、さっさと行く」
「わかりましたよ。そんなに、怒らないでくださいってば」
光の術で自分のすがたを消したセルヴァン会長の気配が、じょじょに遠のいていく。
燐くんは、呆れたといわんばかりに、ため息をついた。
「陽菜、ずっとあの人と修行してたんでしょ。大変だったんじゃない」
「セルヴァン会長は、自由だから」
昔っからあんな調子だから、わたしは慣れっこだけど、燐くんはずっと信じられないものを見たって顔してる。
くすくすと笑っていると、ふいに、会長との厳しい修行風景が脳裏によみがえる。
はじめて、術が成功したときのこと。
星成石の生成が、うまくいかなかったときのこと。
そして、自分の寿命を使って、導力を使うやり方を教わったときのこと。
「いろいろあったけど、ここまで来られたのは、セルヴァン会長がいてくれたからだからさ」
「――その人がいなければ、陽菜はこんなことに巻きこまれなかったじゃないか……」
燐くんが、ぼそっとなにかをいったように思ったけれど、わたしにはよく聞こえなかった。
ジッと、わたしを見つめている燐くんは、耐えられないとばかりに言葉をもらした。
「ぼくが六年、アメリカに行っているあいだ、陽菜はセルヴァン会長と修行か。いろいろ苦楽をともにした仲だもんね。そりゃ、ぼくなんて蚊帳の外か」
「燐くん……?」
辛そうにうつむく、燐くん。
「ぼくを守るっていってくれるのは、嬉しいよ。だって、ぼくはまだ、何が起こっているのかすら、うまく理解しきれていない。アステルが、陽菜以外の手に渡ったら、ぼくがこの世から消えること以外は」
「ごめんね。わたしが勝手に守るなんていったから……気を遣わせてるかもしれないけど……」
「――そんなこと思うわけない!」
わたしは、ビクッと肩をゆらした。
すると、燐くんは気まずそうに、わたしのほうへ手を伸ばしかけ、すぐに引っこめた。
「はあ……ごめん。ぼくが、おとなげないだけ。ずっと、もやもやして、落ち着かないんだ。頭では、わかってるのに、気持ちが追いつかない。きみに何をいっても、困らせるだけだって、わかってる」
そして、燐くんは、たまった息をそっと吐くようにいった。
「ぼくがいない、きみの六年に、ぼくの知らないきみの六年があるのが、腹が立つんだ。どうしようもなく……」
燐くんは、わたしのようすを伺うように、恐る恐る、目を上向かせた。
「これが、どういう意味なのか、わかる……?」
「燐くんが、わたしのこと、大切に思ってくれてるってことだよね? わかるよ」
燐くんの気持ちが嬉しくて、嬉しくて、わたしはすぐに答えた。
すると、燐くんは顔を引きつらせがら、大げさにため息をついた。
「……そう。そうだね……うん、そうだよ」
空いているほうの左手で額をおおうと、「わかってたけどね……」とつぶやいた。
燐くんは顔を赤らめながら、気を取り直したように、真面目な声でいう。
「陽菜」
「何?」
「陽菜にとって、ぼくと、セルヴァン会長って……どういう存在?」
「え?」
「大事なことだから、ちゃんと考えて」
「燐くんはわたしの守りたい人で、セルヴァン会長はお世話になってる人だよ」
「そっ。今は、それでいいよ」
燐くんは、ひとりで納得したように頷くと、階段の手すりに頬杖をついた。
「はあ……これからどうなるのか、想像もつかない」
「大丈夫だよ。燐くんは、わたしがぜったいに守るから」
「そっちじゃないよ。まあ……ありがとう。ぼくもできるだけ、自分の身は自分で守るようにするから」
「ふたりで何、話してるんですか?」
いつのまにか戻ってきていたセルヴァンが、急にすがたを現し、わたしと燐くんの顔のあいだで、おだやかにほほ笑んでいる。
いつもながら、神出鬼没だ。
「アステル。歌仙くんのこと、いじめてなかったですか?」
「いじめるわけない。きみこそ、勝手に人の制服を着てたりして、いったいどうしたの」
すると、セルヴァン会長は、待ってましたといわんばかりに、ゴホンと咳払いした。
「ぼくは以前から、この宝井中学校に興味があったんです。『星の器』が、この学校の生徒に多いという統計が取れているのは、歌仙くんも知っていると思いますが――」