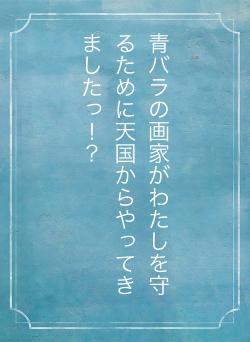じゃあ、この人も、セルヴァン会長と同じ……とんでもない時間を生きている星成士ということ?
「だが……そろそろ、星のちからが尽きそうなんだ。また、アステルを手に入れないといけない」
「そんな……っ。財団のセルヴァン会長は、ひとつのアステルだけで、何百年も生き続けてるっていってた。どうして、またアステルを……?」
竜胆先輩の目は、ここではないどこかを見つめている。
まるで、遠くにいる誰かを思うように。
「ある人にもう一度、巡り合うためだ。そのために、おれは次元をいくつも超え続けている。だから、無尽蔵の導力がいる。アステルひとつでは、足りないんだ」
「だからって……」
すると、竜胆先輩はいまにも泣きそうな顔をしていった。
「前回の祝祭で『星の器』となったのは、おれの恋人だった」
「なっ……」
わたしは、信じられない気持ちで、息を飲んだ。
竜胆先輩は、アステルを手に入れるために、自分の恋人を……?
「ど……どうして……?」
「彼女は……余命わずかだった」
竜胆先輩は、まるで自分にいい聞かせるように、消え入りそうな声でいった。
「アステルとなって消えるくらいなら、おれのちからになりたいといった。だから、前回の祝祭は、すぐにおわった。おれが、あっというまにアステルを手に入れたからだ」
「それじゃあ、竜胆先輩は……」
「おれは、彼女のために生き続けなければならない。彼女の命をむだにしないためにも……だから、次元を超えて彼女を探している。彼女に再び、巡り会うために」
竜胆先輩が、紫色のマチェーテナイフをおろす。
そしてなぜか、わたしの顔をのぞきこんだ。
「――あんた」
そっと、わたしの手を取ると、自分の頬にあわせた。
「ちょ……っ」
「あんたの瞳、彼女の色と同じだ。まさか、あんたは……」
そのとき、わたしの背後から、ざわりとしたおぞましい気配を感じた。
そばにいるだけで、びりびりとした、怒りが伝わってくる。
穏やかじゃない気配を感じたのか、竜胆先輩はそっと、わたしの手を放した。
「おまえ……後ろに誰かいるのか? 星成士の気配を感じるような気がする」
セルヴァン会長のことだ。
ふだん、おだやかなセルヴァン会長だけど、こんなに怒るなんてどうしたんだろう。
それにしても。
すがたを消したセルヴァン会長の気配は、これまで、アステルである燐くんしかわからなかった。
竜胆先輩。
やっぱり、一筋縄ではいかない相手だ。
硬い道路のうえで、ひざをついたままの燐くんに、わたしの気持ちが焦る。
わたしは、スカートのポケットに入れている、星成石をひとつ握りしめ、竜胆先輩を見あげた。
「燐くんの支配を解いてください」
「知ってるか?」
竜胆先輩は紫色のマチェーテの刃先を、わたしに向けていった。
「むかしから、現在の宝井中学がある場所にいる人間が、『星の器』に選ばれやすいといわれている。前回も……そうだった」
「それって――」
竜胆先輩のマチェーテが振りおろされると同時に、わたしの剣がぶつかり、ガキインッ、という甲高い音が、響き渡る。
武器と武器の、激しいぶつかり合いがはじまる。
剣を跳ね返されたわたしは宙返りをし、再び竜胆先輩へと飛んでいく。
青い剣先が、竜胆先輩の制服の袖口を切り裂き、紫のマチェーテはわたしの制服のリボンタイを切り落とした。
わたしは、ポケットから星成石を取り出し、呪文を唱える。
「星よ、聴け――我が青き導力の煌めきを見よ。遠きアステルの導きに従い、轟きうねり爆ぜよ」
竜胆先輩目がけ、星成石を投げつけた。
とたん、あたりを爆風が襲う。
竜胆先輩が、住宅街の塀に飛ばされるのを見たあと、わたしは急いで、燐くんのもとに駆け寄った。
しゃがんだまま、背中から抱き起し、両肩を支える。
意識のない燐くんのからだはふらふらで、病弱だったときのことを思い出してしまう。
燐くんの首にかかっている、ネックレス。
取り出してみると、ペンダントトップの青い星成石がヒビ割れている。
「これが完全に割れていたら――燐くんは……たぶん、竜胆先輩に」
燐くんの意識支配は、竜胆先輩を倒すしかない、とセルヴァン会長はいっていた。
竜胆先輩を倒す――。
あの人は、一度、アステルを手に入れている。
つまり、強い。
「いったん燐くんを連れて、引いたほうが――でも逃げたところで、竜胆先輩から逃げられるとは思えない」
もしかして、絶体絶命?
燐くんを守ることもできずに?
そんなのいやだ――。
ポケットから、星成石を取り出す。
わたしの導力の色は、青。
「決意の青色なんだって、セルヴァン会長がいってた……」
すると、わたしのようすに気づいたのか、すがたの見えないセルヴァン会長の声が、どこからともなく聞こえた。
「アステルとの約束を、破るんですか?」
「今の状況を突破するには、これしかない。燐くんを守るため……です」
「――そうですか……」
この方法を教えてくれたのは、セルヴァン会長なのに、どうしてか彼は苦しそうにうなった。
わたしは、星成石に大量の導力を注ぎこんだ。
すると、いつもは青い星成石に、きれいな黄金色の渦が混ざり、複雑な輝きを放ちだした。
「この色は……?」
壁から立ちあがりかけていた竜胆先輩が、わたしの星成石を見て、ほれぼれするようにいった。
「あんなに導力を注ぎこんだら、ふつう、石は割れてしまう。あそこまで、きれいに導力が注ぎこまれた星成石……見たことがない」
黄金色の渦を描く星成石が、わたしの手のひらで輝く。
紫の魔霧から、青い導力の光が、まぶしく差しこんだ。
「星よ、聴け――我が青き石の煌めきを見よ。遠きアステルの導きに従い……」
言葉が、出てこない。
どんな呪文をいえば、竜胆先輩に勝てるのか。
強い言葉? 激しい言葉?
確実に、燐くんを助けられる言葉が、わからない。
そのとき、わたしの手に温かいものが触れた。
そして、弱弱しく、そっと握られる。
「り、燐くん……?」
背中から支えていた燐くんの手が、わたしの手にぬくもりを与えてくれている。
燐くんの重たいまつ毛が、わずかに揺れたけれど、目を覚ましてはいない。
まだ、かんぜんに竜胆先輩の支配は解けていないみたいだ。
とたん、わたしの頭のなかに、呪文の言葉が浮かびあがった。
「星よ、聴け――我が青き導力の煌めきを見よ。新しきアステルの導きに従い、古きアステルの星よ眠れ――」
「……ぐっ」
竜胆先輩が、苦しそうに頭を押さえた。
「この導力は……? おれの導力が、押さえつけられている……。新しきアステルの導き――だって……」
紫のマチェーテが、道路のコンクリートにカシャンと落ち、崩れた。
「アステルから貰った導力が、からだの奥に沈んでいく……消えてしまう……」
紫の魔霧が濃くなるなか、竜胆先輩の嘆きが響いた。
そのゆらめきに、竜胆先輩のすがたは溶け、やがて見えなくなってしまった。
魔霧が晴れると、周りの住宅街の風景が、何事もなかったかのように流れ出す。
「歌仙くん」
背後から、すがたをあらわしたセルヴァン会長に駆け寄られ、頬をぺたぺたと触られる。
「すごい呪文でした! あんな呪文は三百年のあいだ、聞いたことがないです! どこから着想を得たんですか? ぼくにも、ご教示願いたいです!」
「ちょっと、会長。今日は、おしゃべりだね」
「あっ、す、すみません。――そうだ。アステルは……」
わたしに背中を預けていた燐くんの目が、ふわりと開く。
導力を眠らせた竜胆先輩の支配が解けたんだ。
「燐くん!」
「……陽菜」
まだ、ぼんやりとしている燐くんだったけど、すぐに意識がはっきりとしてきたみたいで、ぎゅっと眉間にシワがよる。
「……どうして、ここにいるの?」
「――えっ」
「ぼく……陽菜にひどい態度をとったのに」
「えーと」
そうだったっけ?
たしかに、燐くんは、いきなりわたしの家を出て行っちゃったんだけど。
それは、燐くんに色んなことをたくさん説明したからだから、こっちがわるいんだよ。
「燐くんは、何もわるくないよ」
「陽菜は、ぼくに甘すぎる」
「え? えっ、そ、そんなことないよ……?」
「激甘だよ」
深くため息をつく燐くんに、わたしは、あわてふためいてしまう。
「そうだね。わるいのは、そこにいるナントカ財団の会長だ」
「ええっ。ぼくですかっ?」
きょとんとした顔で、小首を傾げるセルヴァン会長に、燐くんはまた不機嫌そうにくちびると引き結んだ。
「きみの飄々とした態度、どうにかならないの? 腹が立って仕方がない」
「アステル。あなたは、起きたばかりなのに、ずいぶんと元気ですね。いちおう、ぼくは大きな組織の会長なんですが?」
「そんなこと、ぼくの知ったことじゃない。それにぼくは、アステルとかいう、財団の大事な存在なんでしょ。そんな態度でいいの?」
「そうですね。歌仙くんに頼まれたら、態度をあらためないこともありませんが」
ふたりのあいだに、バチバチとした火花が見える。
え? なんでケンカみたいなことになってるの?
おろおろしているわたしを見て、燐くんは「はあ」と息をついた。
「――そういえば、陽菜。聞こえてたよ」
「え?」
「また、ぼくを、助けてくれたでしょ。ぼくは、へんな術をかけられて、意識をなくしてしまってた。でも、陽菜の声はずっと聞こえてたよ。……助けてくれて、ありがとう」
そういうと、燐くんは照れくさそうに、頬をかいた。
燐くんのそんな表情を見れるのは、とってもレアだよね。
嬉しさがこみあげ、じんわりと顔が熱くなる。
「ちょっと、陽菜。なんで、にやにやしてんの」
「へへ……」
「はあ。ぼくも、きみには甘すぎるのかも」
燐くんの琥珀色の瞳が、うれしそうに細められた。
まるで、さっき見た、黄金色の光のようにきれいだった。
「だが……そろそろ、星のちからが尽きそうなんだ。また、アステルを手に入れないといけない」
「そんな……っ。財団のセルヴァン会長は、ひとつのアステルだけで、何百年も生き続けてるっていってた。どうして、またアステルを……?」
竜胆先輩の目は、ここではないどこかを見つめている。
まるで、遠くにいる誰かを思うように。
「ある人にもう一度、巡り合うためだ。そのために、おれは次元をいくつも超え続けている。だから、無尽蔵の導力がいる。アステルひとつでは、足りないんだ」
「だからって……」
すると、竜胆先輩はいまにも泣きそうな顔をしていった。
「前回の祝祭で『星の器』となったのは、おれの恋人だった」
「なっ……」
わたしは、信じられない気持ちで、息を飲んだ。
竜胆先輩は、アステルを手に入れるために、自分の恋人を……?
「ど……どうして……?」
「彼女は……余命わずかだった」
竜胆先輩は、まるで自分にいい聞かせるように、消え入りそうな声でいった。
「アステルとなって消えるくらいなら、おれのちからになりたいといった。だから、前回の祝祭は、すぐにおわった。おれが、あっというまにアステルを手に入れたからだ」
「それじゃあ、竜胆先輩は……」
「おれは、彼女のために生き続けなければならない。彼女の命をむだにしないためにも……だから、次元を超えて彼女を探している。彼女に再び、巡り会うために」
竜胆先輩が、紫色のマチェーテナイフをおろす。
そしてなぜか、わたしの顔をのぞきこんだ。
「――あんた」
そっと、わたしの手を取ると、自分の頬にあわせた。
「ちょ……っ」
「あんたの瞳、彼女の色と同じだ。まさか、あんたは……」
そのとき、わたしの背後から、ざわりとしたおぞましい気配を感じた。
そばにいるだけで、びりびりとした、怒りが伝わってくる。
穏やかじゃない気配を感じたのか、竜胆先輩はそっと、わたしの手を放した。
「おまえ……後ろに誰かいるのか? 星成士の気配を感じるような気がする」
セルヴァン会長のことだ。
ふだん、おだやかなセルヴァン会長だけど、こんなに怒るなんてどうしたんだろう。
それにしても。
すがたを消したセルヴァン会長の気配は、これまで、アステルである燐くんしかわからなかった。
竜胆先輩。
やっぱり、一筋縄ではいかない相手だ。
硬い道路のうえで、ひざをついたままの燐くんに、わたしの気持ちが焦る。
わたしは、スカートのポケットに入れている、星成石をひとつ握りしめ、竜胆先輩を見あげた。
「燐くんの支配を解いてください」
「知ってるか?」
竜胆先輩は紫色のマチェーテの刃先を、わたしに向けていった。
「むかしから、現在の宝井中学がある場所にいる人間が、『星の器』に選ばれやすいといわれている。前回も……そうだった」
「それって――」
竜胆先輩のマチェーテが振りおろされると同時に、わたしの剣がぶつかり、ガキインッ、という甲高い音が、響き渡る。
武器と武器の、激しいぶつかり合いがはじまる。
剣を跳ね返されたわたしは宙返りをし、再び竜胆先輩へと飛んでいく。
青い剣先が、竜胆先輩の制服の袖口を切り裂き、紫のマチェーテはわたしの制服のリボンタイを切り落とした。
わたしは、ポケットから星成石を取り出し、呪文を唱える。
「星よ、聴け――我が青き導力の煌めきを見よ。遠きアステルの導きに従い、轟きうねり爆ぜよ」
竜胆先輩目がけ、星成石を投げつけた。
とたん、あたりを爆風が襲う。
竜胆先輩が、住宅街の塀に飛ばされるのを見たあと、わたしは急いで、燐くんのもとに駆け寄った。
しゃがんだまま、背中から抱き起し、両肩を支える。
意識のない燐くんのからだはふらふらで、病弱だったときのことを思い出してしまう。
燐くんの首にかかっている、ネックレス。
取り出してみると、ペンダントトップの青い星成石がヒビ割れている。
「これが完全に割れていたら――燐くんは……たぶん、竜胆先輩に」
燐くんの意識支配は、竜胆先輩を倒すしかない、とセルヴァン会長はいっていた。
竜胆先輩を倒す――。
あの人は、一度、アステルを手に入れている。
つまり、強い。
「いったん燐くんを連れて、引いたほうが――でも逃げたところで、竜胆先輩から逃げられるとは思えない」
もしかして、絶体絶命?
燐くんを守ることもできずに?
そんなのいやだ――。
ポケットから、星成石を取り出す。
わたしの導力の色は、青。
「決意の青色なんだって、セルヴァン会長がいってた……」
すると、わたしのようすに気づいたのか、すがたの見えないセルヴァン会長の声が、どこからともなく聞こえた。
「アステルとの約束を、破るんですか?」
「今の状況を突破するには、これしかない。燐くんを守るため……です」
「――そうですか……」
この方法を教えてくれたのは、セルヴァン会長なのに、どうしてか彼は苦しそうにうなった。
わたしは、星成石に大量の導力を注ぎこんだ。
すると、いつもは青い星成石に、きれいな黄金色の渦が混ざり、複雑な輝きを放ちだした。
「この色は……?」
壁から立ちあがりかけていた竜胆先輩が、わたしの星成石を見て、ほれぼれするようにいった。
「あんなに導力を注ぎこんだら、ふつう、石は割れてしまう。あそこまで、きれいに導力が注ぎこまれた星成石……見たことがない」
黄金色の渦を描く星成石が、わたしの手のひらで輝く。
紫の魔霧から、青い導力の光が、まぶしく差しこんだ。
「星よ、聴け――我が青き石の煌めきを見よ。遠きアステルの導きに従い……」
言葉が、出てこない。
どんな呪文をいえば、竜胆先輩に勝てるのか。
強い言葉? 激しい言葉?
確実に、燐くんを助けられる言葉が、わからない。
そのとき、わたしの手に温かいものが触れた。
そして、弱弱しく、そっと握られる。
「り、燐くん……?」
背中から支えていた燐くんの手が、わたしの手にぬくもりを与えてくれている。
燐くんの重たいまつ毛が、わずかに揺れたけれど、目を覚ましてはいない。
まだ、かんぜんに竜胆先輩の支配は解けていないみたいだ。
とたん、わたしの頭のなかに、呪文の言葉が浮かびあがった。
「星よ、聴け――我が青き導力の煌めきを見よ。新しきアステルの導きに従い、古きアステルの星よ眠れ――」
「……ぐっ」
竜胆先輩が、苦しそうに頭を押さえた。
「この導力は……? おれの導力が、押さえつけられている……。新しきアステルの導き――だって……」
紫のマチェーテが、道路のコンクリートにカシャンと落ち、崩れた。
「アステルから貰った導力が、からだの奥に沈んでいく……消えてしまう……」
紫の魔霧が濃くなるなか、竜胆先輩の嘆きが響いた。
そのゆらめきに、竜胆先輩のすがたは溶け、やがて見えなくなってしまった。
魔霧が晴れると、周りの住宅街の風景が、何事もなかったかのように流れ出す。
「歌仙くん」
背後から、すがたをあらわしたセルヴァン会長に駆け寄られ、頬をぺたぺたと触られる。
「すごい呪文でした! あんな呪文は三百年のあいだ、聞いたことがないです! どこから着想を得たんですか? ぼくにも、ご教示願いたいです!」
「ちょっと、会長。今日は、おしゃべりだね」
「あっ、す、すみません。――そうだ。アステルは……」
わたしに背中を預けていた燐くんの目が、ふわりと開く。
導力を眠らせた竜胆先輩の支配が解けたんだ。
「燐くん!」
「……陽菜」
まだ、ぼんやりとしている燐くんだったけど、すぐに意識がはっきりとしてきたみたいで、ぎゅっと眉間にシワがよる。
「……どうして、ここにいるの?」
「――えっ」
「ぼく……陽菜にひどい態度をとったのに」
「えーと」
そうだったっけ?
たしかに、燐くんは、いきなりわたしの家を出て行っちゃったんだけど。
それは、燐くんに色んなことをたくさん説明したからだから、こっちがわるいんだよ。
「燐くんは、何もわるくないよ」
「陽菜は、ぼくに甘すぎる」
「え? えっ、そ、そんなことないよ……?」
「激甘だよ」
深くため息をつく燐くんに、わたしは、あわてふためいてしまう。
「そうだね。わるいのは、そこにいるナントカ財団の会長だ」
「ええっ。ぼくですかっ?」
きょとんとした顔で、小首を傾げるセルヴァン会長に、燐くんはまた不機嫌そうにくちびると引き結んだ。
「きみの飄々とした態度、どうにかならないの? 腹が立って仕方がない」
「アステル。あなたは、起きたばかりなのに、ずいぶんと元気ですね。いちおう、ぼくは大きな組織の会長なんですが?」
「そんなこと、ぼくの知ったことじゃない。それにぼくは、アステルとかいう、財団の大事な存在なんでしょ。そんな態度でいいの?」
「そうですね。歌仙くんに頼まれたら、態度をあらためないこともありませんが」
ふたりのあいだに、バチバチとした火花が見える。
え? なんでケンカみたいなことになってるの?
おろおろしているわたしを見て、燐くんは「はあ」と息をついた。
「――そういえば、陽菜。聞こえてたよ」
「え?」
「また、ぼくを、助けてくれたでしょ。ぼくは、へんな術をかけられて、意識をなくしてしまってた。でも、陽菜の声はずっと聞こえてたよ。……助けてくれて、ありがとう」
そういうと、燐くんは照れくさそうに、頬をかいた。
燐くんのそんな表情を見れるのは、とってもレアだよね。
嬉しさがこみあげ、じんわりと顔が熱くなる。
「ちょっと、陽菜。なんで、にやにやしてんの」
「へへ……」
「はあ。ぼくも、きみには甘すぎるのかも」
燐くんの琥珀色の瞳が、うれしそうに細められた。
まるで、さっき見た、黄金色の光のようにきれいだった。