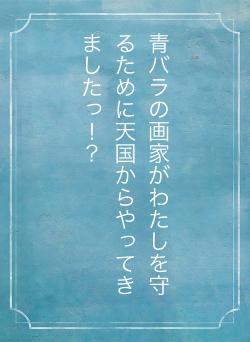燐くんを複雑な気持ちで見送ったあと、わたしはセルヴァン会長をじっとりとした目で見あげた。
セルヴァン会長は、困ったように肩をすくめる。
「歌仙くん……あなたのその顔の意味をぼくは知っていますよ。怒っているんですね」
「怒っているというか」
「じゃあ、どうしてそんな目で、ぼくを見るんでしょう?」
「セルヴァン会長。以前わたしに、こういってましたよね」
――あなたは……このまま永遠に、アステルを守り抜く覚悟があるということですね?
セルヴァン会長は、琥珀色の瞳を細め、「ええ」とうなずいた。
「財団の本当の理由なんて、わたしはどうでもいいです。わたしが燐くんを守ることに、財団の理由なんて関係ないから。だから、あんな……財団の『いいわけ』なんて、燐くんに打ち明けてほしくなかった。しかも、よりによって、いちばん燐くんが混乱してる、いま……」
すると、セルヴァン会長は、なぜか花がほころぶように微笑んだ。
「――そうですか。ぼくはアステルに、いじわるをしてしまったかもしれませんね」
「いじわる……? なんでそんなこと」
「六年も、ぼくはあなたといっしょにいたでしょう? なのに最近、あなたはアステルとばかりいっしょにいるから」
「はい……? こんなときに、何わけのわかんないこといってるんですか」
すると、セルヴァン会長は、わたしの頬にそっと手を添えた。
「安心してください。これ以上、あなたを困らせることはしませんから」
「最初から、へんなことをするのは止めてください。燐くん、ただでさえいっぱいいっぱいだったと思うのに」
「心配ですか?」
「あたりまえです」
「ふふ。口癖まで、彼に似てきていますね」
「からかわないでくださ……」
いいかけてた言葉を、喉の奥へと押しこめた。
――ざわり、と、いやな気配が背筋を走る。
なんだろう、この感じ。
時任先輩のときとはまた違う、胸のざわめき。
学校にも、燐くんにも、結界を張っている。
もちろん、燐くんの家にも、厳重に。
時任先輩には、「いくつ結界を張っている?」なんて聞かれたけれど、足りないと思っているくらい。
だから、わたしの居場所も、燐くんの居場所も、ふつうならバレないはず。
時任先輩は、財団に繋がりのある身内から、情報を横流ししてもらったって、いってたっけ。
そのことについて、くわしく聞いてなかったけど、それっていったい、誰?
セルヴァン会長は、時任家の身内について、何か知っているのかな。
「歌仙くん」
「うん」
「導力の気配ですよ。それも、そうとう近く」
「――燐くんがあぶない!」
玄関を飛び出してすぐ、わたしは足を止める。
家のまわり一帯に、うっすらと紫色の霧が立ちこめている。
そしてそれは、燐くんの家に近づくごとに、濃くなっていく。
「魔霧……」
つまり、時任先輩のときと同じ、ここら一帯の人たちはみんな、眠りについていることになる。
見えないけれど、路上で眠っている人もいるかもしれない。
セルヴァン会長の気配を、すぐそばで感じた。
光の屈折を利用した術で、自分のすがたを見えなくしている。
相手の星成士に、財団の会長の存在を知られないようにするためだろう。
「……急がないと」
走って、燐くんの家へ向かおうとしたとき、家の門のそばに、見知らぬ人物がたたずんでいるのに気づいた。
その人は、質のいいスラックスのポケットに両手を差しこみ、藤色のパーマがかかった髪を風になびかせていた。
わたしのすがたを目にとどめると、無感情にぺこりと頭をさげてきた。
「……来たか」
こちらへ一歩近づいてきて、コンクリートの砂が、ざり、と音をたてた。
その人の足元に、見覚えのある制服が見えた。
とたん、わたしは心臓を誰かにつかまれたような感覚におちいった。
燐くんが両ひざをついて、首をだらりと、うつむかせている。
「――燐くん!」
わたしが駆け寄ろうとすると、セルヴァン会長に声だけで、制止される。
「会長! 放して、燐くんが」
「落ち着いて。状況をよく見てみてください」
セルヴァン会長に必死にいわれ、わたしはバクバクと暴れる自分の心臓の音を聞きながら、ゆっくりと深呼吸をした。
いまの燐くんのようす、なんだかおかしい。
眠らされている? それにしては、ようすがへんだ。
「アステルはいま、目の前の彼に、意識を支配されているようです」
「……そんな」
「こういう精神系の術は、相手の術者を倒せば、元に戻るでしょう」
「――あの人が、三人目の星成士?」
「ええ。竜胆家の星成士ですね」
わたしは、制服のポケットから、星成石を手に取った。
同時に、青い石はつららのように形を変え、透き通った剣となる。
燐くんは、道路にひざをついたまま、身動きひとつしてくれない。
「すぐに、助けるから……っ」
その人は、鮮やかな藤色をした天然パーマの髪を耳にかけ、「ふん」と鼻を鳴らした。
彼が、手のひらを開くと、そこに紫色の召喚石がひとつ、転がった。
ゆらりと揺れた、竜胆くんのすがたが、こつ然と消える。
彼は紫色のナイフを、わたしに突きつけた。
同時にわたしも、竜胆くんの急所に刃先を向ける。
セルヴァン会長が、「わあ」と声をあげた。
「マチェーテナイフ……ずいぶんと、乱暴で強引な武器を生成したものですね」
わたしは、剣の刀身をギリギリと押しつけながら、怒りをあらわに、竜胆くんに問いつめた。
「燐くんに、何をしたの? どうして、燐くんを狙ったの?」
「こいつ、ネックレスにした星成石を見てた」
わたしがあげた星成石……!
それじゃあ、燐くんが狙われたのって、わたしのせい?
「まあ、それは関係ないか。おれは、時任家の星成士と、おまえの戦闘を見ていたから」
この人も、学校にいたの?
まさか……時任先輩との会話を聞かれてた……?
「あなたも、宝井中学なの?」
「ああ。竜胆仙太。宝井中学の三年生だ」
先輩だったんだ。
「時任の魔霧のなかでも、眠らず起きていた。こいつ、アステルなんじゃないか?」
燐くんのこと、やっぱりバレてる……。
「アステルを手に入れるためだからって、こんなにひどいことをしてっ……なんとも思わないんですかッ?」
感情に任せていうと、これまで無表情だった竜胆先輩が、かなしそうに目を伏せたので、わたしはビクッと肩をゆらした。
どうして、そんな顔をするの……?
「おれは、前回の祝祭で、アステルを手に入れた」
「え……」
前回のアステル百年祝祭で――ッ?
セルヴァン会長は、困ったように肩をすくめる。
「歌仙くん……あなたのその顔の意味をぼくは知っていますよ。怒っているんですね」
「怒っているというか」
「じゃあ、どうしてそんな目で、ぼくを見るんでしょう?」
「セルヴァン会長。以前わたしに、こういってましたよね」
――あなたは……このまま永遠に、アステルを守り抜く覚悟があるということですね?
セルヴァン会長は、琥珀色の瞳を細め、「ええ」とうなずいた。
「財団の本当の理由なんて、わたしはどうでもいいです。わたしが燐くんを守ることに、財団の理由なんて関係ないから。だから、あんな……財団の『いいわけ』なんて、燐くんに打ち明けてほしくなかった。しかも、よりによって、いちばん燐くんが混乱してる、いま……」
すると、セルヴァン会長は、なぜか花がほころぶように微笑んだ。
「――そうですか。ぼくはアステルに、いじわるをしてしまったかもしれませんね」
「いじわる……? なんでそんなこと」
「六年も、ぼくはあなたといっしょにいたでしょう? なのに最近、あなたはアステルとばかりいっしょにいるから」
「はい……? こんなときに、何わけのわかんないこといってるんですか」
すると、セルヴァン会長は、わたしの頬にそっと手を添えた。
「安心してください。これ以上、あなたを困らせることはしませんから」
「最初から、へんなことをするのは止めてください。燐くん、ただでさえいっぱいいっぱいだったと思うのに」
「心配ですか?」
「あたりまえです」
「ふふ。口癖まで、彼に似てきていますね」
「からかわないでくださ……」
いいかけてた言葉を、喉の奥へと押しこめた。
――ざわり、と、いやな気配が背筋を走る。
なんだろう、この感じ。
時任先輩のときとはまた違う、胸のざわめき。
学校にも、燐くんにも、結界を張っている。
もちろん、燐くんの家にも、厳重に。
時任先輩には、「いくつ結界を張っている?」なんて聞かれたけれど、足りないと思っているくらい。
だから、わたしの居場所も、燐くんの居場所も、ふつうならバレないはず。
時任先輩は、財団に繋がりのある身内から、情報を横流ししてもらったって、いってたっけ。
そのことについて、くわしく聞いてなかったけど、それっていったい、誰?
セルヴァン会長は、時任家の身内について、何か知っているのかな。
「歌仙くん」
「うん」
「導力の気配ですよ。それも、そうとう近く」
「――燐くんがあぶない!」
玄関を飛び出してすぐ、わたしは足を止める。
家のまわり一帯に、うっすらと紫色の霧が立ちこめている。
そしてそれは、燐くんの家に近づくごとに、濃くなっていく。
「魔霧……」
つまり、時任先輩のときと同じ、ここら一帯の人たちはみんな、眠りについていることになる。
見えないけれど、路上で眠っている人もいるかもしれない。
セルヴァン会長の気配を、すぐそばで感じた。
光の屈折を利用した術で、自分のすがたを見えなくしている。
相手の星成士に、財団の会長の存在を知られないようにするためだろう。
「……急がないと」
走って、燐くんの家へ向かおうとしたとき、家の門のそばに、見知らぬ人物がたたずんでいるのに気づいた。
その人は、質のいいスラックスのポケットに両手を差しこみ、藤色のパーマがかかった髪を風になびかせていた。
わたしのすがたを目にとどめると、無感情にぺこりと頭をさげてきた。
「……来たか」
こちらへ一歩近づいてきて、コンクリートの砂が、ざり、と音をたてた。
その人の足元に、見覚えのある制服が見えた。
とたん、わたしは心臓を誰かにつかまれたような感覚におちいった。
燐くんが両ひざをついて、首をだらりと、うつむかせている。
「――燐くん!」
わたしが駆け寄ろうとすると、セルヴァン会長に声だけで、制止される。
「会長! 放して、燐くんが」
「落ち着いて。状況をよく見てみてください」
セルヴァン会長に必死にいわれ、わたしはバクバクと暴れる自分の心臓の音を聞きながら、ゆっくりと深呼吸をした。
いまの燐くんのようす、なんだかおかしい。
眠らされている? それにしては、ようすがへんだ。
「アステルはいま、目の前の彼に、意識を支配されているようです」
「……そんな」
「こういう精神系の術は、相手の術者を倒せば、元に戻るでしょう」
「――あの人が、三人目の星成士?」
「ええ。竜胆家の星成士ですね」
わたしは、制服のポケットから、星成石を手に取った。
同時に、青い石はつららのように形を変え、透き通った剣となる。
燐くんは、道路にひざをついたまま、身動きひとつしてくれない。
「すぐに、助けるから……っ」
その人は、鮮やかな藤色をした天然パーマの髪を耳にかけ、「ふん」と鼻を鳴らした。
彼が、手のひらを開くと、そこに紫色の召喚石がひとつ、転がった。
ゆらりと揺れた、竜胆くんのすがたが、こつ然と消える。
彼は紫色のナイフを、わたしに突きつけた。
同時にわたしも、竜胆くんの急所に刃先を向ける。
セルヴァン会長が、「わあ」と声をあげた。
「マチェーテナイフ……ずいぶんと、乱暴で強引な武器を生成したものですね」
わたしは、剣の刀身をギリギリと押しつけながら、怒りをあらわに、竜胆くんに問いつめた。
「燐くんに、何をしたの? どうして、燐くんを狙ったの?」
「こいつ、ネックレスにした星成石を見てた」
わたしがあげた星成石……!
それじゃあ、燐くんが狙われたのって、わたしのせい?
「まあ、それは関係ないか。おれは、時任家の星成士と、おまえの戦闘を見ていたから」
この人も、学校にいたの?
まさか……時任先輩との会話を聞かれてた……?
「あなたも、宝井中学なの?」
「ああ。竜胆仙太。宝井中学の三年生だ」
先輩だったんだ。
「時任の魔霧のなかでも、眠らず起きていた。こいつ、アステルなんじゃないか?」
燐くんのこと、やっぱりバレてる……。
「アステルを手に入れるためだからって、こんなにひどいことをしてっ……なんとも思わないんですかッ?」
感情に任せていうと、これまで無表情だった竜胆先輩が、かなしそうに目を伏せたので、わたしはビクッと肩をゆらした。
どうして、そんな顔をするの……?
「おれは、前回の祝祭で、アステルを手に入れた」
「え……」
前回のアステル百年祝祭で――ッ?