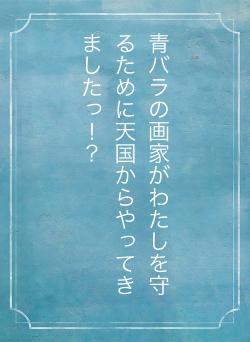じんわりと暑い夏の夜だった。
家に帰る道を歩いていると、セルヴァン会長が、闇に溶けるようなしずかな声でいった。
「歌仙くん——ついに……『アステル』が日本に帰ってくるんですね」
「セルヴァン会長。あいかわらず、神出鬼没ですね」
「それほどでも」
さっきまでは、わたししかこの夜道を歩いていなかったのに、この人はいつも急にどこからか現れる。
「褒めてないですっ。それに……」
セルヴァン会長のいったことの間違いをただすように、わたしは、ゆるゆると首を振った。
「アステルじゃありません。佐々波燐くんです。ちゃんと覚えてください」
燐くんが、宝井町に帰ってくる。
それは、わたしの怒涛の日々の、はじまりを意味していた。
「ええ、努力します」
「燐くん、二学期からは、いっしょに宝井中学校に通えるみたいです。朝、お母さんがいってました」
うれしさを隠しきれずにいると、セルヴァン会長がスッと目を細めた。
まるで、猫みたいに。
「アステルがこの町に来るってことは……いよいよ、はじまりますね。アステル百年祝祭が」
「はい」
「準備は、よろしいですか? これから、あなたはとても忙しくなりますよ」
「いいんです。わたしが、望んだことだし」
「永遠に、戦い続けなければならなくなっても……ですか?」
胸が締めつけられそうになる気持ちを抑えながら、わたしは返事をする。
セルヴァン会長が、わたしの顔を覗きこんだ。
そのきれいな顔が、ふんわりとした月の光のなかにぼんやりと浮かびあがる。
「アステルは、この町に戻る運命だったのでしょう。そして、あなたが『星成士』という道を選ぶことも、運命だった」
セルヴァン会長は、月の光のような髪をゆらりとゆらした。
夜空色のスーツを身にまとったすがたは、この世のものではないのではないかと思うほどに、きれいだと思ってしまう。
「安心してください。祝祭が永遠に終わらなくても……ぼくは、アステル星成士財団の会長として、あなたを見守り続けます。なにしろ、あなたの選んだ道は、祝祭はじまって以来の異例のことですから」
「改めて聞きますけど……祝祭をはじめないようにすることは、できないんですよね」
厳格な表情で、わたしを見おろす、セルヴァン会長。
「それは、できません。『星』が定めた、ルールですから」
いい終えたと同時に、闇に消えるセルヴァン会長を見届けたあと、わたしはひとり、夜道を歩く。
今日の修行も、ぶじにおわった。
星成士……みずからの力を使って、あらゆるものを生み出すものたち――のこと。
わたしはこの六年間、星成士としてつよくなるためだけに、修行を続けてきた。
祝祭までのカウントダウンは、もうはじまっている。
燐くんが、この宝井町についた、その瞬間。
星成士たちのアステルを賭けた戦い――アステル百年祝祭が、スタートする。
■
朝の通学路、歩きながらポケットのなかを確認する。
くるりとなかをかき混ぜると、入っている石が、じゃらりと音を立てた。
いち、に、さん、し、ご。
「うん。数はじゅうぶん」
足りるのかはわからないけれど、このくらいの数はいつも持ち歩くことにしていた。
『星成石』。
わたしの導力――星成士だけが持つ、ふしぎな力――がこもった、手作りの石。
わたしの導力の色は青いらしいから、海みたいに透き通った青い石ができあがる。
燐くんが、もうすぐ日本に帰ってくると聞いて、一週間前から準備してた。
いつ会っても、渡せるように。
今日、わたしのクラスに、転校生がやってくる。
佐々波燐くん。
わずらっていた難しい病気を治すために、わたしたちが小学校にあがる前に、燐くんはアメリカに引っ越してしまった。
だから……六年ぶりになるのかな。
秋めいた、涼しい風がイチョウの並木を抜けていく。
青葉から、黄金色に染まりつつあるイチョウの葉。
なんだかフレンチネイルをしているようで、少しだけおしゃれ。
その中途半端なのに、かわいいイチョウの葉が、わたしはすきで毎日、登校するたびに、ながめていた。
幼稚園のときの、金色に色づいた光景を思い出すな……。
「まだ、イチョウの葉を降らせてるの? 懐かしいね、金色の雨」
秋の風みたいな、涼しげな声。
それは、小さいころに比べて、ずいぶん大人びたものに変わっていた。
でも、ぜったいそうだ。
この声は——。
「り、燐くん?」
「なんで、疑問系……ぼくだって確信、なかったの? ぼくはすぐに、陽菜だってわかったのに」
うれしそうにほほ笑んでくれる燐くんに、わたしは急いで駆け寄った。
「ち、ちがうよ。まさか、朝に会えるとは思ってなくて」
「ふうん」
黒蜜色をしたふわふわの髪に、猫のような丸い釣り目。
あのころと変わらない、まっすぐなまなざし。
そして、向かいあって立つと、すぐにわかる。
わたしよりも、頭ひとつぶん身長が高くなった、燐くん。
幼稚園のころは、同じくらいの高さだったのに。
離れ離れになっているうちに、わたしたち中学生になったんだな。
「燐くん、元気に……なったんだ」
「うん。もう全快」
「小さいころに住んでた、あの家に帰ってきたんだよね? 宝井神社の近くの」
「そうだよ」
「おじさんと、おばさんは元気? 挨拶しに行ったほうがいいよね」
「平気。昨日、陽菜とうちの両親、すでに挨拶すませたらしいみたいだから」
燐くんは、すっと車道側に立つと、わたしを自然に歩道のほうへとうながした。
「ほら。遅刻するよ。いっしょに行こう」
「……うんっ」
久しぶりに、燐くんと並んで歩く。
すると、ふわりと幼稚園のころを思い出した。
燐くんの両親から、特別な許可を得て、一度だけ、ふたりで町を歩いたことがあったんだ。
近所にある宝井神社には、この宝井町でいちばん大きな銀杏の木があった。
秋になると、黄金色の銀杏の葉が、ひらひらと舞って、きれいなんだ。
それをふたりで、両手いっぱいに集めて、金色の雨を降らせる。
その光景が、きれいで、きれいで、わたしはだいすきだった。
でも……そのあと——。
「陽菜。どうしたの」
ずっと黙っているわたしの顔を、燐くんが心配そうにのぞきこんだ。
「えっと、何でもないっ」
「……幼稚園のころのこと、思い出してた?」
「う……うん」
燐くん、幼稚園ころはいつもわたしの前を歩いていたのに、今日は隣を歩いてくれてる。
わたしの歩幅に合わせてるのかな。
「陽菜。覚えてる?」
「……なに?」
「宝井神社に、いっしょに行ったときのこと」
どきん、と心臓がはねた。
「うん、覚えてるよ」
「ふたりで、銀杏の葉っぱを集めて……空に向かって、投げて遊んだよね」
「そうそう。金色の雨だっていってね」
でも、そのあと、燐くんは大変なことになったんだ。
イチョウの金色の雨を降らせるのが、楽しくて、わたしは大はしゃぎだった。
燐くんは、わたしを喜ばせようとしてくれて、たくさんイチョウの葉を降らせてくれて。
わたしは、楽しくて楽しくて、帰りもなんだか落ち着かなくて。
いつもは、しっかり守る信号を、つい見逃してしまって。
赤信号のまま、飛び出しちゃったんだ。
走ってきたトラックのクラクションの音は、いまだに忘れない。
もうダメだ、って思って、わたしは目をつむった。
気づいたときには、わたしは、小さい燐くんの腕のなかにいた。
トラックの運転手さんや、通行人のおとなたちが、いろいろやってくれたみたいだけど、わたしの頭のなかは真っ白で。
わたしのせいで、燐くんが死んじゃったって、その場でわんわん泣いていた。
燐くんは、奇跡的に数か所の擦り傷ですんだみたいだったけれど。
わたしは燐くんと、燐くんの両親に何度も謝った。
誰も、わたしを責めなかった。
みんなが、大丈夫だよっていってくれるたびに、申し訳なかった。
燐くんは、わたしの命の恩人だから……。
「あのころは」
燐くんが、わたしのほうを見つめながら、懐かしむようにいう。
「陽菜との思い出が、これからも増えていくんだとばかり思ってた。春も、夏も、秋も、冬も、もっともっと」
さみしそうに話す燐くんに、わたしの胸がぎゅっと締めつけられる。
「やっと――陽菜と再会できた」
燐くんが、まぶしそうに、その猫みたいな目を細めた。
「ぼくは、あのとき、きみがぼくにくれた言葉、忘れてないよ」
「……え?」
すると燐くんは、困ったように眉尻を下げながらも、そっとほほ笑んでくれた。
「まあ、いいよ。ぼくたちには、これからたくさんの時間があるんだ」
時間、か……。
もう、わたしはただ、泣いてるだけの子どもじゃない。
燐くんを守る、力を手にいれたんだ。
今度こそ、燐くんに悲しい顔はさせない。
「——そうだ。燐くんに渡したいものがあるんだ」
「渡したいもの……?」
「うん。受け取ってくれる?」
「きみが、くれるものなら」
おだやかに、ほほ笑む燐くんに、わたしは胸の奥が苦しくなる。
制服のポケットから、青い石をひとつ取り出して、燐くんに渡した。
燐くんは、いっしゅん目を見開き、驚いたように、それを受け取ってくれた。
「これは……宝石? ぼくに、くれるの?」
あからさまに戸惑う、燐くん。
そ、そうだよね!
いきなり、石なんて渡されたら、誰だってびっくりするよ。
「えーっとね。パワーストーンみたいなものだよ。燐くんに持っててほしいんだ。燐くんをあぶないものから、守ってくれると思う」
「……あぶないものから? だったら、きみが持ってたほうがいいんじゃない」
「へっ? な、なんで?」
「きみ、昔から、よく転んでたし」
幼稚園のころのことを懐かしむように、にやりと笑う、燐くん。
わたしは、当時のことを思い出して、じわじわと顔が熱くなる。
そりゃあのころは、いまのわたしより、どんくさかったかもしれないけど!
いまは、変わったんだから!
「ちょっと。なんで、そんなむかしのこと、覚えてるの」
「きみのことだから」
「もうっ。いいから。これは燐くんに持っててほしいの」
すると燐くんは、すねたように、くちびるを尖らせた。
「……ぼく、もう元気になったんだけど。まだ、ぼくのことが心配なの?」
病気の治療のために、燐くんは、宝井町から引っ越していった。
昔は、家に閉じこもっていたから色白だった肌も、あのころよりは少しだけ陽に焼けてる。
無事、全快したっていってたし、もう病気の心配はないことは、わかってるよ。
ほんとうに、元気になってくれて、わたしも嬉しい。
――でも。
「ただの、お守りだよ! 深く考えないで。帰国祝いみたいなものだから」
「……そう。わかった。それじゃあ、ありがたくいただく」
嬉しそうに、燐くんは太陽に向けて、石をかざしている。
青い石が、きらきらと光って、ほんとうに宝石みたいだ。
青は、わたしの星成力の色。
燐くんを守るという、決意の青色なんだと、セルヴァン会長がいっていた。
家に帰る道を歩いていると、セルヴァン会長が、闇に溶けるようなしずかな声でいった。
「歌仙くん——ついに……『アステル』が日本に帰ってくるんですね」
「セルヴァン会長。あいかわらず、神出鬼没ですね」
「それほどでも」
さっきまでは、わたししかこの夜道を歩いていなかったのに、この人はいつも急にどこからか現れる。
「褒めてないですっ。それに……」
セルヴァン会長のいったことの間違いをただすように、わたしは、ゆるゆると首を振った。
「アステルじゃありません。佐々波燐くんです。ちゃんと覚えてください」
燐くんが、宝井町に帰ってくる。
それは、わたしの怒涛の日々の、はじまりを意味していた。
「ええ、努力します」
「燐くん、二学期からは、いっしょに宝井中学校に通えるみたいです。朝、お母さんがいってました」
うれしさを隠しきれずにいると、セルヴァン会長がスッと目を細めた。
まるで、猫みたいに。
「アステルがこの町に来るってことは……いよいよ、はじまりますね。アステル百年祝祭が」
「はい」
「準備は、よろしいですか? これから、あなたはとても忙しくなりますよ」
「いいんです。わたしが、望んだことだし」
「永遠に、戦い続けなければならなくなっても……ですか?」
胸が締めつけられそうになる気持ちを抑えながら、わたしは返事をする。
セルヴァン会長が、わたしの顔を覗きこんだ。
そのきれいな顔が、ふんわりとした月の光のなかにぼんやりと浮かびあがる。
「アステルは、この町に戻る運命だったのでしょう。そして、あなたが『星成士』という道を選ぶことも、運命だった」
セルヴァン会長は、月の光のような髪をゆらりとゆらした。
夜空色のスーツを身にまとったすがたは、この世のものではないのではないかと思うほどに、きれいだと思ってしまう。
「安心してください。祝祭が永遠に終わらなくても……ぼくは、アステル星成士財団の会長として、あなたを見守り続けます。なにしろ、あなたの選んだ道は、祝祭はじまって以来の異例のことですから」
「改めて聞きますけど……祝祭をはじめないようにすることは、できないんですよね」
厳格な表情で、わたしを見おろす、セルヴァン会長。
「それは、できません。『星』が定めた、ルールですから」
いい終えたと同時に、闇に消えるセルヴァン会長を見届けたあと、わたしはひとり、夜道を歩く。
今日の修行も、ぶじにおわった。
星成士……みずからの力を使って、あらゆるものを生み出すものたち――のこと。
わたしはこの六年間、星成士としてつよくなるためだけに、修行を続けてきた。
祝祭までのカウントダウンは、もうはじまっている。
燐くんが、この宝井町についた、その瞬間。
星成士たちのアステルを賭けた戦い――アステル百年祝祭が、スタートする。
■
朝の通学路、歩きながらポケットのなかを確認する。
くるりとなかをかき混ぜると、入っている石が、じゃらりと音を立てた。
いち、に、さん、し、ご。
「うん。数はじゅうぶん」
足りるのかはわからないけれど、このくらいの数はいつも持ち歩くことにしていた。
『星成石』。
わたしの導力――星成士だけが持つ、ふしぎな力――がこもった、手作りの石。
わたしの導力の色は青いらしいから、海みたいに透き通った青い石ができあがる。
燐くんが、もうすぐ日本に帰ってくると聞いて、一週間前から準備してた。
いつ会っても、渡せるように。
今日、わたしのクラスに、転校生がやってくる。
佐々波燐くん。
わずらっていた難しい病気を治すために、わたしたちが小学校にあがる前に、燐くんはアメリカに引っ越してしまった。
だから……六年ぶりになるのかな。
秋めいた、涼しい風がイチョウの並木を抜けていく。
青葉から、黄金色に染まりつつあるイチョウの葉。
なんだかフレンチネイルをしているようで、少しだけおしゃれ。
その中途半端なのに、かわいいイチョウの葉が、わたしはすきで毎日、登校するたびに、ながめていた。
幼稚園のときの、金色に色づいた光景を思い出すな……。
「まだ、イチョウの葉を降らせてるの? 懐かしいね、金色の雨」
秋の風みたいな、涼しげな声。
それは、小さいころに比べて、ずいぶん大人びたものに変わっていた。
でも、ぜったいそうだ。
この声は——。
「り、燐くん?」
「なんで、疑問系……ぼくだって確信、なかったの? ぼくはすぐに、陽菜だってわかったのに」
うれしそうにほほ笑んでくれる燐くんに、わたしは急いで駆け寄った。
「ち、ちがうよ。まさか、朝に会えるとは思ってなくて」
「ふうん」
黒蜜色をしたふわふわの髪に、猫のような丸い釣り目。
あのころと変わらない、まっすぐなまなざし。
そして、向かいあって立つと、すぐにわかる。
わたしよりも、頭ひとつぶん身長が高くなった、燐くん。
幼稚園のころは、同じくらいの高さだったのに。
離れ離れになっているうちに、わたしたち中学生になったんだな。
「燐くん、元気に……なったんだ」
「うん。もう全快」
「小さいころに住んでた、あの家に帰ってきたんだよね? 宝井神社の近くの」
「そうだよ」
「おじさんと、おばさんは元気? 挨拶しに行ったほうがいいよね」
「平気。昨日、陽菜とうちの両親、すでに挨拶すませたらしいみたいだから」
燐くんは、すっと車道側に立つと、わたしを自然に歩道のほうへとうながした。
「ほら。遅刻するよ。いっしょに行こう」
「……うんっ」
久しぶりに、燐くんと並んで歩く。
すると、ふわりと幼稚園のころを思い出した。
燐くんの両親から、特別な許可を得て、一度だけ、ふたりで町を歩いたことがあったんだ。
近所にある宝井神社には、この宝井町でいちばん大きな銀杏の木があった。
秋になると、黄金色の銀杏の葉が、ひらひらと舞って、きれいなんだ。
それをふたりで、両手いっぱいに集めて、金色の雨を降らせる。
その光景が、きれいで、きれいで、わたしはだいすきだった。
でも……そのあと——。
「陽菜。どうしたの」
ずっと黙っているわたしの顔を、燐くんが心配そうにのぞきこんだ。
「えっと、何でもないっ」
「……幼稚園のころのこと、思い出してた?」
「う……うん」
燐くん、幼稚園ころはいつもわたしの前を歩いていたのに、今日は隣を歩いてくれてる。
わたしの歩幅に合わせてるのかな。
「陽菜。覚えてる?」
「……なに?」
「宝井神社に、いっしょに行ったときのこと」
どきん、と心臓がはねた。
「うん、覚えてるよ」
「ふたりで、銀杏の葉っぱを集めて……空に向かって、投げて遊んだよね」
「そうそう。金色の雨だっていってね」
でも、そのあと、燐くんは大変なことになったんだ。
イチョウの金色の雨を降らせるのが、楽しくて、わたしは大はしゃぎだった。
燐くんは、わたしを喜ばせようとしてくれて、たくさんイチョウの葉を降らせてくれて。
わたしは、楽しくて楽しくて、帰りもなんだか落ち着かなくて。
いつもは、しっかり守る信号を、つい見逃してしまって。
赤信号のまま、飛び出しちゃったんだ。
走ってきたトラックのクラクションの音は、いまだに忘れない。
もうダメだ、って思って、わたしは目をつむった。
気づいたときには、わたしは、小さい燐くんの腕のなかにいた。
トラックの運転手さんや、通行人のおとなたちが、いろいろやってくれたみたいだけど、わたしの頭のなかは真っ白で。
わたしのせいで、燐くんが死んじゃったって、その場でわんわん泣いていた。
燐くんは、奇跡的に数か所の擦り傷ですんだみたいだったけれど。
わたしは燐くんと、燐くんの両親に何度も謝った。
誰も、わたしを責めなかった。
みんなが、大丈夫だよっていってくれるたびに、申し訳なかった。
燐くんは、わたしの命の恩人だから……。
「あのころは」
燐くんが、わたしのほうを見つめながら、懐かしむようにいう。
「陽菜との思い出が、これからも増えていくんだとばかり思ってた。春も、夏も、秋も、冬も、もっともっと」
さみしそうに話す燐くんに、わたしの胸がぎゅっと締めつけられる。
「やっと――陽菜と再会できた」
燐くんが、まぶしそうに、その猫みたいな目を細めた。
「ぼくは、あのとき、きみがぼくにくれた言葉、忘れてないよ」
「……え?」
すると燐くんは、困ったように眉尻を下げながらも、そっとほほ笑んでくれた。
「まあ、いいよ。ぼくたちには、これからたくさんの時間があるんだ」
時間、か……。
もう、わたしはただ、泣いてるだけの子どもじゃない。
燐くんを守る、力を手にいれたんだ。
今度こそ、燐くんに悲しい顔はさせない。
「——そうだ。燐くんに渡したいものがあるんだ」
「渡したいもの……?」
「うん。受け取ってくれる?」
「きみが、くれるものなら」
おだやかに、ほほ笑む燐くんに、わたしは胸の奥が苦しくなる。
制服のポケットから、青い石をひとつ取り出して、燐くんに渡した。
燐くんは、いっしゅん目を見開き、驚いたように、それを受け取ってくれた。
「これは……宝石? ぼくに、くれるの?」
あからさまに戸惑う、燐くん。
そ、そうだよね!
いきなり、石なんて渡されたら、誰だってびっくりするよ。
「えーっとね。パワーストーンみたいなものだよ。燐くんに持っててほしいんだ。燐くんをあぶないものから、守ってくれると思う」
「……あぶないものから? だったら、きみが持ってたほうがいいんじゃない」
「へっ? な、なんで?」
「きみ、昔から、よく転んでたし」
幼稚園のころのことを懐かしむように、にやりと笑う、燐くん。
わたしは、当時のことを思い出して、じわじわと顔が熱くなる。
そりゃあのころは、いまのわたしより、どんくさかったかもしれないけど!
いまは、変わったんだから!
「ちょっと。なんで、そんなむかしのこと、覚えてるの」
「きみのことだから」
「もうっ。いいから。これは燐くんに持っててほしいの」
すると燐くんは、すねたように、くちびるを尖らせた。
「……ぼく、もう元気になったんだけど。まだ、ぼくのことが心配なの?」
病気の治療のために、燐くんは、宝井町から引っ越していった。
昔は、家に閉じこもっていたから色白だった肌も、あのころよりは少しだけ陽に焼けてる。
無事、全快したっていってたし、もう病気の心配はないことは、わかってるよ。
ほんとうに、元気になってくれて、わたしも嬉しい。
――でも。
「ただの、お守りだよ! 深く考えないで。帰国祝いみたいなものだから」
「……そう。わかった。それじゃあ、ありがたくいただく」
嬉しそうに、燐くんは太陽に向けて、石をかざしている。
青い石が、きらきらと光って、ほんとうに宝石みたいだ。
青は、わたしの星成力の色。
燐くんを守るという、決意の青色なんだと、セルヴァン会長がいっていた。