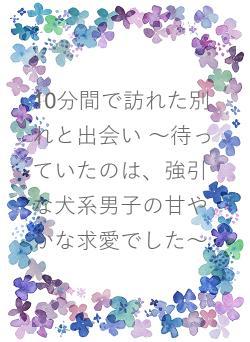「……浅羽くんも、さみしかったんだね」
――だけど、先に口を開いた音無さんの言葉が、俺の心臓にツキリとささった。
「……分かったようなこと言わないでくれる? 音無さんに俺の気持ちなんて分かるはずもないだろ」
だから思わず、突き放すようなことを言ってしまった。
それは多分、図星をつかれたからだ。
音無さんの言う通り、俺は……さみしかったんだと思う。
だから、そんなさみしさを少しでも紛らわせるために、一人で夜の街をさまよったりした。
不良だなんだと噂されるようになったのは、塾帰りなんかにそれを目撃した同じ中学校の生徒がいたからだ。それに尾ひれはひれがついて回り、危ないことをしているなどと影で囁かれるようになった。
まぁ、俺としてはだれにどう思われても問題ないから、自分からそれを否定して回るようなまねはしなかったけど。面倒だし。
だけど音無さんには……今更かもしれないけど、そんな風に勘違いされたくないと思った。幻滅されたくない。
音無さんがはなれていくのが、こわいと思ったんだ。